幼馴染のが男と別れたらしい。そんな話を兄貴から聞かされ、オレはすぐに彼女を食事に誘った。その日はの誕生日だったからだ。
でも結局急な仕事が入っていけずじまい。だからその帰り道、深夜にも関わらず、オレはついの家へ立ち寄ってしまった。
「竜ちゃん、どうしたの?」
は酷く驚いてたけど、入ってと部屋へオレを招き入れ、熱いコーヒーを淹れてくれる。普通なら夜中に尋ねてきた幼馴染なんて面倒だと思うのに、彼女は相変わらずオレを甘やかすのが上手だ。
ふと見れば、の髪が前に会った時よりも少しだけ伸びていた。何だかんだと忙しくしてたから、と会うのは1ヶ月ぶりだ。
本当なら昨日の夜、二人で食事に出かけるはずだったのに。
「昨日はごめん。誘ったのオレなのに」
「いいよ。竜ちゃん忙しいの分かってるし」
「せっかくの失恋パーティしてやろうと思ってたのに」
「だからぁ、それホントしなくていーから」
は苦笑しながらもオレの方をジロっと睨む。だけどオレはそれを敢えてやることで一つのケジメをつけたかった。
には最近まで恋人がいたけど、ソイツと別れたって聞いた時、今度こそ自分の気持ちを彼女に伝えようと思っていた。
長いこと幼馴染という関係を続けて来たけど、そろそろ素直になってもいい頃だ。
他の男の話を聞かされるのはいい加減ウンザリだった。
「、明日は……っていうか今日は仕事?」
「ううん。実は休み取ったの」
「え、マジで」
「だって昨日はいーっぱい竜ちゃんに奢ってもらって高いシャンパン飲むつもりだったもん。そしたら次の日仕事なんか行けないでしょ?」
オレの幼馴染はちゃっかりしてるわ、マジで。
思わず吹き出せば「でも誰かさんのせいでひとり寂しくビール飲んで寝た」と彼女はスネたように目を細めている。誕生日をひとりで過ごすなんて最低と笑う彼女に、オレは笑みが零れた。
「じゃあ……今夜、その穴埋めさせてもらうわ」
苦笑交じりでそう言えば、彼女は驚いた顔で振り向いた。
「……え、うそ。いいの?竜ちゃん、忙しいんでしょ?」
「いや……昨日が大変だったから、まあ昼間は仕事だけど夜は空けてある」
「でも空いた時間は他の人とデートとかじゃないの?前はよくどっかのモデルとデートしてたじゃない」
「あ~、そういうの、もうやめたんだよね、オレ」
「……そういう……のって?」
が不思議そうな顔で首を傾げる。この様子じゃは全然気づいてないみたいだ。
オレはコーヒーを飲みながら、視線だけに向けると「好きでもない子とのデート」と言った。
はギョっとしたような顔を見せて「好きじゃなかったの?」と驚いている。
「……まあ。本命の子にはいつも恋人がいたからな」
「本命って……竜ちゃん、そんな子いたの?」
「いるよ、それくらい」
は今度こそ本当に驚いたみたいだ。冬の夜のような黒く澄んだ瞳を大きく見開き、伺うようにオレを見ている。
でも当然か。自分の気持ちに気づいてからずっと、には気づかせないように接してきたんだから。
オレや兄貴のいる世界とは無縁の子だから、バレないように心を押し殺して、普段通りの自分を誇張して見せてきた。そのたびに呆れられたりしたこともあったし、沢山心配もかけたけど、それも今日で終わりにしたい。
本当のオレは優しくないけど、唯一の前でだけは優しい男でありたいから、取り繕うような嘘はもう必要ない。
「誰だと思う?」
黙ってを見つめると、彼女は戸惑うように瞳を揺らして、それから視線を反らした。
その後も視線が合ったかと思えば、またそれは離れて、忙しなく動いている。
まあ、その答えは明日の夜でもいいか、と思いながら、彼女の戸惑う姿を眺めていた。
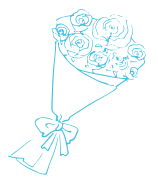
朝方、二人でコーヒーを飲んで、その後に少しだけ寝て、竜ちゃんは太陽が上がり始めた頃に一度マンションへ戻ると言って帰って行った。
私は竜ちゃんを見送った後、せっかく休みをとったんだから、とベッドに戻って再び夢の中へ。
次に目が覚めたのは、宅配を知らせるインターフォンが鳴った時だった。
「竜ちゃんから……?」
宅配のお兄さんが配達してくれたのはハイブランド名が刻印された大人っぽい黒のリボンを施された大きな箱だった。
驚いて開けてみると中にはメッセージカード。
"誕生日おめでとう!今夜のデートはこれ着て"
デート?着て?と訝しく思いながらも箱の中身を出してみると、そこには私に似つかわしくない黒のドレスと黒のハイヒールが入っていた。
「うそ……」
そのいかにも本命にあげるようなプレゼントに、寝起きでボケていた頭が一瞬で覚醒した。
そして竜ちゃんからのプレゼントが届いてから一時間経過――。
私はドレスとハイヒールを交互に眺めながら、未だ竜ちゃんの真意を図りかねていた。
このプレゼントはいったいどういうつもりなんだろう。
そもそも昨日の誕生日、突然食事に誘ってきたとこからしておかしかった。
これまで私の誕生日とかクリスマスとか、イベント的な日に会うのは避けてる様子だったのに。
"本命の子にはいつも恋人がいたからな。――誰だと思う?"
さっき竜ちゃんの言ってた言葉がぐるぐる回ってる。あの時、竜ちゃんは真っすぐ私を見て、そう言った。
だからまさか、とか、もしかして、なんて少しだけ自惚れそうになった。
でもすぐにありえない、と淡い期待を打ち消して、つい「知らない」と答えて「眠たいから寝る」と答えを探る前に逃げてしまったのだ。
竜ちゃんはいつものように笑ってそれ以上何も言ってこなかったし、だからやっぱり私の自惚れか……と再確認させられて少しだけ落ちこんだというのに。
「こんな高級なプレゼントなんて今までくれたこともないくせに……突然何なの……?」
私はずっと竜ちゃんが好きだった。子供の頃からずっとだ。
気づけば一緒にいるのが当たり前だった"カリスマ兄弟の弟"が初恋で、今日までずっとその想いは変わらない。
だけど竜ちゃんにとって私はいつまでも"妹"や"幼馴染"で、その枠から抜け出せないと思っていた。
あれは中学の頃、蘭ちゃんと竜ちゃんが暴走族の人と決闘をして大怪我をさせたことがあった。一人はそれが原因で死亡。
少年院に入ると聞いた時、しばらく二人に会えなくなるんだと思ったら無性に怖くなった。
結局、二人が少年院へ入ってからは二年ほど疎遠になり、私が高校二年の頃、街中で蘭ちゃんと竜ちゃんにバッタリ会った。
それからまた竜ちゃんと連絡を取り合うようになったけど、あれは今思えば蘭ちゃんのおかげだった。
――、ケータイ番号教えてー。
蘭ちゃんがあのノリで聞いてくれたおかげで、竜ちゃんもしょっちゅう連絡をくれるようになり、1ヶ月に1度くらいのペースで会うようになって。でも再会した竜ちゃんは、昔よりもだいぶチャラくなっていた。
恵まれた容姿のおかげで寄って来る女は数知れず。そんなのを近くで見ていたら、私の入る余地なんていつまで経っても来そうになくて、私も寂しさを埋めるように他の男と恋をするようになった。
でも去年から付き合っていた彼にやっとプロポーズまでされたというのに、先週いきなり振られてしまった。
プロポーズされたことを竜ちゃんに話したら、オレが見極めてやるから会わせろというので彼に紹介した直後のこと。
「、あの幼馴染のこと好きなんだろ」
初めて彼氏を竜ちゃんに紹介したからか、私は終始ぎこちなかったんだと思う。ズバリ彼にそんな話を切り出され、すぐに違うと言えなかった私が悪い。プロポーズの返事すらしていなかったことも仇になり、あっけなく別れることになった。
でも、だから竜ちゃんが誕生日に私を誘ってくれたんだと思ってた。
「失恋パーティしてやるよ」
なんてからかうように電話してきて、一瞬断ろうと思ったけど、こんな機会は滅多にない。だからOKしたのにドタキャンされ、私はつくづく男運がないんだと少し落ち込んだりもしてた。
「なのに何で今更デートなのよ……」
プレゼントのハイヒールを指でつまんで呟く。これまで何度も一緒に食事は行ってるけど、一度もそんな単語を口にしたことなんかなかったくせに。
「期待なんてしないんだから……」
同じ男に何度も失恋したくはない。そう決心して、今夜は最初の予定通り、高級シャンパンをたらふく飲んでやろう、と心に決めた私は、出かける用意をするべくバスルームへと飛びこんだ。
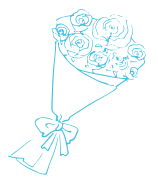
そこは豪華な装飾と煌びやかなイルミネーションや品のあるシャンデリアで飾られた、いわゆる超高級ホテルのレストランだった。大理石で出来た床を歩くたびに響くヒール音がどことなく気恥ずかしい。
そしてエスコートしてくれるのは普段のラフな格好ではなく、高級スーツに身を包んだ幼馴染だ。
他の女性客達の視線が一斉に竜ちゃんへ向けられる。正直この状況は考えていなかった。
いつもは違う意味で注目を浴びてる人だけど、まともな恰好をしたら更に人目を惹く男だというのをすっかり忘れていた。
それくらい今日の竜ちゃんはカッコ良くて、そんな竜ちゃんの隣にいるのが私でいいのかと申し訳ない気持ちになってくる。
「ね、ねえ……ほんとにここで食事するの……?」
1番奥のテーブルに案内され、座った後でも落ち着かずにそんな質問を投げかけると、竜ちゃんは呆れたような笑みを浮かべた。
「何だよ、今更。が言ってたんだろ?一度でいいからここで食事したいって」
「そ、それ就職した時の話じゃない」
「でも一度も行けてなーいってこの前言ってたじゃん。彼氏に強請ったけどスルーされたって」
「そ、それは……そうなんだけど……」
「だからオレが初めてオマエを連れて来てやりたかったんだよ」
「……え」
意味深な言葉を吐いて、竜ちゃんは優しい笑みを浮かべた。その言葉も、表情も、全てにドキドキしてしまう。期待なんかしないと誓って来たというのに、その決心が容易く鈍りそうになるのだから嫌になる。そもそも竜ちゃんと二人でレストランなんて来たこともないのだ。
「私はいつもの店とかで良かったのに……」
「せっかくの誕生日デートなのに、いつものバルとかじゃ恰好つかねえだろ」
「デ、デートって……私の失恋パーティなんでしょ?」
「それはただの理由付け」
「え……?」
それはどういう意味?と訊こうとした時、アペリティフとオードブルが運ばれて来て会話は一時中断した。
けど人気店なのによくここをリザーブ出来たなと不思議に思った。
やっぱり日本の裏社会を牛耳る梵天の幹部ともなれば、色んなところにツテがあるのかもしれない。
「んー!美味しい……!」
「そ?なら良かった」
私の顔を見て満足そうに微笑む竜ちゃんは、いつになく大人の男性に見える。いや、もうお互い大人なんだけど、竜ちゃんは未だに子供みたいな時があるから余計にそう見えてしまうのかもしれない。
「でも……何で急にドレスなんてくれるの?」
そう、そのことも聞こうと思っていたのだ。待ち合わせた場所にいった瞬間、竜ちゃんは「ちょー似合ってる」と大げさに誉めてくれたものだから、恥ずかくなって訊きそびれてしまった。
改めて尋ねると、竜ちゃんはキョトンとした顔で「何でってあげたかったから」とだけ言って微笑んだ。
「だ、だから何であげたいなんて……」
「これまでの分、取り戻したくて」
「これまでの……って?」
「そういう話はあと。今は食べとけよ」
次々に運ばれてくる料理を見て、竜ちゃんが笑った。確かに今は食べることに集中した方がいいかもしれない。
そこは素直に言うことを聞いて、まるでオブジェのような盛り付けをされた料理に感動しつつ、出されるままに食べて飲むことに専念した。
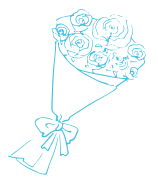
「あー最高に美味しかった。竜ちゃん、ご馳走様」
「いえいえ。あれくらい」
レストランを出て、私がお礼を言うと竜ちゃんは笑いながらわざと畏まった口調で応える。料理もお酒もたらふく堪能した私は、久しぶりに幸せな気持ちになっていた。
約束通り、高級シャンパンを一人で2本は飲んでしまった私は、多分いや、絶対に足元がフラついてる。
案の定、よろけた私の肩を竜ちゃんがスマートに支えて転ばないようエスコートしながら歩いてくれる。
「ご、ごめん」
「別にいいけど、マジで2本も飲むとは思わなかった。少しは考えろよ」
「だ、だって美味しかったんだもん……。梵天の幹部さまならあれくらい微々たるもんでしょー?」
「お金のことじゃなくて体の心配してんの。せっかくのデートなのに飲み過ぎだし」
「まだデートとか言っちゃって……。あー分かった。竜ちゃんってば女の子弄びすぎて、幼馴染の私しかデートする相手いなくなったんでしょ」
掴まってる竜ちゃんの腕に自分の腕を絡めて笑えば、彼は小さく溜息をついた。
「そんなんじゃないよ。オレはとデートしたかったの」
「ま、またまたそんなこと言って……。私なんか口説いたって何も出ませんよーだ」
「はあ……マジで酔っ払いだな」
「すみませんね。このままタクシー乗せてくれたら、ちゃんとひとりで帰るから」
呆れたように私を見下ろす竜ちゃんを見上げると、不意に目が合った。あまりに真剣な目で見て来るから、胸がドキリと音を立てる。
「誰が帰すって言った?」
「……え?」
竜ちゃんは私の肩を抱いたまま、エントランスではなく、何故かエレベーターホールの方へ歩いて行く。何で、と聞く前に、竜ちゃんは「部屋、取ってあるから」とあっさり言ってエレベーターを呼ぶボタンを押した。
私は驚き過ぎて言葉もなく、ただ口をパクパク動かすことしか出来ない。
周りには泊り客と思われるカップルも何組かいるからだ。
そうこうしている内にエレベーターが到着し、竜ちゃんは私の肩を抱いてそれに乗り込んだ。
何故か他の客は乗って来なかったけど、その疑問よりも何よりも私の意識は別のところに向いていた。
「ちょ、へへ部屋って……な、何?!」
エレベーター内、二人きりになった途端、そんな抗議とも取れる言葉が口から飛び出した。
これまで何度となく竜ちゃんには驚かされて来たけど、今日はその中でもダントツに理解が追いつかない。
目に見えて慌てている私を見下ろすと、竜ちゃんは小さく吹き出して「、耳まで真っ赤じゃん」なんて言って笑っている。
「だ、だって竜ちゃんが……いつもと違うから――」
「言っただろ。今夜はデートだって。誕生日デートならホテルリザーブするのは当然だし」
「だからそれは普通、恋人同士がするデートでしょ?私達は違うじゃん……きゃっ」
急に顔を上げたせいで足元がフラつき、壁に肩をぶつけそうになった。でもその前に竜ちゃんの腕が伸びて来て、腕と腰を引き寄せられる。一気に距離が縮んで、私はアルコールとは別に顔が火照るのを感じた。
こんな風にされたことは一度もない。
「……」
「……」
「夕べ……オレが言ったこと、覚えてる?」
「……夕べ?」
「本命の子の話」
ドキっとして思わず顔を上げてしまった。もちろん覚えてる。そのせいで私が自惚れてしまいそうになったのだから。
でも私が応える前に顏が翳って、えって思った時にはもう唇に柔らかいものが押し付けられていた。
一瞬、何が起こったのか分からないまま。目を見開いて固まっている私の唇を何度か啄んだ竜ちゃんは、最後名残惜しそうにちゅっとリップ音を立てて唇を離した。
「な、何で……」
「今日は質問ばっかだな、は」
竜ちゃんは艶のある笑みを浮かべながら私の腰を抱き寄せた。いつの間にか竜ちゃんと壁の間に挟まれて、逃げ場すらない。
「だ、だって質問したくなるようなことばかり……って、な、何してんの?っていうか誰か乗って来たら――」
腰に回した手で背中を撫でながら、竜ちゃんは身を屈めて私の首筋に口づけてきた。慌てて身を捩りながら顔を反らすと、今度はアップにしたことで露わになっている耳にもちゅっとキスをされる。
音が直接脳に響いて思わず肩が跳ねてしまった。
「スイート直通エレベーターだから誰も乗って来ない」
「……え?」
「安心した?」
「そ、そんなわけ――」
ないと顔を上げると、また唇を塞がれた。抗議したいのに、初めて触れた竜ちゃんの唇が優しくて、身も心も蕩けて崩れ落ちそうだ。
男の人にこんな甘いキスをされたのは、初めてだった。
「……、目が潤んでる。可愛い」
竜ちゃんからそんな甘ったるい言葉を囁かれるのも初めてで、全ての疑問なんかどうでも良くなって来た。
「が訊きたいこと、全部教えてやるよ」
ベッドの上でね、と付け足した竜ちゃんの表情は、今まで見たこともないくらいに扇情的だった。

