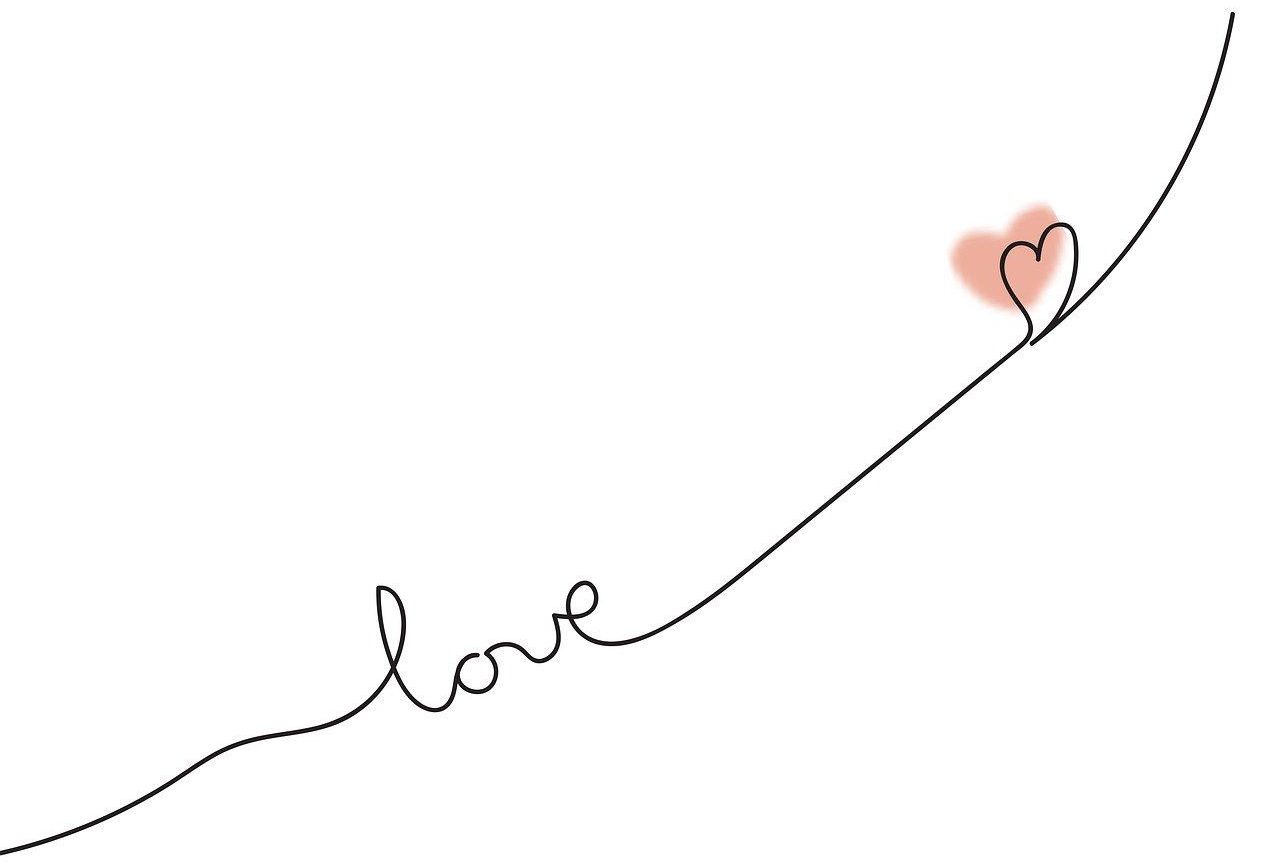転校初日の話-01
1.
その日の夜は、よく知らない男の前で泣いてしまった気まずさで、なかなか寝付けなった。何であんなに感情が昂ってしまったのか自問自答してたのもある。一つ思い当たるとすれば、お父さんの話を持ち出された時、色んな記憶が走馬灯みたいに流れては消えて、もう戻れない頃の思い出を楽しそうに話すお母さんにやたらと腹が立ったこと。過去を忘れて、母娘でこれからを生きていこうって時に、お母さんだけが、まだ過去に縋りついてるように見えたからだ。今、目の前にいない人の話を、すでに過ぎ去った日のことを、嬉しそうに語られたら、娘のわたしはどんな顔をすれば良かったんだろう。幸せだった日々は、もう、この手にないんだから。
(ああ…そうか…現実を突きつけられた気がしたんだな…きっと…)
昔は確かにこの手にあったお父さんからの愛情が、少しずつ零れ落ちていった悲しい現実だ。
しっくりくる答えが出たような気がして、ひとり納得した。そこから記憶がない。引っ越しやら、面接やら、祖父母との顏合わせやら、ついでに見知らぬ男と夕食を共にしたことで疲れもあったんだろう。途中で爆睡して、気づけば朝だった。目覚まし二つかけておいて大正解だ。
「え、ちゃんの初登校の日に、関東一帯初雪?!わ~ほんとに降ってる!」
シャー。カラカラカラ。テレビの音声に交じった大きな声に、カーテンと窓を開ける音。部屋から出ると、お母さんが夕べのことを忘れたように大騒ぎしていた。まあ、こういう人だよね、うん。まだ少し気まずいから助かるけども。
「……嘘でしょ。まだ10月後半だよ?」
「あ、ちゃん、おはよう。大変、雪降ってる!札幌で履いてたブーツ出さなきゃね」
お母さんがアタフタしてるのを横目に、やたらと眠たい頭をスッキリさせるため、顏を洗い、歯磨きをしてからリビングに顔を出すと、お母さんが「見てみて」と窓の外を指す。確かに外は細かい雪がちらつく程度に降っていて、一瞬まだ札幌だっけ?と錯覚しそうになった。っていうか…ここ、ほんとに東京か?
札幌でも降るか降らないかって時期に、まさかの関東に初雪を先取りされるとは…と、ちょっとだけ驚く。まあ、こっちの雪の質は向こうと違うから、そんなに積もらないって話だけど、寒いものは寒い。
「今年の冬はラニーニョ現象の影響で、関東近郊も寒気に覆われる日が多いんだって。こっちは湿度高めでも気温が一気に下がると雪になるって、さっき三郷ちゃんが言ってたの」
「誰よ、みさと」
「めざましテレビのお天気お姉さんよ。ほら、毎朝ちゃんも観てるでしょ」
「……めざまし?」
ああ…あの笑顔が可愛らしい女子アナか、と言われて思い出す。最近はやたらと顔が売りのような女子アナが増えて、タレントなのか女子アナなのかも分からないし、ましてお天気お姉さんやってる人の名前まで、いちいち覚えてられない。ってか、女子アナをちゃん付けとか、友達か。
お母さんはベランダから身を乗り出して「この曇天…まるでちゃんの行く末を暗示してるかのよう…」と、伸ばした手のひらに雪を乗せて溜息を吐いている。白煙のように白くなった息を見ただけで、外の気温はだいたい想像できた。制服の中にヒートテックを着よう、と決心する。
「とりあえず朝から縁起の悪いこと言わないでもらえますか」
「だって関東でこんなに早い初雪なんておかしいじゃない…悪いことの前兆かも…」
お母さんはこの寒いのにベランダの窓を全開にしてバカなことを呟いてる。でもパジャマ姿じゃすぐに限界がきたらしい。「へっぷし!」という芸人ばりの間抜けたクシャミまでしてるから「閉めなよ。また風邪引く」と声をかける。お母さんは術師を辞めたら「体がやわになった」と言ってるくらい、よく風邪を引くから、その辺を気をつけてもらわないと。看病するのはわたしだし。
そのままキッチンに行って、食パンをトースターへぶっこみ、パンが焼ける間に目玉焼きも焼いてしまおう、と冷蔵庫を開けた。
「あー…やっぱ、こうなるよね」
中を見た瞬間、そんな言葉が漏れたのは、ドアポケットの卵置き場に数制限を無視してぎゅうぎゅうに置かれてる卵のせいだ。絶対、買いすぎだと思う。しばらくは卵料理かなと溜息を吐きつつ、テフロン加工のフライパンを熱して、黄身が崩れないよう丁寧に卵を落とす。ジュウゥっという小気味いい音がわたしは好きだ。火が通ると白身のふちに焦げ目がついてくる瞬間も。この時、いつも黄身を半熟にしようか、固まるまで蓋をするかで迷う。今朝は半熟をソースで食べたい気分だった。
「ん~いい匂い」
その匂いに釣られたのか、お母さんがキッチンに顔を出した。
「…ちゃん。お母さん、また寝るから朝食は――」
「うん。ラップかけとく」
お母さんは地味に低血圧で朝は弱い。弱いクセに離婚後は母親としての威厳を保つためなのか、朝はこうして一度は起きてくる。でもすぐにベッドへ逆戻りするのが、今の家ではデフォルトになりつつある。因みに結婚中はお父さんが朝ご飯担当だった。まあ、それも二人がモメだしてからはなくなって、朝晩とわたしが作るようになったんだけど。おかげで料理の腕は格段に上がったと思う。
「ありがと~…ごめんね」
いつもの返事をしながら手を動かしていると、お母さんは盛大な欠伸をかましながら、自分の寝室へと歩いていく。でも、ふとこっちへ振り返ると、意外にも真面目な顔でわたしを見つめた。
「どうしたの?あ、卵焼きの方がいい?」
「そうじゃなくて…」
時短の為に、とお母さんの分も目玉焼きで焼こうとした手を止めると、お母さんは軽く首を振った。
「呪術師って変人多いし、中にはエリート意識の強い意地悪なのもいるから、もしイジメられたらちゃんと言ってね」
「何それ」
今時イジメ?と驚いたけど、お母さんはどうやら本気で言ってるらしい。自分だって呪術師だったくせに、と思わず吹いた。まあお母さんは変な人ではあるけど、意地悪ではないか。むしろイジられキャラだった気がする。
「まあ、そうなったらイジメ返すからへーき」
さくっと応えると、お母さんは「ふふ…ちゃん、サイコー」と言って、そのまま寝室へと消えた。きっと昼まで寝てるに違いない。
昨日、祖父母と今後のことを話し合ったみたいだけど、やっぱり術師としてはブランクがありすぎで現場に出るのは危険だと言われたらしい。と言って普通の仕事なんか出来ないだろうから、と、来年から実家の仕事を継ぐ方向でいくようだ。それまでは「ニート生活満喫しよ~」なんてほざいてた。
因みに、お母さんの家系は代々"呪具師"のようで、武器に己の術式を使って武器を作ったり、破損した呪具を修理したりもする。その界隈ではかなり力のある家柄だった。術師としての現役を引退した祖父母も当然、その仕事は今も請け負っているから、お母さんはそこで働くことになりそうだ。
――ちゃんは生まれた時から特別なのよ。
幼い頃、お母さんはわたしによくそんなことを言っていた。あの頃はその言葉の意味が分からなかったし、分からないまま、お母さんに術式の使い方を教わってたけど、祖父母に会って何となく、自分の本来の力を理解できた気がする。
ふと自分の手を見下ろし、呪力を集中させると、脳内で犀利な小型ナイフを思い浮かべる。出来るだけ鮮明に、繊細に。そうすることで呪力が形を変え、気づけば手の中に本物のナイフを握っていた。想像から造った"呪具"の完成だ。でもこんな即席の呪具は、低級呪霊を祓っただけですぐに壊れてしまう。
お母さんや祖父母はもっとリアルに強い呪具を造れるはずだ。ただ、そこそこ時間を要するらしい。それは普通の人間には数秒ないし、一分もしない程度の差。その僅かな差が、戦闘中という状況下では苦労する場面もあるという。当然、命を危険に晒す可能性も増える。
でもわたしは――本気でやろうと思えば数秒もかけずに構築できる。思い浮かべた瞬間から、それは発現する。
構築術式――家は数百年も前から、脈々とその血を受け継いでいるとのことだった。その力を利用した稼業が、いわば老舗の呪具師というわけだ。その中でもわたしのような"敏速"の構築術師は数が少なく、昔から"特別"だと言われてきたらしい。ついでに呪力量も現役の頃のお母さんより多いようで、燃費が悪いとされてる構築術師にしては、やたらと燃費もいい方だと言われた。要は"脳の違い"だそうだ。
自分の力の根源を教えられ、何故お母さんがお父さんの反対を押し切り、わたしを呪術師にしようとしたのか、本当の意味で納得がいった。
(だからおじいちゃんも必要以上にわたしを可愛がってくれるんだろうなぁ…)
昨日、目の前で披露したら涙ながらに喜ばれてしまった。たかが毒針を一瞬で造っただけなのに。他にも色々リクエストされ、おかげでガラクタ同様の呪具が溢れたけど、それを再び取り込んで呪力に還元できるのが、この術式の強みだ。そもそも自分の呪力で出来てるのだから、超難しいと言われてる還元技もコツさえつかめば簡単だった。まあ造った時の呪力量よりは減るけど。手数料みたいなものだと思えば仕方ない。
おじいちゃん達は還元に苦労したみたいだけど、わたしにはその才能が他の構築術師よりも秀でていると喜んでいた。
通常の構築術師たちは、一度に造れるものは限られているそうで、戦闘で使用できるほどの呪具を構築するには、それなりの呪力がいる。一つ造っただけで脳に負荷がかかり、ぶっ倒れる人もいるという話だ。わたしにはまだその経験がないから、聞かされた時は驚いた。
それでも、この力は――高専で役に立つんだろうか。
血筋がエリート家系というのは分かっても、わたしには幼い頃から受けられるはずだった教育を受けたこともなければ、表立った実績がない。その遅れがどう影響するのかという不安はあるし、高専にはわたしより強い術師がわんさかいそうで、ちょっとだけ怖かった。
(初登校ということで少しだけナーバスになってるのかな…。情けな)
自分の弱さに辟易しつつ、簡単に朝食を済ませて出かける準備をする。そこで初めて昨日受け取ってきた制服に袖を通した。デザインは多少好きに決められると言うから、スカートは前の学校と同じく短めにしてもらったけど、今日の天気を見て少しだけ後悔した。ジャージはまだ受け取ってないから、札幌にいた頃、寒い日によくやっていた、スカートの下にジャージという女子定番のスタイルも出来ない。
ダイチには「だっせーからやめろ」って言われ続けたけど、寒い時にダサいもカッコいいもない!と反論して、ジャージを履き続けたっけ――。
「…はっ」
気づけばダイチとの思い出を振り返ってる自分に寒気がした。夕べお母さんにお父さんの話を持ち出されてキレたはずなのに、わたしも無意識にダイチのことを考えてしまった。つくづく人間の脳は厄介だと思う。一つのことを思い出すと、それに紐づけられた記憶が勝手にずるずる引き出されて、思い出したくないことまで思い出してしまうんだから。
「学校いこ…」
軽く自己嫌悪に陥りながらも、ちゃんと食器を洗い、歯を磨いて、きっちりコートの上からマフラーを巻く。そしてとっくに寝てるであろうお母さんに「行ってきます」と声をかけると、深呼吸をしてから、わたしはドアを開けた。
「あ、おはよ~。今日から学校?」
「……!」
ドアを開けた瞬間、聞こえた声。弾かれたように左を見れば、そこには隣の白髪イケメンがコーヒーカップを手に部屋着姿で――部屋着まで真っ黒だ――立っていた。夕べは頑なに外さなかったサングラスも今はしていない。朝からこのご尊顔は眩しすぎる。青い、いや水色がかった綺麗な瞳がキラキラしすぎて、どこの国の王子さまですか?と聞きたい。いや、どうせカラコンだろうけど。
「おはようございます…。っていうか、この寒い中で何…してるの?」
素朴な疑問を早速ぶつけると、隣人さんは通路の洒落た小窓を開けて「だって初雪じゃん」と理解不能な言葉を発した。ついでに彼が開けた小窓から強い北風が入って雪まで吹き込んでる。開けた張本人は「さっぶ!」と騒いでるんだから呆れてしまう。最上階を舐めんなと言いたい。
というか、初雪だから何?と思ったけど、ふと「関東の人には雪が珍しいから、通勤通学は大変だと分かっててもはしゃぎたくなっちゃうんですよねー」という、お天気お姉さんの言葉を思い出した。そうかそうか。この人もそのクチか。
「ふ……子供」
「ん?何か言った?」
今では窓から顔を出して雪を愛でてる白髪イケメンが小首をかしげる。わたしは「別に」と応えて、エレベーターの方へ歩き出した。雪なんか見慣れてるし、大事な初登校日にあの人と雑談する気分にはなれない。夕べのこともあるし。
それが原因なのか、自然と歩く速度が上がる。でもエレベーターが到着して、いざ乗ろうとした時、「」と呼ばれて固まった。いきなり呼び捨て?と思いながら、一歩だけ下がって通路の奥を見る。すると眩しいほどのご尊顔を晒した隣人さんが「行ってらっしゃい」と言いながら、唐突に投げキッスをしてきた。しかも「ちゅぱぁぁ♡」っというハートと擬音付きで。
「う…」
思わず赤面したのが分かって、速攻でエレベーターに乗り込んだ。寒いはずなのに、何故か頬が火照っていく。それが妙にイラついて、「何なんだ、アイツは…」と悪態をつきながら、心臓の音をかき消すよう、ロビーのボタンを連打した。
少しずつ、少しずつ、わたしの周りが変わっていく。そんな予感がしていた。
2.
「じゃあ半端な時期だが、今日から一年に合流するということでいいか?」
「はい。宜しくお願いします」
初雪の中の初登校。まずは来年から担任になる夜蛾先生のところへ顔を出した。通常の時間より一時間も早く来たせいか「随分早いな」と驚かれてしまった。
「夜蛾先生に色々と聞きたいことがあったんで」
「ん?何だ」
夜蛾先生は今日もサングラスをかけたまま、ふと顔を上げた。わたしは室内をぐるりと見渡しながら、まず「どうして誰もいないんですか?」と尋ねた。いくら早く来すぎたとはいえ、他の教師がいないのが気になったからだ。
「ああ、みんな任務に出てる」
「任務…。ああ…依頼が入れば術師が派遣されるんでしたっけ」
「そうだ。教師といえど呪術師。依頼が重なればこういう時もある。となれば当然、補助監督も動くから、そういう時は高専もこんなもんだ」
「はあ…夜蛾先生は任務入らなかったクチですか?」
納得しつつ、そう尋ねると、夜蛾先生は「俺の術式の関係で今は主に高専内で内勤をしている」と言った。簡潔すぎてよく分からない。
「じゃあ今日の授業とか、どういった内容だとか説明してくれる一年の担任もいないってことですかね」
「ああ、一年の担当教師は昨日から東北に出張中だ。でも教育実習生の教師もどきならいる。聞きたいことがあればソイツに訊け。まあ、まだ来てないがな」
「……何ですか、そのもどきって」
真顔で説明され、少しだけ戸惑った。こんな緩い学校でいいのか?と首を捻る。この時のわたしは、まだ高専がどういった場なのかを理解出来てなかったのかもしれない。
「俺の教え子だった男だ。教師になりたいというから、卒業後に色々と叩き込んで、やっと他人を教えられるくらいの器量が身についたんでな。今年から俺の下で教育実習をさせてる。だから本来は俺のサポート的な役割で二年を受け持つことになるんだが、一年の担当教師が不在がちでな。その穴を埋めるのに、担当教師が不在の時はヤツの勉強もかねて、まずは一年の生徒を任せてるってわけだ。だが来年からは本格的に二年担当の教育実習生として今の一年をそのまま教えることになる」
「はあ…」
「何だ。心配か?」
きっとそんな顔をしてたんだろう。夜蛾先生が苦笑気味に訊いてきた。でも彼の教え子だというし、まさか「はい」とも言えず、慌てて「そんなことはありません」と笑顔を作る。引きつってたと思うけど。
案の定、夜蛾先生は笑いながら「まあ、気持ちは分かる」と言った。
「は幼い頃からお母さんに術式の手ほどきを受けて、かつ呪霊を祓ったりもしてたそうだが、きちんと学ぶのは初めてなんだ。その辺は心配だろうな。だが、まあ…その教え子は色んな意味で優秀だ。人間性はともかく――」
「はい?」
最後の方はモゴモゴとよく聞き取れなかったから聞き返すと、夜蛾先生は慌てた様子で「い、いや…何でもない」とニッコリ微笑んだ。それがやけに不気味だった。
「そろそろ一年の生徒も全員来るだろう。教室はこの二階奥にある。案内しようか?」
「いえ、自分で行けます」
と言って椅子から立ち上がる。ただ転校初日にいきなり一人で教室へ行くのもどうかと思った。そこで「あの…教育実習されてる先生はまだですか?」と尋ねた。いくらわたしが早く来すぎたとはいえ、仮にも教師ならとっくに来てもいい時間だ。夜蛾先生は「もう来るはずだが…」と言いつつ、壁時計を確認した。
「怒るほどでもない遅刻をよくする男でな」
「……大丈夫ですか、その教え子」
遅刻魔と聞いて、遂に本音が口から洩れる。夜蛾先生は何とも困ったように溜息を吐いた。その時、職員室のドアが静かに開く気配がして、わたしと夜蛾先生が同時に視線を向けると、そこには可愛らしい女の子が、わたしと似たような制服を着て立っていた。
「何だ、モカじゃないか。どうした?」
「…お、おはよう御座います。あの…五条先生は…」
モカ、と呼ばれた女子生徒はわたしをチラリと見たものの、すぐに視線を反らした。お人形さんみたいに可愛い顔をしてるのに、何となく冷めた表情の子だなと思う。とりあえず、わたしを見る視線が冷たい。
「ああ、もうすぐ来ると思う。先に教室へ行ってろ」
夜蛾先生がそう言うと、その女子生徒は「はい」と返事をして、すぐにドアを閉めてしまった。まるでわたしは存在しないような空気にされた気がする。それに気づいたのか、夜蛾先生は苦笑気味に「ああ、モカは人見知りでな」とフォローを入れてきた。ついでに「彼女もと同じ一年だ」と言った。途端に教室へ行くのが怖くなる。この時期に転校生ってだけでも敬遠されそうなのに、あんな態度の子が同級生とはついてない。
(ほんとにイジメられたりして…)
ふと今朝お母さんに言われたことを思い出し、気分が滅入ってきた、その時。今度はガラガラガラっと派手な音をさせてドアが開き、夜蛾先生がすぐに椅子から立ち上がった。
「悟!やっと来たのか…遅い!転校生が今日から通うかもしれんと言っておいただろうが!」
「いや~初雪だったから歩きにくくて~」
「そのすぐバレる嘘をつくクセもやめろ。だいたい昨日はお前が休んだせいで、一年担当の阿賀が出張になってるんだから、お前が来なきゃ一年の授業を始められないだろうが」
「はいはい…悪うございましたー。ってか、普通、教え子が入院したって聞いたら、もう具合はいいのかとか、少しは僕の体調心配しない?」
「ただの急性アルコール中毒だろう。そもそも電話してきた時は無駄に元気だったから、ずる休みかと疑ったくらいだ」
「ひでぇ…」
すぐ横でそんな会話が繰り広げられてる。わたしはドアに背を向けて立っていたから、入って来た人の顔は見てない。だけど。夜蛾先生と楽しげに話すその声は、物凄く聞き覚えがあった。
「待たせたね~。」
「……な…」
「ほら、教室行くよ~」
振り向いた途端、視界に飛び込んできた長身の男が、身を屈めてわたしの顔を覗き込む。目の前には見覚えのある白髪にサングラス。瞬時に固まったわたしの頭をクシャリと撫でていく、その教師は、隣に住む、あの白髪サングラスのイケメンだった。