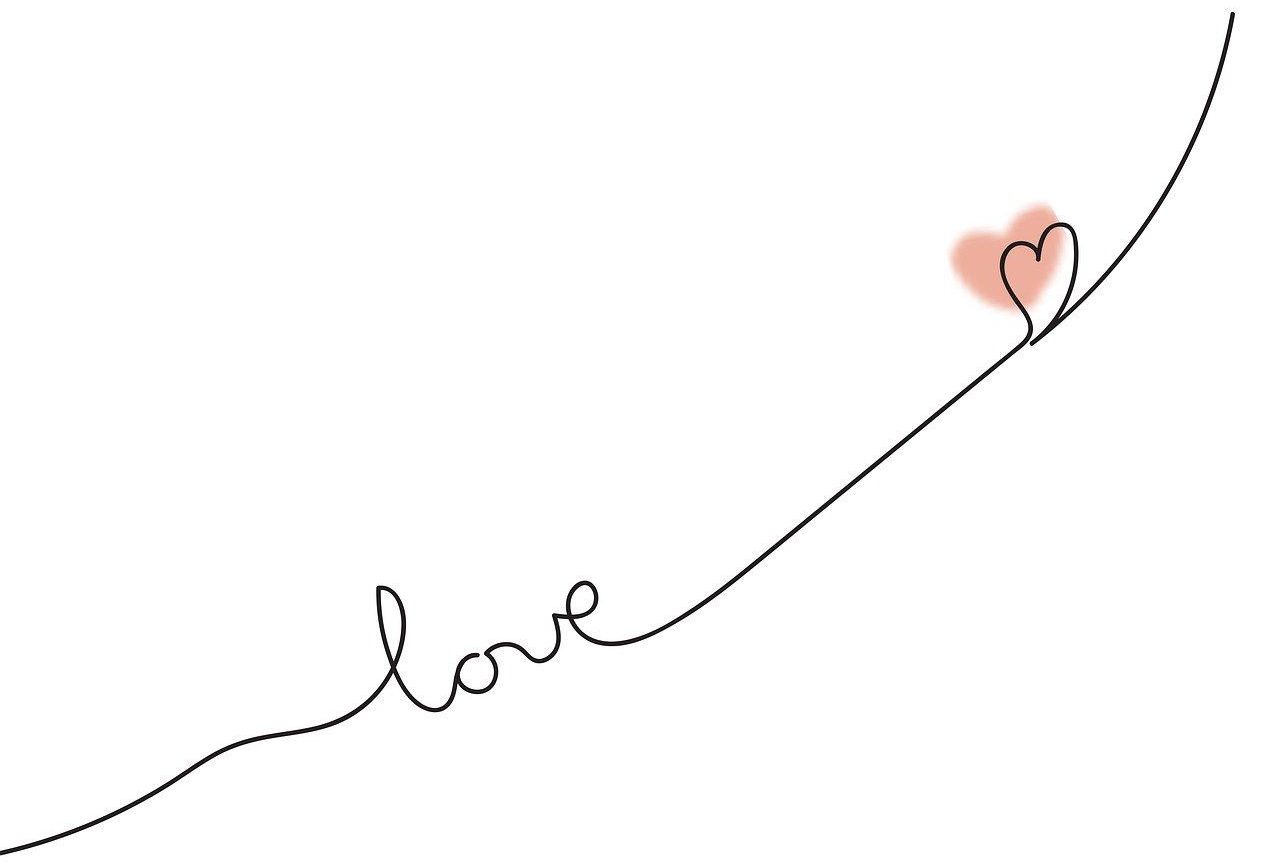転校初日の話-02
脳内、思考停止。"エラー!エラー!"
頭の中でそんな機械音声が聞こえたのは、実はわたしがヒューマノイドだったとか、脳だけ人工知能だとかいうオチではなくて、多分わたしの想像力が豊かなせいだ。その言葉を最後に思考がホントにフリーズしてしまった。でも、いくら想像力豊かなわたしでも、こんな状況は想像すらしていなかった。
「待たせたね~。。ほら、教室行くよ~」
わたしの頭をクシャリと撫で、職員室を出ていく男の背中を見つめながら、大混乱した頭で考えた。彼はいったい何者なんだ、と。夜蛾先生とのやり取りを聞けば、さっき話に出てきた教え子という可能性が高いし、この状況での登場はそれ以外に考えられない。なのに、頭と感情が追いつかないのは予想外のことすぎて動揺してるからだ。
「し…質問」
「はい、どうぞ~」
夜蛾先生への挨拶もそこそこに、フラフラと彼の後をついて行きながら、最終確認の為に声をかける。どうか違うと言って欲しい。
「お兄さん…何者?」
その問いに彼は顔だけこちらへ向けると「僕?」と聞き返しながら、指でサングラスを下げた。
「五条悟。現在、一年担当、来年から二年担当になる教育実習生。兼、特級呪術師だよ。あ、今日から僕のことは"五条先生"って呼んで」
あっさり名乗った隣人の白髪イケメン――五条悟先生は、そのまま教室のドアを開けて、「みんな、おはよ~」と軽快な足取りで中へ入っていく。よくよく見れば、彼は昨日や今朝の私服とは違い、今は高専の制服を着ていた。ボタンが同じだ。わたしは唖然としたまま、ただ今の情報を処理するべく、頭を働かせるだけで精一杯だった。
「えー今日は嬉しいお知らせ!皆さんに新しい仲間を紹介しまーす!」
教壇に立ち、教師らしいことを言いながら、未だ廊下に突っ立ったままのわたしを見る。彼の青い瞳がかすかに微笑んでる気がして、だんだんと顔に熱が集中してくるのが分かった。恥ずかしいからじゃない。もっと別の何かだ。
「え~新しいって転校生?!」
「そうそう」
「ほんまに?!男?女?」
「女の子だよ。ほら、。こっちおいで」
生徒達が騒ぐ中、五条悟と名乗った隣人は、わざとらしいくらいの笑顔で手招きをしてくる。ゆっくり教室に入ったわたしは、無意識に「…です」と自己紹介していた。その間も、沸々と怒りの熱が腹の底から湧いてくる。何だろう。ものすごく質問攻めにしたい気分だ。
「は術師の家系だけど、呪いをきちんと学ぶのは初めてだから、みんなも色々教えてあげて」
隣で尤もらしいことを言ってる彼の声が、わたしの神経を逆なでしていく。っていうか――。
(――あっさりこの状況を受け入れてるとこからして…この人、隣人のわたしが高専の生徒だって絶対知ってたよね?!知ってて知らんぷりしてたよね?!家のことまで知ってるっぽいし!あげく特級術師?!現在3人しかいないって夜蛾先生が話してたあの特級?!そんな規格外の階級の術師が教師って、何の冗談よ!)
沸騰した脳内で思い切り突っ込みながら、「えっと席は~」と教室を見渡している彼を睨む。驚きと恥ずかしさと怒りで、この時のわたしはクラスメートになる生徒達のことなんて、全く見えていなかった。
「モカ。机と椅子、宜しく~。はそこに座って」
「…え?」
そう言われて初めて教室を見渡すと、目の前には男の子二人と、その後ろに女の子が一人、その少し後ろにも女の子が一人座っていた。でも全員が真ん中付近に寄っている。え、もしかして…生徒数ってこれだけ?…少な!
内心、驚いていると、席を立った女の子がわたしの机と椅子を運んできて、何故か自分より更に後ろへ置いた。その子はさっき職員室で見かけたモカというコーヒーみたいな名前の子だ。え、早速イジメ受けてる?
「ハァ…お前ら少ないんだから、もっと真ん中に固まるとかしろよ。何でそうバラバラに座るかなー」
彼が溜息交じりで言えば、一番前の席に座っている茶髪に釣り目の男子が笑いだした。
「少ないからこそ、おのおの好きな場所に座りたいんやけどー。こんなんで固まったら、仲良しグループみたいでごっつ見栄え悪いやん。なあ?ケンタロー」
「俺はどこでも。別に教室にずっといるわけじゃねえし。タクミだけ好きなとこ座ればいいだろ」
話を振られた隣の黒髪のっぽ男子が冷めた顔で頬杖をつく。その後ろに座ってたショートボブの女の子は「じゃあタクミが後ろに来てよ。私が前に座るから」と席を立った。何というか、自由だな、というのが最初の印象。それをニヤニヤしながら見てる彼は特に注意もしない。
(っていうか…ほんとに教育実習中…?教師志望には全然見えないんだけど…)
ジトっとした目で彼を見てると、不意にイケメン顔がこっちを向いた。普通にビビる。
「はは、疑ってる疑ってる」
「…は?」
「コイツが教師志望~?全然見えねーくらい思ってるんでしょ、ちゃん」
「…別に」
何がちゃんだ、と半目で抗議すると、彼は華麗にスルーして「あそこへ座って」と、さっき一番後ろに置かれた机を指す。仕方ないから席に着くと、彼はやっと先生らしく「えー授業を始めます」と定番の台詞を吐いた。え、待って。そう言えばわたし、高専の教科書とかもらってないかも――。
なんて、そんな心配は秒で終わった。彼が「では今から呪術実習に行くよ~」と一人でパチパチ拍手を始めたからだ。何、そのノリ。ここは小学校かな?っていうか、わたしを席につかせた意味よ。
色んなことに引っかかってる合間に、彼は「ついておいでー」と教室を出ていく。いや、だからちょっと待って。他の生徒の紹介くらいしてよ。と思った時だった。茶髪の関西弁男子――確かタクミ?――が「ちょお待って、悟~。俺らのことも転校生に紹介してぇなー」と言いながら立ち上がった。グッジョブ、関西弁男子。
「ああ、そうだった」
うっかり忘れてたらしい。彼は出ていきかけた体をそのままバックさせると、わたしを見ながら「コイツは京都からわざわざ高専に入学した禪院巧」と関西弁男子の肩をポンと叩いた。彼は御三家と呼ばれるうちの禪院家の子らしい。京都にも姉妹校があるにも関わらず、何故か東京校に入学したそうだ。
「どーもー。タクミって呼んでや。俺もって呼ぶし」
「はあ、どうも…宜しく。タクミ…?」
「そうそう。かっこええ名前やろ~?」
ノリが軽い、と思いながら、わたしも笑顔で「そうだね」と応えておく。こういうノリの方が馴染みやすいし、何事も最初の印象が肝心だ。そして彼は次にタクミの隣に座ってた黒髪のっぽくんを見て「んで、こっちが高藤健太郎」と紹介した。彼は東京育ちで親が元呪術師ということだった。高藤くんがわたしに軽く会釈をするから、わたしも「宜しく」と頭を下げる。タクミとは対照的で愛想はないけど、特に拒否られてる空気はない。
「はい、じゃあ次は女子ねー。この子が武井美琴で、そっちが一条モカ。以上!いや、生徒数が少ないと紹介も楽だな」
彼が笑いながらそんなことを言ってる。でも呪術師になる人は多くないと聞いてるし、この生徒数でも仕方がないんだろうな、とは思った。
「初めましてー!ちゃん、美琴って呼んでねー」
「よ、宜しく」
美琴というショートボブの子が笑顔でわたしの前に立つ。元気はつらつといった感じで可愛らしい顔立ちの子だ。ただ、距離感バグってない?と思うほどに近い。でもタクミと同様、懐っこい感じでホっとした。でも職員室でも顔を合わせたモカという子は、わたしをチラっと見るだけ。こっちから「宜しくね」と声をかけたけど、また視線を反らされてしまった。近くで見ると、可愛い系というよりは美人系。日本人形みたいな綺麗な子だけに冷たさが際立つ。
「はい、じゃあ紹介も済んだところで早速、行こうか」
「…どこに?」
気になって尋ねると、彼は「課外授業だよ」と言って、ニッコリ微笑んだ。
「課外授業って…」
「まあ簡単に言えば、任務と同じ祓徐の授業。生徒にも任務は入るから、まずは経験積ませるために呪術実習は必須なんだ」
「え…そうなんだ。でも…いきなり?わたし、まだここのやり方、よく分かってないんだけど…」
「だからでしょ。まずは実践で覚えてもらう。みんなもの実力を知りたいはずだし、知らないと今後の任務で自分の背中預けらんないからさ。もちろん逆も然り。みんなの力をにも知ってもらう」
確かに、と思わず納得させられた。これまでは見つけた呪霊を祓うのも全て一人でやってたから、他人に自分の命を預けるという感覚すらなかった。でも今日からは彼らと一緒に学んで、任務をこなしていく"仲間"になるんだ。一人じゃなくなる分、戦術もその都度、変えていく必要もある。
「じゃあ、この近場だからすぐに行くけど――心の準備は?」
そう訊かれて、ふと顔を上げると、彼が挑発するような笑みを浮かべていた。相変わらず憎たらしい、と思う反面、こうなったら徹底的に特級術師のやり方を学んでやる、という思いが溢れてきた。いくらわたしに多少の経験値があろうと、それは自己流でしかない。自分の足りないところを知る為、間違いがあるなら、それを正す為に、慣れ親しんだ故郷を捨てて高専に来たんだから。
わたしが生きた証を、自分自身に刻む為に。生まれてきて良かったんだと思いたいから。お父さんにも、いつかそう思って欲しいから。
「…できてます」
「上等。んじゃー行こうか」
ニヤリと口角を上げて、彼はまたしても頭をクシャリと撫でていく。癖のないわたしの髪が、彼の指をするりと撫でて、最後はわたしの頬をくすぐった。お母さんに夕飯呼ばれて素直に受けてた時も思ったことだけど、やっぱりこの人、他人との距離感が近い気がする。それとも相手が生徒だから?なんにせよ、生徒からは人気があるらしい。男子二人もそんな感じだったし、今は美琴という子が彼の腕にしがみつきながら歩いて行く。まあ、あのタッパと顔だし、そりゃそうか…と思いながら、わたしも皆の後から歩いて行くと、それまで静かすぎて存在さえ忘れかけてたモカという子と目が合う。その時、違和感を覚えたのは、彼女が美琴という子をキツイ目つきで見てたからだ。でもモカという子はわたしと目が合うと、すぐに反らして歩き出す。やっぱり転校生のわたしとは、言葉を交わす気はないらしい。
(まあ…いいけどね…)
前の学校の時はこんなことがなかっただけに、少しの寂しさを覚えつつ、一瞬だけ浮かんだ元クラスメート達の顔を、すぐに打ち消した。
2.
彼がみんなを案内したのは、高専から徒歩圏内にある大きな川だった。この川はウチのマンションの裏手にも流れてるから、こんな近場に呪霊が湧いたのかと少し驚いた。彼はしっかり帳を下ろすと、土手に座って「あとは宜しく~」と、途中にあるコンビニ横の自販機で買ったホット缶コーヒーを一人で飲みだした。
さっきは良い感じに教師っぽいこと言ってたわりに、やる気ないな、あの人。っていうか丸投げにもほどがある。説明も何もないまま、初対面の生徒同士で祓わせる気満々だ。
でもみんなは彼の理不尽さに慣れてるのか「寒~い」だの「サッサと祓て帰んでー」だのと呑気なものだ。帳が下りたことで数体の呪霊は姿を見せたけど、みんなにはあまり緊張感がない。川の水を媒介にした下級呪霊もいいところだし、誰が祓っても瞬殺だろう。そう思ってたらタクミが「来い。"猫鬼"」と呟いた。その瞬間、彼の背後から大きな大きな猫の形をした何かが発現する。それは顎よりも長い鋭い牙で、あっという間に呪霊数体をかみ砕いた。
「…式神?!」
そういうものがあるのは聞いてたけど、実際に見るのは初めてだ。唖然として見ていると、大きな猫型の式神は、むしゃむしゃと呪霊を食べ始めた。でも鳴き声は「みょーん」と可愛いから、そのミスマッチ感がエグい。猫型の式神は呪霊を完食すると、タクミに擦り寄り、ゴロゴロ喉を鳴らしている。その姿はデカい猫にしか見えない。
「よしよし。よぉやったなあ、猫鬼~!えらいでぇ」
「みょ~~ん」
「……(可愛い…)」※猫好き
「も~タクミってば、まーた自分だけ格好つけちゃってー。私のまで祓わせないでよ」
出番がなかったことへの文句なのか、美琴がタクミに詰め寄っている。まあ確かにこれじゃ勉強にはならない。貴重なものは見れたけど。
「早いもん勝ちやろ。なあ?悟」
「先生とお呼び。それにまだ終わってないでしょーが」
「って、おーい。生徒ほったからしで肉まん食うてるやん。先生がすることちゃうやん」
「いや、コレはあんまんだから」
「てか、どっちでもええわ!食うなや!」
タクミが突っ込んだのも当然で、今ではすっかり土手で寛いでる姿が憎たらしい。ってか目の前のコンビニに行ったな?さっきは持ってなかったコンビニ袋がいい証拠だ。課外授業とか言って自分だけオヤツ持参ってどういうことなの。
(まあ言いたいことは山ほどあるけど…彼の言ったことは嘘じゃない。まだ別の呪いがこっちの様子を伺ってる気配がする)
きっとこっちが本命だ。そう確認するのに彼を見れば、口元にどこか愉しげな笑みを浮かべてる。って、ちゃっかりカイロ持ってきてるしズルい。カイロをモミモミしながら、二個目のあんまんを頬張ってる。あの人、この雪の中、ピクニックに来てると勘違いしてないだろうか。そんな気がしてならない。
「出てくるな…」
と、それまで静かに様子を伺ってた高藤くんが、手にしていた業物の刀を握って川の方へ視線を向ける。高藤くんの持ってる刀は呪具だ。柄の目貫き部分が祖父の紋章と似てる気がして、その辺の話を聞きたいと思ったけど、高藤くんの視線の先から大きな呪力を感じて、すぐに武器を構築できるよう身構えた。美琴とタクミもすでに川へ警戒を向けていたけど、一人だけ興味もなさそうに後方で傍観してる子がいる。モカだ。
(何、あの子…戦う気ゼロ?)
ちょっと驚いて見ていると、彼女は何故か彼の方へ歩いて行く。どういうつもりだと思っていた時だった。ザバァァッという音と共に、川の中から巨大なモノが姿を現した。
「な、何これ…雪…だるま?」
「何や、これ。おもろ!」
「子供が作った雪だるまっぽいよねー。目とか鼻の位置が下手な福笑いみたいでウケる」
タクミと美琴が同時に吹き出し、目の前の大型呪霊を見上げながら笑っている。まあ、わたしもちょっと吹きそうになったけど、見た目よりは手強そうだ。まず体がデカい。その分、けた外れのパワーがある。丸い巨体を浮かした呪霊は、高速で地面に落下し、わたし達を押し潰そうとしてくる。その振動で地面が揺れて、立っているのもやっとだ。全員が攻撃を交わしながら、転ばないよう姿勢を低くしていると、不意に彼が「今日の異常気象はソイツの仕業だよ」と言ってきた。
「え、嘘…コイツが原因?」
思わず振り返ると、彼は「そういうこと」と肩を竦めた。その時、ふと今朝のことを思い出した。彼が通路側の窓から外を見ていたことを。
ウチのマンションの近くを流れるこの川は、マンションの裏手、つまり通路側方面にある。もしかしたら彼はあの時から気づいてた?だから寒い中、窓を開けて――。
「危ない、!」
意識が別の方へ向いた時、美琴の声が聞こえた。一瞬、考え事をしてたせいで、反応が遅れた。そこへ雪の塊のような呪霊が高速で降ってくる。でも伊達に一人で戦ってきたわけじゃない。それより速く、わたしは瞬時に頭で描いた呪具を敏速に構築した。手に、ずしりと重みのある大きな炎のハンマー型呪具が現れる。それを両手で握って力いっぱい振り抜いた。
「…溶けろ!!」
渾身のスイングが、だるま落としのように呪霊の足元を撃ち抜く。その熱で溶けて崩れ始めた時、美琴が呪霊に向かって跳躍し、呪力を込めた蹴りを繰り出した。真っ二つに割れた胴体が、左右に吹っ飛ぶ。それを高藤くんの持つ刀がバラバラに切り裂いた。そしてつかさず、その残骸を――。
「"猫鬼"!」
「みょーん」
再生しそうな動きを見せたからか、トドメと言わんばかりにタクミの式神、猫鬼がそれを食べ始める。…見事なコンビネーションだ。
「お~!偉い偉い。よくみんなで祓ったねー」
雪だるまの攻撃を凌いだ後の少しの息切れを整えてるみんなに、呑気な声をかけながら拍手をしてる彼は、やっぱりどこか楽しそうだった。どこまでも呑気な人だ、と思いながら、呪力の還元をしていると、突然後ろからガバリと抱き着かれた。美琴だ。驚いて一瞬だけフリーズする。
「、すごーい!あの炎のハンマーどうやって出したの?!気づいたら持ってるから驚いちゃった!」
美琴が無邪気な笑顔で訊いてくる。やっぱり距離が近い、と思いつつ「構築したの」と応える。説明はしょりすぎ、と突っ込まれたけど。でも、この気さくなノリが懐かしく感じた。
「え、って構築術師なん?初めて会うたわー!凄いやん!」
「俺も初めて見た。え、で、そのハンマーどこに隠したんだ?」
高藤くんまで食いついてきて、説明する前にわたしの周りは一気に賑やかになった。みんなコミュ力がありすぎる。こういうの嫌いじゃないけども。
「隠したんじゃないよ。は自分で造った呪具をまた自分に還元したの」
彼はやっと土手から下りてくると、わたしの代わりに説明を始めた。この人はわたしの術式に詳しいみたいだし、話が早くて助かる。
「…え、還元って?ポイント還元みたいなやつ?」
「ポイントって…。きっと呪力のことでしょ。ね?」
「あ、うん…まあ、そういうこと」
「ほんまに?それええやん。呪力還元!ガス欠ならへんやん」
タクミは単純に考えてそんなことを言ってるけど、彼が笑いながら「まさか」と言った。
「そんなことはなくて、容量超えれば還元された呪力もあっという間に消費するほど、物体を構築するのは膨大なエネルギーを使う。それに一級相当の呪霊を一撃で倒せるような強固な武器などを造ったりと、自分の容量を超えるような無理をした場合、脳が焼き切れる危険もある。そこは考えて構築しないといけない。それに構築術式と一口にいっても術師によっては結構違いがあるんだけど、の術式は特にコントロールが難しい術式なんだ」
その説明にタクミ達は「へえ~!そういうもんなんやー」と納得した様子だ。わたしが説明するまでもなく、彼の言ったことが正解。でも本当に詳しいな、と思う。もしかしてウチの家系に知り合いでもいるのかな。まさかおじいちゃんではない…よね?
「ってことで、高専に帰ったら、みんなの術式についての授業もしようか」
「お~それええやん。俺や五条先生みたいな御三家はある程度、知られてるけど、他のヤツのはよぉ分からんのもあるしなー」
「五条家も…御三家?」
タクミのその言葉が気になって尋ねると、彼は「その話も後で説明する」と言ってくれた。なるほど。こうして見てると、本当に教師に見えてくる不思議。まあ"見える"と言ったからって、そう"思う"のとは別の話だけど。
それに、だ。事実を隠してたことは、やっぱり腹が立つ。ただの隣人だと思ってたから、あんな恥ずかしいとこ見られても我慢できたのに。
「…ん?、どした?」
ジト目を向けていたら、彼は身を屈めて顔を覗き込んできた。その時視界に入ったのは、若干腫れてる額の傷。一昨日ぶっ倒れた時のたんこぶだ。それを見てたら、ふと思いついてしまった。ちょとしたお仕置きを。
「五条先生…」
「何?」
「オデコに虫が」
言ったのと同時に、腫れてるオデコをペシっと叩くと、五条先生は「いったぁ!」と大げさなほどの声を上げた。その時の情けない顔が、やっぱりちょっと可愛くて笑ってしまった。
仕方がないから――今ので許してやるか。