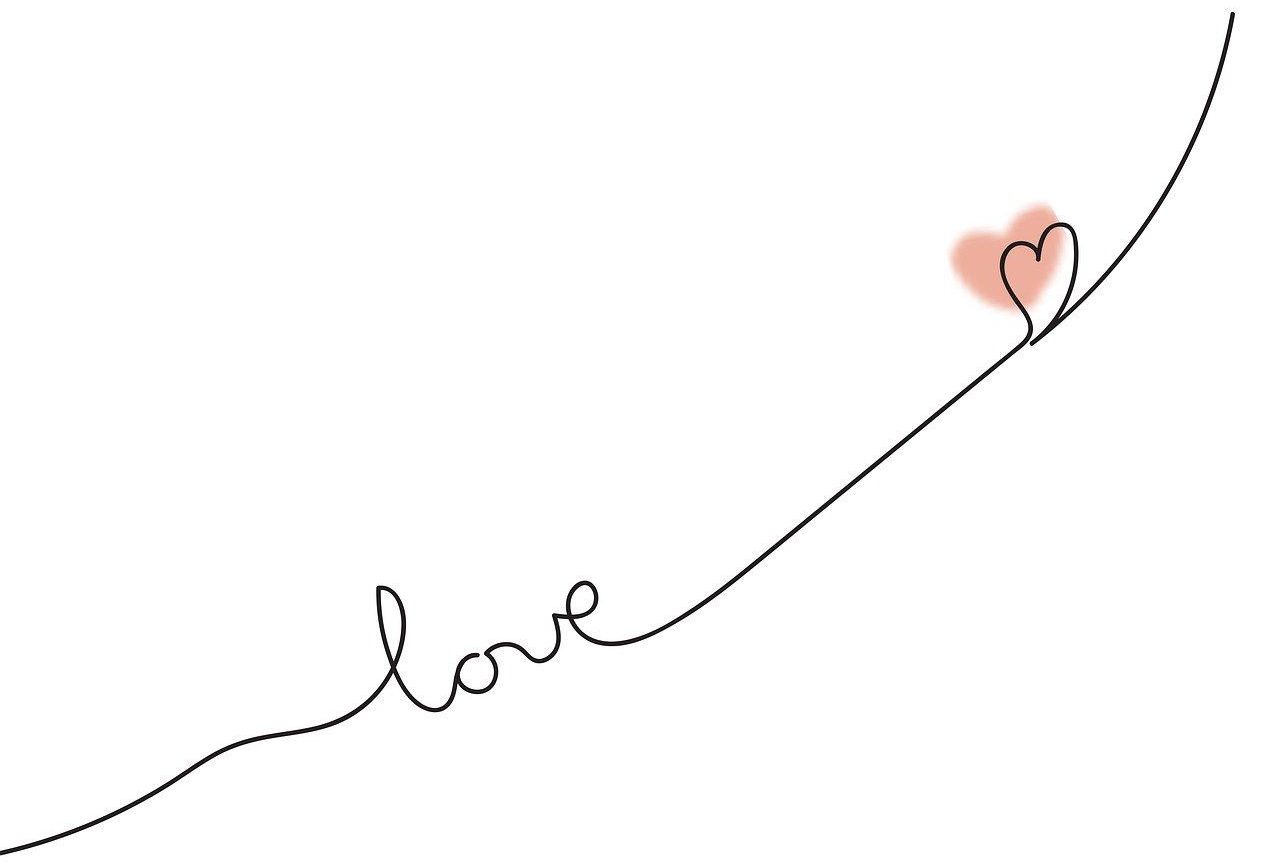鼻につく寛容-01
先生のタンコブと、わたしの涙は、高専ではまだ内緒の話だ。
東京に引っ越して半月は経った11月の半ば。久しぶりにダイチが夢に出てきた。わたしを振った男の夢を見てしまうなんて自分でも未練たらしいと思うけど、目が覚めたら意外と心も冷めていて。まだ悲しい気持ちは残ってるのに、寂しいのは変わりないのに、もう目覚めに泣くことはなかった。
――ずっと会えない状態で上手くいくとは思えない。
寝起きの頭に隣人…いや、先生の言葉が響く。それが現実になっていく気がして、何となくイラっとしたから被っていた布団を蹴飛ばしながら起きた。
「おはよ~」
今日も家を出ると、真横から元気な挨拶が飛んできた。こともあろうに隣人が担任(教育実習生だけど)なんて、世も末とはこのことだ。まだ、その現実に慣れなかったりするけど、ここを引っ越すわけにもいかないから、甘んじてこの環境を受け入れてる自分がいる。
「……はよ」
「あれ、元気ないじゃん。どうした?」
「…別に。夢見が悪かっただけ」
高専まで徒歩27分。その道のりを、自然と一緒に歩く羽目になる。
担任もどきと。
「夢ぇ?どんな夢?」
「……忘れた」
「わっかりやすい嘘つくな~。夢見が悪いってことは覚えてるからでしょ」
笑いながら隣を歩く彼は、相変わらず真っ黒なサングラスをかけていて、見た目も何気に若いから、ちょい悪高校生に見えなくもない。全然、教師に見えない。あと、どうでもいいけど、ほんとに足が長い。わたしと歩く速度も歩幅も違いすぎる。
「あ、は昨日の課題やってきた?」
「えっ課題?嘘、やってない…かも」
「うっそー。ないよ、そんなの。どんだけ僕の話を聞いてないか分かるよなー?」
「……」
でも言うことは教師のそれ。油断してると、こんな反撃に合う。今も嫌味のような笑みを口元に浮かべてるんだから憎たらしい。そもそも自分だって昨日、夜蛾先生の話を聞かずに無駄なお喋りして怒られてたくせに。この人は生徒と一緒になって――特にタクミや美琴と――騒ぐから、生徒かな?と錯覚してしまうことが多々ある。おかげでみんなと早く打ち解けることは出来たけど。
そんなことを思い出してたら、頭頂部付近に熱い視線を感じた。ふと顔を上げると、不意打ちの如く綺麗な青が私を見下ろしていた。因みにこのよーく術式やら呪いが視えるという綺麗な碧眼は自前らしい。カラコンだと信じて疑わなかったわたしは、それを聞かされた時、めちゃくちゃ驚いた。だから川に沸いた呪霊もすぐ見つけられたんだと納得もした。イケメンは瞳まで宝石で出来てるらしい。羨ましい人だ。で…その綺麗な目でジっと見られると、わたしの情緒が誤作動起こしそうだからやめて欲しいんですが。そんな切迫した思いが塩対応として出てしまった。
「何…?ジロジロ見ちゃって」
「いや、何か可愛いと思ったら、、今日は三つ編みなんだ」
「…へ?」
想定外の言葉でサラリと褒められ、わたしは酷く動揺したらしい。その動揺が吃音として現れた。
「か…かわ…?こ、これは……寝癖ついちゃって…ブローする時間なかったから…って、それ、いつもは可愛くないって言ってる?」
動揺を悟られまいと、少し強気に出てみる。でも彼は真顔で「違うでしょ」と返してきた。
「いつも可愛いけど、今日は何か女子高生って感じで、いつも以上に可愛いし、凄く似合ってるって意味だから」
「………」
そう言ってサングラスをかけ直す彼は、時々反則級に距離を縮めてくる。さり気なく褒めるとか、どこのナンパ師だ。恥ずかしいからやめてよ、そういうの。勝手に心臓が反応して朝から一気に負担がかかった気がする。こんな風に男の人から褒められたことなんかなくて、何となく体のどこかがむず痒くなった。
「都会の男ってやつは…」
「ん?何か言ったー?」
「別に…」
腰をかがめて顔を覗き込んでくるから、思い切りそっぽを向く。これ以上、思春期真っ盛りな女子高生の情緒を刺激しないでくれという、わたしなりのアピールだ。なのにこの男は、わざわざ歩くスピードをわたしと同じにするから、いっそう距離が近くなってしまった。こうなると何か話さなくちゃいけない気持ちになるんだから不思議だ。でもそうなればなったで変な焦りが出るから、すぐには話題も思いつかない。だから、ここは呪術学校の生徒らしい質問をすることにした。前から聞こうと思ってたのに、つい学校で会うと忘れてしまうから。
「そう言えば…ずっと気になってたんだけど」
「お、なになに?先生に質問?」
やけに嬉しそうに乗ってくるから、若干口元が引きつった。普段みんなから先生扱いしてもらえてないからって、やたら「先生」と強調するのやめて。
「先生の術式のこと。無下限呪術?」
「あーうん。それの何を知りたい?あ、言っとくけど必殺技はまだ秘密だから」
ビシっと指を立てて言い切る彼の顏が、"どこでもいっしょ"のトロにしか見えない。だって目が矢印化して、ムカつくほどキャピってる。その顏を見てたら、わたしの表情筋が死んだように動かなくなった。瞼も重い。
「……必殺技はどうでもいいんだけど」
「え、凄いんだよ?僕の必殺技。きっとが見たら喜ぶと思うんだけど」
「…どうして?」
何となく理由を訊いて欲しい空気を出すから、仕方ないとばかりに乗ってあげた。わたしって先生思いの生徒だ。自分で自分を誉めたい。でも彼はそんなわたしの気遣いも知らず、愉しげに口元を緩めた。何か嫌な予感。
「だって小さい子って派手な技とか好きじゃん。ドカーン!ドォーン!みたいなやつ」
「…子供扱いしないでよっ」
驚いた時のアライグマかと思うほど、爆発を現わすように長い両手を広げて笑うから、つい彼の背中を叩く、つもりだった。でもそんな感触はなく、何かに押されるような、戻されるような圧迫感を手に感じて、思わず彼を見上げる。彼の術式を体験させてもらった時と同じだ。
「これ…無限でしょ」
「まあねー。今、が僕のこと殴ると予想して、ついオンにしたわ。この前の経験を活かして」
先生の最強無敵な術式のことは初めての授業で教えてもらったし、触れられないという体験をさせてもらったから、何とか理解は出来た。だけど、だったら何で?という小さな疑問がずっと残ったままだった。
「で、僕の術式の何が聞きたいんだっけ」
「あ、だから…これ。この術式は普段オートにしてるって話してたでしょ」
「うん、そうだけど」
「なら何で?これ使えば、わたしのデコビンタ回避できたんじゃない?」
そう。初めての課外授業の時、わたしは高専の教師であることを秘密にしてた彼に対して、小さな仕返しをした。初対面の夜、ぶっ倒れて床にしたたか打ったオデコが腫れてた箇所を、思い切り叩いたのだ。倒れた時は意識がなかったから、術式がオフになってたんだと想像できる。でもオデコを叩いた時は、今みたいに回避できたはずだ。些細なことだけど、先生の術式を聞いた時から何となく気になっていた。
「あ~アレ。アレは油断してたわ。そうくるかって笑ったけど。戒めとしてすぐ治さなかったのが仇になったなー」
わたしの話を聞いた先生は怒るでもなく軽く苦笑いを零すと、「でもまあ、生徒の前じゃ、殆どオフにしてるんだよね」と教えてくれた。何でって聞いたら、ちょっと笑ってしまうくらいの理由だったけど。
生徒とのじゃれ合いを無限で邪魔されたくないって、寂しがり屋か。
だったらさっきも甘んじて殴られてくれればいいのに、と言ったら、無意識に防衛反応が出たと言われた。
「でもの前じゃ常にオンにしとこう」
「え…何でよ」
それはわたしが寂しいじゃない。何となくそう思って抗議の目を向けると、彼は「冗談だよ」と、さり気なくわたしの頭に手を乗せた。そういう時、いつも優しく触れてくる。鍛え抜かれた大きな手なのに、指の先までしなやかに動く彼のこの手が、わたしは地味に好きだった。わたしって手フェチだったっけ?
なんて考えながらも、つい彼の手の動きを目で追ってしまった。そんな自分に気づいてハッと我に返る。一気に頬が熱くなった気がして、誤魔化すのに口元をマフラーで隠したのは、万が一赤くなってたりしたら困るからだ。
っていうか、わたしの異性感知システム、バグってない?ついこの前振られたばかりの女がする反応じゃないってば。しかも隣人で教師の男相手に。
ダイチに振られたからって、すぐ他の男を意識してしまうわたしは、いつからこんなに浅ましい女になったんだ?という疑問が脳内を駆け巡る。
「…無駄に顔がいいのも考えものかも…」
「ん?何て?」
「…いえ、何でもないでーす」
つい口から出た独り言を誤魔化すのに、嘘くさい笑顔で交わしておく。聞かれたらこの人絶対調子に乗るし。そういうとこ、うちのお母さんにそっくり――。と、そこで我が家の愚母を思い出したことで、もう一つ忘れてたことを思い出す。彼が高専の教師だと教えた時に「伝えておいてね」と言われてたことだ。あの時のお母さんは「えー!彼、高専の教師だったのぉー?!え、しかもあの五条家~?!」と、ムンクばりの顔ですんごく驚いてたっけ。仮にも元呪術師なら、彼の呪力くらい感知してくれよと思う。まあ、この人もきっと敢えて呪力押さえてたんだろうけど、多分、お母さんの呪力感知システムがザルだったということも無きにしも非ず。あ、ということは、必然的に娘のわたしもザルってことじゃん。と、どうでもいいことでヘコみつつ、忘れないうちに、と彼を見上げた。
「あのね、テストとかでバタバタしてたから言うの忘れてたんだけど」
「ん?何を?」
「ウチのお母さんがまたご飯食べに来てだって。おじいちゃんからいいお肉もらってくるから焼肉とかどうかなって言ってた」
もうすぐ高専に着くというところで、やっとお母さんからの伝言を伝えることができた。彼が御三家の一つ、五条家のトップ・オブ・ザ・トップと知った途端、目の色を輝かせてたのを思い出す。どうやら彼の顔だけじゃなく、名門とか次期当主という肩書きにもときめいたらしい。長い物に自ら巻かれにいこうとは、我が母ながら分かりやす過ぎて笑ってしまう。
伝言を聞いた彼はふと驚いた顔でわたしを見てから「マジ?嬉し~かも」と柔らかい笑みを浮かべた。その自然の笑みに、またしても胸の奥がキュっとなる感覚に襲われる。ただでさえイケメンの笑顔は破壊力が凄い。勝手に脳が持っていかれそうになるのが怖いと思う。
彼の様子を見て、この感じはOK的なやつ?と勝手に決めつけそうになった時だった。彼はふと前の方へ視線を向けて「でも、僕はいちおー教師志望の教育実習生だから」と笑う。ん?と首を傾げながら見上げると、彼は澄ました顔でこう言った。
「特定の生徒と特別親しくなっちゃうのは――困るでしょ」
彼はそのまま高専の敷地へ続く門をくぐって歩いて行く。その背中を見つめながら、何となく「ふーん…」と力の抜けた声が漏れた。何だろう、このガッカリ感。わたし、ちょっとおかしいんじゃない?なんて自問自答してると、校舎に向かう途中で、タクミが寮方面から歩いて来るのが見えた。
「おー悟~もおはようさん」
呑気に挨拶してるけど、もうすぐ授業が始まるギリギリの時間に来たってことは、また寝坊でもしたに違いない。
高専は普通授業もあるし、当然の如くテストもある。わたしも転入早々それにぶつかって、一昨日まではテストに奮闘する羽目になった。
タクミはテスト期間中、ほぼ徹夜の一夜漬けをしてたらしく、おかげで深夜すぎに寝るクセがついたと、昨日話してたのを思い出す。きっと夕べも無駄に夜更かしをしてたに違いない。
彼はタクミの方へ歩いて行くと、その190はある長身を屈めてタクミの顔を覗き込んだ。タクミも180近いのに、彼と並ぶと小柄に見えるほど視覚がバグる。
「おはよう、追試くん」
「は?マジ?この前の期末、オレ、ヤバかったん?」
「うっそー。まだ採点すらしてないよ」
「はあ?!教師が生徒にシレっと嘘つくん?」
「僕はまだ教育実習生なんで」
「いっつも先生と呼べぇ言うくせに、都合の悪い時だけ、実習生になんなや」
「あれ、タクミ、髪型変えた?無造作ヘア似合うじゃん」
「そうやろー?って、コレは寝癖や!話のすり替え上手いなあ、相変わらず!」
「……」
あの二人、同級生だっけか。思わず首を傾げたくなった。歳も5歳しか離れてないせいか、時々そんな錯覚をしてしまいそうになる。みんなとも友達みたいに接する彼は、夜蛾先生に「ちゃんと指導しろ!」と怒られることもしばしば。特に最近まで一般人として暮らしてたわたしが転入したからか、今まで出来なかった分、きちんと呪術を学ばせたいと思ってくれてるようで、初授業の日は夜蛾先生が彼のフォローをしてたように思う。
その中でみんなの術式についても教えてもらった。すでに呪術実習で目の当たりにしてたから、だいたいは把握したけど。
タクミは禪院家の分家出身で、幼少時代は冷遇されてたみたいだけど、彼が目覚めた術式は禪院家相伝の中でも最も強いらしく、それを知った本家の人間が手のひら返しの如く擦り寄って来たとかで、それにムカついたタクミは半ば家出同然で東京に来たようだ。けど京都姉妹校に入学しなかった最大の理由が「東京には現代最強の五条悟がいるから」だと言うから驚いた。何でも彼がタクミの目標らしい。
健太郎は名門出身じゃないとは話してたけど、自身の呪力を付与した物の力を飛躍的に向上させたり、身体能力を上げたりと、バランスのいい能力を持ってる。彼の愛用してた刀はやっぱりおじいちゃん作で、その辺で話が盛り上がった。
美琴は対象の動きを操れる術式で、それは生きたものでも無機質なものでも良いらしい。でもそれじゃ弱いから、と身体能力を向上させて体術を得意とする子だ。運動神経がないに等しいわたしとしては、羨ましい限りだ。
そして――最後に例のモカ。あの子も名門と名のつく家柄みたいだけど、術式は対象に幻影を見せるもの、らしい。らしい、というのは美琴から聞いただけで、未だ実際に彼女が戦ったところは見たことがないからだ。呪術実習でもモカは殆ど参戦しない。その理由は「自分が戦う前にみんなが祓ってしまうから」だとか。
でも授業なんだから、そんなんでいいのか?とも思うけど、夜蛾先生は何も言わない。担任なのに生徒のことは教え子に任せきりだからだ。早く一人前の教師になって欲しいから、という理由みたいだけど、肝心の彼がモカに何も言わないから、みんなもその辺はスルーしてるようだった。
――なーんか五条先生、モカには甘いんだよねー。美人だからって贔屓してんのかな。
彼女の話が出た時、美琴がそうボヤいてたのを思い出す。だけど、彼は特定の生徒と親しくなるのは困ると、さっきわたしに言った。
(スキヤキくんのクセに、急に先生ぶっちゃって)
未だタクミとじゃれ合いながら前を歩く長身の彼の影を踏む。何か日にちが経っても「先生」という意識がもてないのは、あんな出逢い方をしたせいかもしれないな。
「コラー!悟!生徒と一緒になって遅刻する気かー!」
校舎が見えてきた途端、爽やかな朝の空気に野太い怒号が響く。見れば教室の窓から夜蛾先生が身を乗り出して叫んでいた。
「あーあ。朝から元気だなーあの人。落ちればいいのに」
「うわ、恩師に向かってひどっ。まーたゲンコツ喰らうんちゃうん、悟~」
「いや、他人事みたいに言ってるけど、この場合タクミも同罪だから」
「げ、嘘やん!おい、、はよ教室いくで!」
「はーい」
二人の男子生徒に「早く早く」と手招きされて、わたしは良い子です風に返事をしながら走って行く。最後は古びた廊下を三人で走ったけど、しっかり数分の遅刻。怒るまでもない遅刻のハズなのに、夜蛾先生は見せしめとして、わたし達三人をゲンコツの刑に処した。
「あははっ今日はまで遅刻なんてどうしたの~?」
軽い説教の後、一旦夜蛾先生と彼が教室を出ていった。普段は教え子に任せきりで、呪術専門学以外は来ない夜蛾先生が、朝から教室に顔を出したのは彼に用があったかららしい。テストの結果が予想以上に悪かったとかじゃなきゃいいけど、と思いながら、頭に出来たタンコブをさする。
「何か二人の漫才見てたら、時間忘れてて」
「あーまた五条先生と一緒に来たんだ」
「そうやで。仲良く通学しとったわ。やらし~」
不意にタクミがニヤケ始めるから「何よ、やらしいって」と訊けば、「一つ屋根の下に住んではるやん」と肘でつついてきた。…言い方。
「おい、タクミ。変な言い方すんなって」
「何やねん、ケンタローだけいい子ぶんなや」
「はいはい。朝からケンカしない。五条先生は単なる隣人だし」
タクミと健太郎の小競り合いを止めてると、美琴が鼻息荒く「そうよ!誰かのものになっちゃダメなの」と割り込んできて、後ろにある机上にステージへ上がるかの如く立った。
「五条先生は公共物なの!」
ミュージカルでもやってるのかと思うほど、大げさに両手を広げて宣言する美琴を見上げながら、タクミが盛大に笑った。確かに公共物は笑う。
「なんじゃそりゃ」
「まあ、五条先生が個人に所有されるイメージねえし、似たようなもんじゃねえの」
「ああ、それ分かる」
彼は五条家の次期当主で、現代最強と呼ばれる呪術師だ。だからなのか、かなりのワンマンぶりで周囲の人間を振り回す天性の才があるらしい。そんな男を飼いならせる人間がいるとは思えない。
美琴の一言に何故か納得してみんなで笑ってると、彼女の背後に誰かが立った。モカだ。
「どいてくれる?そこ、私の席」
「え?ああ、ごめん!」
美琴が上っていたのはモカの机だった。すぐに謝りながら美琴が下りると、モカは相変わらずの無表情で席へ座った。
最初の日はわたしが一番後ろの席にされたけど、今じゃみんなと仲良くなって、次の日には美琴の隣に移った。だからモカだけが最初と同じく、その後ろの席なわけで、わたしや美琴の周りにタクミと健太郎が集まると、必然的にモカのテリトリーを侵食する時があった。
わたしがここへ来て、すでに二週間は経ったけど、彼女とは未だにまともな会話をしたことがない。
「ほんま暗いなぁ、モカは」
わたし達が相当うるさかったらしい。少しして、またフラリとどこかへ行ってしまったモカを見て、タクミが呆れ顔でボヤいた。高専に入学した頃はいなかったけど、半月ほどで三人と合流したらしい。その頃から今と変わらないと、美琴が教えてくれた。
「俺、アイツの笑ったとこ見たことねえかも」
「そやなぁ、言われてみれば俺もないわぁ」
「私も~。話しかけてもウザって顔で睨まれるから、任務や授業のことでも必要最低限のことしか声かけなくなったなー」
健太郎とタクミ、男同士で頷き合う。そこへ美琴も加わった。わたしよりも長く一緒にいる三人にもそうなんだから、途中で来たわたしに塩対応なのも納得がいく。「綺麗だし、もったいない気がするよねー」と美琴が少し寂しそうに言った。
「俺はどんなけ綺麗でも性格ブスは嫌やわぁ。そんならオレはや美琴の方がええ」
「…ん?今の流れでわたしの名前を出すのは悪意という名の煽りかな?タクミくん」
「いでっ」
笑顔で寝癖のついた後頭部を小突けば、美琴も「そーだそーだ!」と同じ場所を殴る。タクミは降参したのか「夜蛾ゲンされたとこ殴んのやめぇっ」と逃げ出した。それを見て健太郎も「バーカ」と笑ってるし、何かみんなとは会ったばかりという気がしない。高専に入るまでは、どんな人がいるのか分からなくて、ちょっと不安だったけど、今のとこお母さんが心配してたようなイジメもなく。みんな明るくて楽しい同級生たちだ。
「関西人にバカは禁句やで、ケンタロー」
「じゃあアホ」
「ならええわ…って、何でアホやねん!」
男子二人はいつものようなノリで騒ぎだし、それを笑いながら見てると、隣の美琴がふとわたしを見た。
「モカのことだけど…」
「ん?」
「前に夜蛾先生と五条先生が話してるのチラっと聞いたことあって。何か…モカの家って複雑らしいよ」
「…そっか」
「それが理由かは分からないけど、基本モカは五条先生以外の人間にいつもああだから、も塩対応されても気にすることないからね」
美琴はわたしのことを心配してくれたらしい。そう言って可愛い笑顔を見せてくれた。モカの態度は気になってたけど、わたしもだいぶ免疫は付いた方だ。
それに家が複雑と言えばウチもちょっと複雑だったけど、モカみたいに最初から名家の家で育てられた方が大変なのかもしれない。
「それにしても先生、遅いね~」
美琴の言葉を聞いて、ふと壁時計で時間を確認する。今日は2対3に分かれての呪術実習の予定だったはずだ。そろそろ出なくていいのかな。モカも全然戻ってこないけど。
(そう言えば彼女…わたしが初登校した時、一人で職員室に彼を探しに来たっけ)
窓の外を眺めながら、何となく思い出す。わたし達とは話さないけど、美琴が言ってたように、彼とはよく話してる印象があった。それが気になったのは何となくとしか言いようがないけど。
――特定の生徒と特別親しくなっちゃうのは――困るでしょ。
あんなこと言ってたし、別に何があるわけでもない、よね。
さっき言われた言葉を思い出し、一人納得する。それよりご飯のお誘いを、多分遠回しに断られた件の方が頭が痛い。お母さんにどう伝えよう、としばし考える。この時のわたしには、そっちの問題の方が厄介だった。