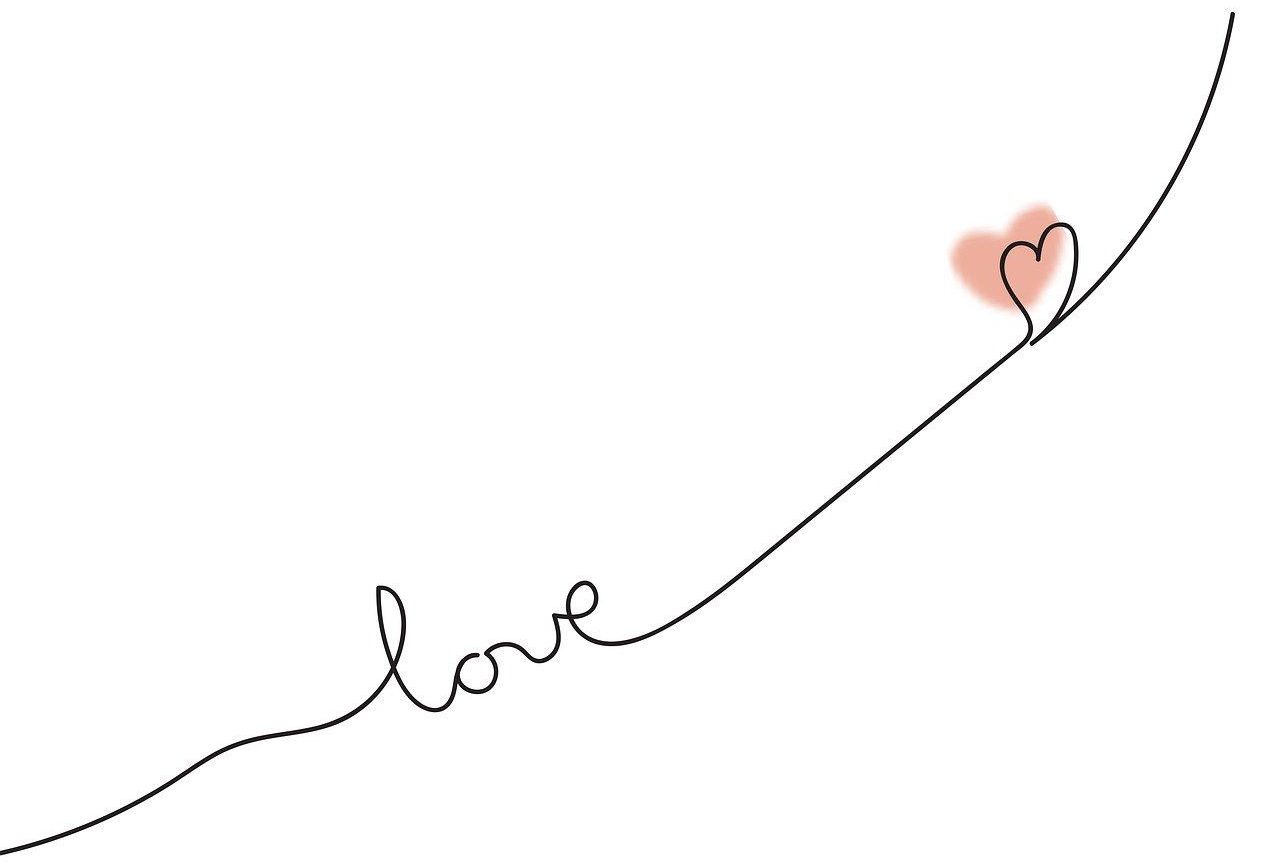鼻につく寛容-02
「五条くん、何とかならんのかね、一年の生徒は」
「は?」
夜蛾先生に「呪術実習行く前にちょっと来い」と拉致られ、職員室へ連れて来られたかと思えば、そこにいたのは普通授業科の教師二名。何事かと思った。
「うるさすぎますよ。期末が終わったからといって、あれは授業を聞く態度じゃない。特に禪院巧と武井美琴は普通授業を軽視してる傾向がある」
「私の授業の時もそうです。女だと思って舐められてるのかと思ってましたけど、どの授業でも同じみたいね」
「は、はあ…私の方でも普段からきつく言ってるんですが…」
数学と英語の教師二人から文句を言われ、夜蛾先生が何故か謝ってる。しかも僕にまで「お前も謝れ」と言い出すから、何で?と果てしなくクエスチョンだった。
「夜蛾先生に謝られてもね。今は五条くんがほぼ呪術の授業を任されてるんでしょう?どういう指導してるのかね」
「…どういうって別に普通の…」
「でもまあ、一年の生徒が一番明るくて元気がいいですな。この世界じゃ貴重な"陽"が揃ってる」
そこへ、他の二人よりは話の分かる歴史文学担当のおじさん教師がフォローするように口を挟んだ。それを聞いて、つい「あ、やっぱり?」と笑顔を向ければ、またしても英語のババアが「しかし小学生じゃないですから」と僕を睨んできた。何だ、これ。魔女裁判か?
彼らは非術師だけど、国から雇われて高専へ教えに来てる連中だ。僕も学生の頃は彼らの生徒だった。その中でも嫌いだったのが、この数学のオッサンと英語のババア教師だ。常に上から目線のエリート根性丸出しってとこが気に入らなかった。あの頃も何かと問題児だった僕が真っ先に目をつけられ、こんな風に説教を受けたことも一度や二度じゃない。当時の担任だった夜蛾先生が、今みたいに頭を下げることもしょっちゅうあった。
何か懐かしい光景だ。そういや、普通科目のある日は憂鬱だったな。まさか卒業してからも説教を喰らうとは思わなかったけど。
「聞いてるの?五条くん」
「聞いてますよー。ま…彼らには僕から言っときますんで」
内心、めんどくせえと思いつつ、頭をガシガシ掻いていると、英語のババアがメガネをくいっと上げて僕を睨んできた。苛立った時のそのクセ、今も健在かよ、と笑いそうになるのを必死で堪える。僕が生徒の時はこいつを怒らせすぎて、くいくいメガネが止まらないから、何度説教中に吹き出したことか。おかげでまた説教を喰らって…以下エンドレス。ムカつくから、付けたあだ名が、そのまんま「くいくいババア」だ。そういやあの時はくいくいババアのモノマネをして「悟、彼女を弄るのもほどほどにしろ」と、あいつにも怒られたっけ。でもそこで「やめろ」と言わないのがみそだ。どうせあいつも腹ん中じゃ僕と同じようなことを思ってたに違いない。マジで懐かしい、と思った途端、苦い思いがこみ上げて、すぐに頭を切り替えた。こんなことで、いちいち感傷に浸ってる場合じゃない。
くいくいババアは怠そうにしてる僕を睨みつつ、盛大な溜息を吐くから、相変わらず嫌味ったらしいヤツだとウンザリした。
「言っても効き目がないから、こうなってるんじゃありません?」
「でも彼らのテスト結果は一通り目を通したけど、平均よりずっと上でしょ。問題ないんじゃありません?」
口調を真似て言い返すと、彼女の目が更につり上がった。また「くいくい」が出るか?と思った瞬間、「悟!」という怒声と共に後頭部へゴツンっという衝撃。夜蛾先生にまた殴られた。地味にさっきの場所と被ってたから凄く痛いが、ここは甘んじて制裁を受ける。
殴られた僕を見て、ババアが呆れた顔で苦笑いしてるから、ちょっとムカつくけど。
「五条くん。君、高専の教師になりたいってことだけど…本当になる気なの?」
まだ絡み足りないのか、ババアはテスト用紙をまとめながら問いかけてくる。サッサと帰れと思いつつ、無理やり笑顔を作っておく。かなり引きつってるけど。
「…どういう意味です?」
「教師としての自覚が足りないんじゃないかと思って。学生の頃から何かと問題ばかり起こしてたけど、今もあまり変わってないようだし?」
「………(殴るか)」
教師志望の人間が考えちゃいけないことを考えて、拳を固めてみたものの、隣にいる夜蛾先生から殺気交じりの負のオーラが漂ってきた。呪いをかけられそうだから、ここは止めておく。呪骸にされちゃたまらないし、文部科学省の人間を殴ったら、それこそ首が飛ぶ。それも――夜蛾先生の。
この国の陰のトップは呪術総本部であり、表側にいるこの教師達も巡り巡って結局そいつらに従ってるに過ぎない。だから別にどうでもいい存在なのは確かだ。そもそもの話、御三家と総本部は蜜月な関係にある。特に五条家には僕もいるから上も簡単に手だしは出来ないだろう。ただ、その分、僕以外の人間が責任を取らされるのは目に見えている。ここは夜蛾先生の為にも我慢するしかない。まあ、もう学生じゃないし、僕も少しは大人になったしね。
「――って、どの辺が大人になったんだ、お前は」
魔女裁判が終わりをつげ、彼らが帰った後、夜蛾先生がグッタリした様子で睨んできた。いや、心外。なったでしょ、大人。昔の僕だったら確実に言い返してたか、近くの机を蹴飛ばしてたと思うけど。そう言ったら、夜蛾先生は深い溜息を吐いて、僕に手をぷらぷらさせながら「しっし」と野良犬でも追い払うかのような態度に出た。いつかあの細いサングラスを真ん中から真っ二つに割ってやろうと心に決める。
それか今度もっといかついサングラスを買ってあげて、指名手配犯みたいな顔にしてやろうかな。なんて考えながら、すぐに生徒の待つ教室へ行くと、タクミの関西弁が廊下にまで響き渡っていた。まあ、確かにうるさいな。ここはNSCのお笑い養成所か?
「ふ…。でもまあ、青い春を謳歌中の若人が元気なのはいいことでしょ」
うんうん、と頷きながら、僕は恩師よりも心の広い教師になってやろうと、と教室のドアを開ける。と、その瞬間、何故か頭上から黒板消しが降ってきた。と言っても人より身長はある方だから、落ちたというよりは頭に乗っかったという感じだ。それでも多少は白い粉が舞い、僕の視界が上半分、真っ白になる。それを見た生徒達が一斉に笑い出した。
考え事をしてたせいで何の警戒もしてなかったのは失敗だった。またベタな悪戯を…と思いながら、足元に落ちたソレを拾う。髪だけじゃなく肩まで真っ白になったけど、まあ、こんな悪戯、可愛いもんだ。でも普通科授業ではもう少し静かにしろと伝えなくちゃならないから、未だに笑い転げてる生徒達の前に立ってみんなを見渡した。ってかサングラスもマジで粉っぽいんだけど。
「あのさ…お前らに話が――」
「ぎゃははは!悟、初めて引っかかってやんのー」
「まさかタクミの作戦が上手くいくとはねー。先生ってアナログに弱い?」
「………」
「たまにドジな五条先生も可愛い~じゃん」
「ヤバいやん。見た感じ白黒の鉛筆みたいになってんで~悟」
「………………………」
注意をしようと思ってたけど、僕の中で何かが唐突にキレた。
「来年、俺が教師になれなかったらお前らのせいだからな!」
「「「「え~~っ?!急にキレた!」」」
学生の時みたいな口調で怒ってはみても、みんなは更に笑い出し、結局こっちも釣られて笑ってしまう。根暗の多い業界だから、たまには元気で明るい生徒がいたっていいだろ。
エリート目線で生徒を語ってんじゃねえよ。
みんなの楽しそうな笑顔を見てたら、やっぱ殴れば良かったな、くいくいババア、と少しだけ後悔した。