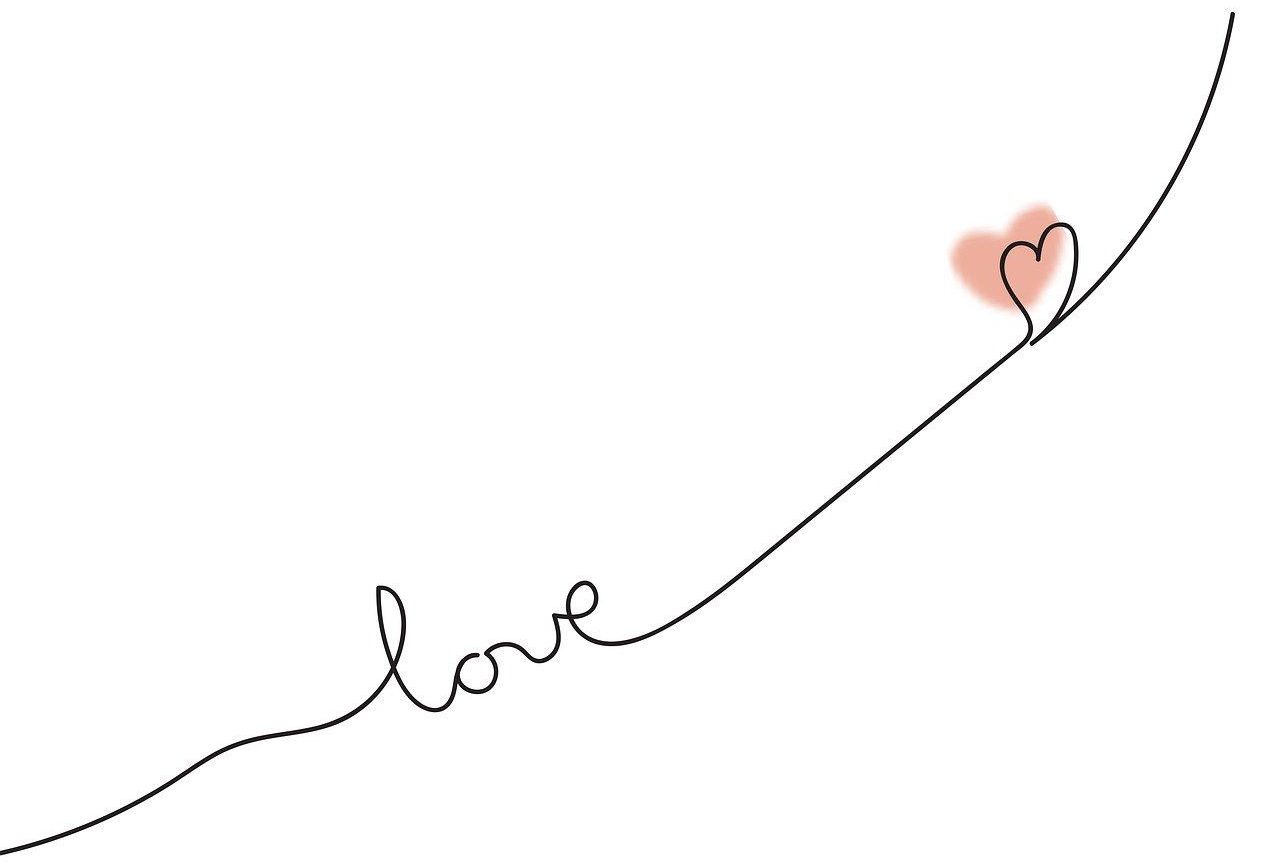鼻につく寛容-03
「来年、俺が教師になれなかったらお前らのせいだからな!」
わたし達を散々待たせておいて、戻って来たら来たで、突然彼はキレた。いつもより口が悪い。何だ情緒不安定か?と心配になったけど、すぐに機嫌が直ったようだ。今は呪術実習に行くコンビ分けをするのにくじ引きなんてものを楽しそうに作ってる。意外と彼は単純なのかもしれない。
彼があまりに遅いからか、暇を持て余したタクミがベタな悪戯を仕掛け始めたのを笑いながら見てたけど、まさかあんな古典的罠に引っかかるとは思わなかった。どうせバレると思って止めなかったんだけど、未だに制服の肩は白いままだし、髪は同色だから分からないけど、彼が歩くたび、白い粉がパラパラ舞うのジワる。
「ほら、もくじ引き引いて」
「あ、うん」
彼の手には人数分のポストイットが握られていて、引くとそこに同行する人の名前が書かれている。二組になった方には彼が引率してくれるからか、他のみんなは真剣にくじを引いてたりする。因みにわたしはまだ二組になったことがない。
「お、やりぃ。オレとケンタローなら楽勝やん」
「はい、油断しない。ってことは男子組が僕とで、女子三人が一緒ってことね。たちは補助監督に同行してもらって」
彼はそれだけ言うと、男三人、楽しそうに実習へと出かけて行った。美琴は「私も五条先生引率が良かったなー」とボヤきつつ、「でも女子三人なんて珍しいからいいけど」と笑ってる。ただ、モカは相変わらず、こっちの輪には入らないでサッサと補助監督の待つ車へと歩いて行った。
因みにモカは彼が戻ってきた後、少しして教室に戻ってきた。どこ行ってたのと彼に訊かれた彼女は「トイレ」と言うだけだったけど、そのやり取りを見て、二人は一緒じゃなかったんだ、と少しだけホっとしたわたしがいる。あんな理由でお母さんからの招待を断ったのに、他の子と親密にされたら、いくら呑気なわたしでも多少は傷つくというものだ。
結局この日の呪術実習は、女子三人で行くことになり、都内にある公園のトイレに沸いた三級くらいの呪霊を片付ける簡単なものだった。それから寄り道もせず再び補助監督さんの運転で高専に戻り、彼に実習の報告をするのに教室へ向かう。男子組はすでに帰校していて「秒で終わったわ」という、どや顔のタクミに出迎えられた。
「そっちはどないやってん」
「んー、似たようなもんかなぁ。その公園、ちょっと不気味でさ。下級の呪霊がわんさかトイレに居座ってた感じ」
「あぁ、公園のトイレって夜とか結構不気味やもんなぁ」
「うん。ただ先月、そこのトイレで事件があったみたいで、だから一気に湧いたんじゃないかな」
「事件?」
「うん。何か近くの高校に通う生徒が、そのトイレで不審死してたって。事故か事件か、それとも呪い関連か、補助監督さんが調べてるって話だった」
「マジか。公共のトイレで発見されるとか、何か悲惨やなぁ…」
タクミが珍しく顔をしかめている。まあ同年代の子の死は特に、呪術師をやってるわたし達でもちょっと気が滅入る話だ。何となく沈んだ空気になった。でもその空気を一転させたのは美琴だった。
「ね~。今度家に泊りに行っていい?駅前の高層マンションなんでしょ?」
突然、背後から抱きついてきたかと思えば、そんなことを聞かれて驚いた。
「え、いいけど…わたしの部屋は狭いよ。お母さんに広い部屋とられたし」
「いいの、いいの」
「美琴は寮に入ってるんだっけ。外泊許可とれるの?」
「その辺はばっちり。早めに申請すれば」
そう言いながら美琴がニコニコと腕を組んでくる。それを見ていた健太郎が「みえみえだな、美琴」と鼻で笑った。何が?と思ったけど、美琴は「うるっさいなあ、ケンタロー」と言い返している。そこにタクミも入って「あーそういうことなんや」とわたしを見るから、頭にクエスチョンが並ぶ。わたしだけ分かってないっぽい。何なんだ、この空気。
「よーく聞け、。こいつの目当てはやなしに、そのお隣さんや」
「へ?」
「いーえ!女同士の親睦を深めるの!」
美琴がまたしても抱き着きながら、「それはホントだから」と笑う。そこでやっとピンときたと同時に、わたしまで釣られて笑ってしまった。
「何でもいいよ。来てくれるのは嬉しいし」
「良かった~!」
美琴が大げさなくらい喜んでくれるから、彼が目当てでも何でもいーやと思ってしまう。こっちに来て早々、こんな風に仲良く出来る友達ができたのは、わたしにとって嬉しい誤算だ。でもホッペにチューはしないで欲しい。わたしにそっちの気はない。
「え、ほなら俺もええ?」
「は?タクミが行くなら俺も行くだろ」
わたしが許可したからか、何故かタクミと健太郎まで参加してきたのも笑う。タクミも、もちろん健太郎も寮生だから夜は暇らしい。ただ、美琴は「はぁ?」と呆れ顔でタクミを睨んだ。
「ダメに決まってるじゃん。何考えてんの、タクミもケンタローも」
「え~~。ずるいやん。女子だけでつるむん」
「わたしは別にいいけど。ウチのお母さん、細かいこと気にしない人だから。でも男子は寝るとこ荷物置き場になってる和室になるけど」
「え、ほんまに?俺はどこでも寝れるし大丈夫や」
「俺も」
「えーちょっと!女同士で積もる話もあるのにー!」
男子二名は喜び、美琴は不満げな声を上げた。でも結局タクミに押し切られ――彼の屁理屈に勝てるのは五条悟だけらしい――美琴は渋々頷いていた。
「ほなら早速、悟に任務のない日、聞きに行くで」
呪術実習の報告を終えた後、職員室へと戻って行った彼を探しに、タクミが帰り支度を始める。彼が出てったと同時にモカも帰ったから、教室にはわたし達しかいなかった。
「そう言えばは寮に入らないの?」
職員室へ向かう途中、美琴がふと訊いてきた。彼女の実家は千葉の方らしく、通うのは当然無理だからと、高専入学と同時に寮へ引っ越したらしい。
「うーん…いつかは入ると思うんだけど…まだ入らないかな」
「そっかぁ。まあ近いっちゃ近いもんね、マンション。いいなぁ、五条先生の隣なんて。あのマンション高そうだし」
「悟も去年までは寮に入ってたのに先生になるからって、近場にマンション借りた言うてたけど、まさかのお隣さんとはなあ」
へえ、彼も寮生だったんだ…と、ふたりの会話を聞いて納得する。あそこへ引っ越した時、管理人さんが隣も引っ越して来たばかりと言ってたのを思い出した。でも教師の仕事の他に、特級呪術師としての任務も入るらしいから、彼はかなり多忙だ。引っ越してから、家で寝たのは数えるくらいだと、この前も話してたっけ。そんな状態で家にいることなんてあるんだろうか、と少し心配になる。みんなが泊りにきたはいいけど、彼が不在じゃ盛り下がる気しかしない。
だから、その辺のことを聞きたかったのに、職員室へ行くと、そこにいたのは、さっき実習に同行してくれた補助監督さんだけだった。
「五条術師ならもう帰られましたよ」
「え、任務ですか?」
「いえ、何か用が出来たとかで…みんなの呪術実習の報告書もそこそこに切り上げて急いで出て行きましたけど」
その説明を聞いて、案の定、高かったみんなのテンションが急下降した。
「なんやねん、悟~。珍しく帰んのはやっ」
「まあ…帰ったんじゃ仕方ねえだろ」
男子二名は切り替えが早いのか、そんなことを話しながら寮へと歩いて行く。でも美琴だけは「先生の部屋見たかったー」と嘆いていて、「とも夜更かしして、いっぱいお喋りしたかったなー」とブツブツいいながら、タクミ達と寮へ帰って行った。わたしもみんなが泊りに来るのは楽しみだった分、ちょっとガッカリしたけど仕方がない。
「また明日ね」
と、三人を見送ったあと、今朝は彼と歩いた道を、帰りはひとりで歩く。高専に戻ってきた時は一面オレンジだった空も、今は帳が下りて外灯が夜道を照らしてくれた。
「泊りに来て欲しかったなあ。お母さんも張り切ってお寿司とか取ってくれたかもしれないし」
なんて独り言ちながら、ふと思ったのは、高専のみんなが凄く懐っこいってこと。タクミや健太郎からも、初対面で「」呼ばわりされて、かえって気が楽になったと思う。
(わたしは…ここで生きてく…この先も…)
今はまだ、ここが自分の居場所と思えなくても、これから住んでいれば、きっと札幌で過ごした時間もおぼろげになっていく。記憶なんてそんなものだ。
「あ…雪…?」
不意に小さな雪が落ちてきて、わたしは空を見上げた。川で祓った雪だるま呪霊はラニーニャ現象で寒気に包まれてる今年、慣れない雪を怖がるこの町の人達が生み出した呪いで、それがあの日の雪を降らせたんじゃないかと彼が説明してくれたけど、祓った後も空に与えた影響は消えないらしい。少し気温が下がるだけで、こんな風に雪が降ってくる。それを見てたら、何故かダイチに告白された時のことを思い出した。雪を見て札幌を思い出すと、必ず次にダイチの顔が浮かぶ。
――、話があんだけど。
――え、ダイチじゃん。うそ、うそ、に何の話~?
――ダイチ、やるじゃーん。
――うっせぇな、お前らに関係ねえから。
あれは夏休み前で生徒が浮かれ始めた頃。少し顔を赤くして、わたしを教室の外に呼び出したダイチは、どこか緊張したような顔をしてた。いつものチャラけた態度は鳴りを潜めて、真剣な目でわたしを見たっけ。
――俺と…付き合わねえ?
その言葉が、胸に突き刺さったかのようにドキドキして、凄く恥ずかしくなったけど、でも同じ気持ちだから嬉しかった。あれはきっと、わたしの初恋だったんだと思う。
――ちゃん、ごめん。ママと東京行こう。
お父さんの説得を諦めたお母さんは今、後悔してないのかな。この先、お父さんも別の人を好きになるかもしれないのに、ツラくないんだろうか。
きっとダイチも…そのうち、また別の人を好きになる。きっと、わたし、も――。
「お帰り~。遅かったね。寄り道でもしてた?」
「……は?」
ボーっと考え事をしながらマンション最上階に到着すると、何故か部屋の前に彼がしゃがみこんでいた。サングラスはしてるものの、今は私服にコート姿。いるなんて想像すらしてなかったから、めちゃくちゃ驚いた。用が出来たから先に帰ったんじゃないのか。
「な…何してんの?こんなとこで――」
「あ~…管理人待ってんのー」
「…え?何かあった?」
少し不機嫌そうに見えてドキっとした。彼はわたしが歩いて行くと、ゆっくり立ち上がって溜息交じりで説明してくれた。
「え?鍵をなくしたぁ?だからこんなとこでしょんぼりしてたんだ」
「うるせー笑うな」
子供みたいだと笑っていると、彼はスネたように文句を言ってきた。学校で会う時より、マンションで会う彼の方が素に近いから何か面白い。なんて思ってると、彼は半目状態で笑ってるわたしを見下ろした。
「僕はデートなの。これから向かわなきゃいけないってのに」
「え…?」
「どうしても渡したいもんが部屋にあるんだよ」
ったく、こんな時に参るよなあ、とボヤく彼は、いつもの飄々とした空気でもなく。恋人とのデートに水をさされてイラつく、一人の男の人に見えて。ああ、彼も最強呪術師で、教師である前に、普通の男なんだな、なんて今更ながらに実感してしまった。