鼻につく寛容-04
鍵を落としたという彼は「管理人、おっそ」とイライラしながらケータイで時間を確認してる。相手との約束の時間が迫ってるのかもしれない。
――僕はこれからデートなの。
――どうしても渡したいもんが…
もしかしたら今日は彼女の誕生日とか、何かの記念日か?彼の言葉を思い出して、ふとそんな想像をしてみる。
よくよく見れば、コートの下はスーツでキメていた。さっきタクミに悪戯されてチョークの粉っぽかった髪も、今はサラサラに戻ってる。部屋に入れないのに何で?と訊くと、彼が高専の寮で使ってた部屋はまだ健在で、私服の類もそこに置いたままだという話だった。時短を目的に寮で風呂も済ませたという。
「ホントはそのまま行くはずだったんだけど、マンションに忘れ物したの思い出してさ」と彼は溜息を吐く。寮をトランクルーム代わりに使うなと突っ込んだら、少し笑ったようだった。
別にプライベートを詮索するつもりはないけど、これまで漠然としてた先生という存在の彼が、"男"なんだとハッキリ突きつけられた現実に少なからず動揺してるのかもしれない。今まで生きてきた中で、先生は"先生"という生き物だと思ってたし、その先生という生き物が、学校以外で誰と会い、どんな付き合いしているのかなんて考えたこともなかった。でも高専に来て、教師と生徒の間にあるはずのボーダーラインが曖昧な状況も多いから、少し前までの感覚がブレてきたようにも思う。
彼は待ちきれないのか、何度もエレベーターの方へ視線を向けている。こういうマンションの管理人は駐在してるとこもあれば、してない場所もあるようで、残念なことにココはしてないタイプらしい。そういう場合は大抵、不動産会社が管理をしてるから、彼が待ってるのは実質、管理人というよりは不動産会社の社員だった。更に残念なのは、その会社が都内にあるということだ。帰宅ラッシュの時間帯。電車も人でごった返すし、車でも渋滞にハマる。
「来ないね。こんな時間だし、車が混んでるのかも」
「…ハァ。最悪」
相当イライラしてきたなぁと思いながら見上げると、彼はふとわたしへ視線を落とした。
「ああ、ごめん。寒いしは家に入って。さすがにもう来ると思うし」
「…うん」
そうなんだけど、と思いながらも、何故か彼を残したまま家に入る気がしない。明かりは消えてるようだから、お母さんは不在というのが分かる。そこで今朝「今日は実家で親戚が集まるから行ってくる。まだ挨拶できてない人達もいるし」と話してたのを思い出す。家の長女が出戻りしたのを祝うらしい。その話だけで、どんだけ非術師のお父さんが冷遇されてたのかが分かるから、ちょっと笑ったけど。結婚する時、お母さんの性にまでして歩み寄ろうと頑張ったお父さんに、少しだけ同情する。結局、最後まで「婿養子」とは認めてもらえないまま離婚したんだから。呪術界に理解がなさすぎたお父さんも悪いけど、それを考えると同情すべき点もあるかもしれない。
「ん?どうした?」
「ううん。何でもない。っていうか、管理会社を待たなくても、先生なら力を使ってベランダまで飛べるんじゃない?窓が開いてるならだけど」
何となく思いつきで提案すると、彼は「いや、目立つでしょ。ここ駅前」と笑った。確かに、こんな田舎の駅でもそれなりに人は歩いてる。ベランダは駅に面してるし、一階はコンビニだから、人が宙に浮かんでたら、それこそ大騒ぎだ。明日の新聞に「フライングヒューマノイド現る!」なんてデカデカ書かれそう。それもちょっと面白いけど、非術師の心を乱すと、その数だけ呪いが発生する可能性も増えるから、やっぱり却下か。
その時、ふと思いついた。下から飛ぶのは目立つけど、ウチのベランダからなら目立たないのでは、と。今なら彼を家にあげてもウザいと思われるほどに絡む存在もいない。
「なら…ウチのベランダづたいに行くってのは…?」
チラっと見上げて新たな提案をすると、彼の頭の上に電球が光ったのが見えた気がした。この顔は「いいな、それ」的なやつだろう。ここは20階だし、隣のベランダへ飛ぶくらいなら、下からは殆ど見えないはずだ。
「でも母ちゃんは?」
「今日はおじいちゃんちで親戚連中と出戻りパーティだからいない。多分、お酒も飲むだろうから泊まってくると思う」
「出戻りパーティって…さすが源太師匠の娘。ファンキーな催しすんね」
源太とはわたしの祖父の名だ。やはりと言うべきか、老舗の呪具師は御三家とも蜜月な関係らしく、当然五条家とも付き合いがあるそうで、彼もおじいちゃんのことは子供の頃からよーく知ってるらしい。わたしの担当する術師が五条悟とお母さんから聞いたおじいちゃんは、その日のうちに『は五条のボンから教わっとるのか!』とメールを寄こした。しかも派手なデコメールに絵文字付きで。ファンキーというなら祖父の方だと思う。ケータイすら使いこなして、現代の若者かと思うくらい、返信が早い上に、絵文字を多用するから女子高生か!と毎回突っ込みたくなる。
「あ~何か雪と風が強くなってきてる」
彼を家に招いて明かりを付けると、すぐベランダへ向かう。窓を開けると高層マンション特有の、ベランダを囲むように設置されたガラスの向こうがやたらと吹雪いていた。そのガラス窓になってる部分の鍵を開けると、一気に強風が流れ込んでくる。構造上、21階以上の建物にはベランダ設置は難しい。でもここは許容階数ギリギリを攻めてベランダを設置したというだけあって、保護用のガラス窓を開けると、体を持っていかれそうなくらい風が強い。
「うわ…!さすが最上階…風だけで飛べそう。こっから先生の部屋に移れるかな」
リビングの明かりだけを頼りに隣を見ると、彼の部屋のベランダは少し距離があるけど、飛べないほどでもない。その時、美琴の言葉を思い出した。
――五条先生の部屋、見たかったなー。
彼の部屋。どんな感じなんだろう。ちょっと気になるところではあるかも。そんなことを考えていると、背後から「!」と呼ばれた。
「危ないって。僕が確認する」
大きく身を乗り出したわたしを見て、彼はサングラスを外して慌てたようにベランダへ出てきた。でも「分かった」と応えて、わたしが身を引こうとした時、再び強風が吹きつけ、一瞬体が持って行かれそうな感覚になった。
あ、ヤバい。そう思った時だった。わたしの腰に何かが巻き付いて、少しだけ体が浮く。え?と思ったら、彼がわたしを抱えていて、すぐにベランダへ下ろしてくれた。その一連の動作もそうだけど、あまりに軽々と抱えられたことに驚く。視線をあげたら彼と目が合い、しばし見つめ合う格好になった。こんな近くで彼の六眼を見たのは初めてかもしれない。吸い込まれそうなくらい綺麗でビビる。
すぐに腕は外されたのに、今も抱きしめられてるような感触が体に残っていて、それがやけにドキドキするのも何か怖い。何この感じ。
「…ス…スケベ」
「いや、何で?」
色々なことに脳が追いつくと、じわりと頬が熱くなった。誤魔化すように出てきた一言は余計だったかもしれない。彼は軽く息を吐くと、「ほら…な?」と呟いた。
「だから問題あるだろ?こういうシチュエーションになると」
「え…?」
何のことだと顔を上げると、彼は綺麗な瞳を僅かに細めてわたしを見下ろしていた。
――特定の子と特別親しくなっちゃうと…
そこで今朝、彼に言われたことが脳裏に過ぎる。また家で食事でも、というお母さんからの伝言を口にしたら、彼はそう言って笑ってた。でも、そんなものは断る為の口実だと思ってた。そもそも――。
「そんなの…自分がこういうシチュエーションになれば手を出すかもしれない男だって自覚あるから思うだけでしょ?」
それはただの軽口だった。ちょっと気まずい今の空気を変えたいがための。
彼は何を言うでもなく、ジっとわたしを見つめるから、一瞬怒ったのかと思った。でも次の瞬間、ふ…と柔らかい笑みを浮かべるから、心臓が変な音を立てる。ここでその優しい微笑は反則だと思う。
「は何か親しみやすいし、いちいち反応も可愛いから」
「…な」
「つい構いたくなって仲良くなっちゃうんだよ。だからはみんなともすぐ友達になれたろ?」
「………」
ん?と伺うように微笑む彼を見上げて、つい吹き出してしまった。完全にわたしの負け。つくづく反則を仕掛けてくる人だ。でも次の瞬間、別の意味でドキッとさせられた。
「みたいな子がモカと仲良くしてくれたら安心なんだけどね」
彼が窓の外を眺めながら、ぽつりと言った。何で今、モカの話をするんだろう。そんな思いが顔に出てたのかもしれない。彼はふとわたしを見て「ほら、あいつ一人だろ、いつも」と言った。
「僕には結構喋ってくれるんだけど、あいつ元々あんなんじゃないと思うんだ。ちょっと家が複雑でさ。でも本当はすごいいい子――」
「…五条先生っ」
「え…?」
話を聞いてたら何故か心臓がバクバクして、つい言葉を遮ってしまった。鼻につくほど、モカに対する彼の寛容な態度が、更に鼓動を速めていく。同時に浮かんだ一つの疑問。
まさか――ね。
「デートって言ってたけど…誰とするの?」
わたしの不躾な質問に、彼は怪訝そうに眉を潜めた。
「…誰って…まあ、婚約者だよ。一応ね」
「…こ…婚約者…?」
21歳で婚約してるって事実にも驚いたけど、御三家に入るほどの名家ならあり得るとも思った。でもそれより。この時のわたしは、彼とモカがデキてるわけないか、という安堵感の方が強かったように思う。それは単に彼の相手が同級生だったら気まずいからなのか、それとも別の理由なのか。そこまでは分からなかったけど。とにかく、顏も知らない婚約者はどうでもよくて、モカじゃないという事実が重要だった。
「何だ…はははは…」
「無意味に笑うな。何なんだ、今の質問は」
彼が呆れたように言った時、ケータイが鳴った。わたしのじゃなく、彼のだ。どうやら管理会社の人が到着したらしい。彼は「すぐ行きます」と言って電話を切ると、そのまま「色々ありがとな、」とわたしに声をかけて玄関へ向かった。
「じゃあなー。また明日」
「うん」
靴を履いて彼がドアを開ける。その背中を見てたら、つい言いたくなったのは、どんな反応をするか見たいという、生徒の悪ノリに近かったのかもしれない。
「でも良かった。これで婚約者の人にプレゼント渡せるね」
「………」
彼はしばし無言だったけど、不意にこっちへ振り向く。すでにサングラスはかけてしまってるから、どんな顔をしてるのかまでは分からない。でも何となく呆れたように目を細めてるような気がした。
「ダレが…プレゼントだと言った?」
「へ…?違うの?」
わたしが訊ねた瞬間、彼は何を思ったのか、思い切り中指を立てて、そのまま出ていった。ちょっと唖然。とても教師のすることじゃないぞ、それ。
「生徒に中指立てるとか…変なヤツ」
やることが悪ガキのそれで、思わず吹き出して笑ってしまったけど、ああいうところは嫌いじゃない。同じ目線で見てくれてる気がして、教師ヅラして上目で話されるより、ずっといい。
ふと自分のお腹に触れてみると、さっきの感触はもう消えていた。なのに、まだ強い腕に抱かれてるような温もりが残ってる気がして、ちょっとだけドキドキが復活する。
先生は"先生"という生き物だと思ってた。でも、それは違うんだという現実を、突きつけられた夜だった。
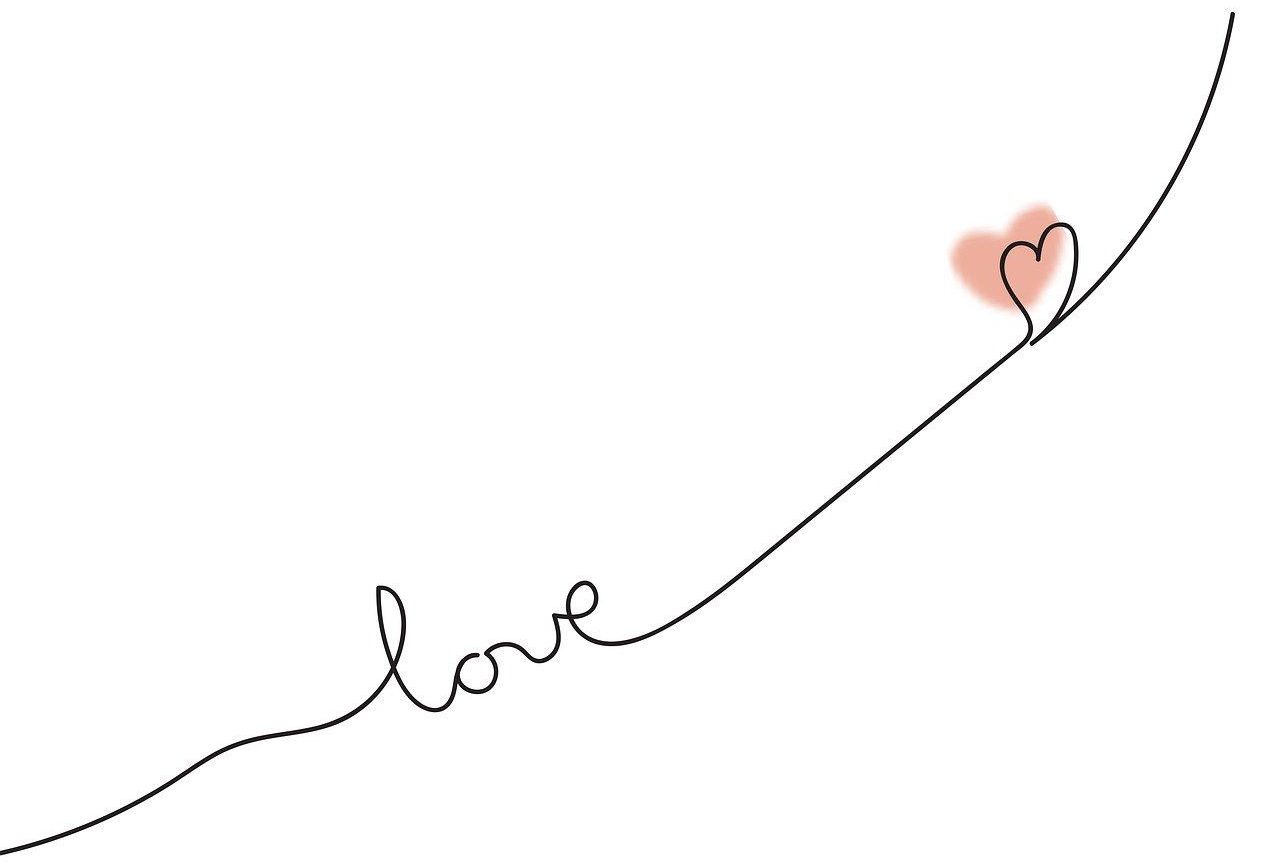
ひとこと送る
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
