12-こころというもの、言葉というもの
次の日の朝、ドアを開けても彼はいなくて、久しぶりにひとりで登校した。
「おはよー!」
「おはよう、美琴」
「ねね、五条先生に予定訊いてくれた?」
「…へ?」
いつものようにガバリと抱き着いてきた美琴の問いに、首を捻る。何だっけ?と思ってると、美琴は「もー!」と口を尖らせる。それが嫌味じゃないから普通に可愛いの羨ましい。
「週末、任務がなければ先生も家にいてって話だよー」
「あー…ごめん。忘れてた。今朝は一緒じゃなかったし…」
ふたりで教室に向かいながら、ふと夕べのデートはどうだったんだろうと考える。まあ、婚約者持ちに週末空いてたら家にいろってのも難しい気がするんだけど、どうなんだろうか。そんなことを考えつつ、2階につくと、わたし達の教室の方がやけに騒がしかった。中を覗くと、まだタクミは来てなかったけど、健太郎の姿は見えた。でも他に見かけない生徒が数人いる。その人達は黒板の前で何やら固まっていたけど、わたし達に気づくと、笑いながら教室を出て行ってしまった。
「何、あの人達」
「あー…確か二年の先輩だよ。たまに体術の指導してくれたりする。最近は出張とかでいなかったけど戻って来たんだ」
美琴はそう言いながら教室へと入っていく。その時、後ろから「おはよーさん」というタクミの声がした。欠伸を連発してるところを見ると、また徹夜でゲームでもしてたんだろう。
「どないしたん?教室前に突っ立って。入らへんの?」
「あー…うん。今、二年の先輩達が教室に来てて…」
「は?二年…?何しに来てん」
タクミが驚くってことは、こんなことが普段からあるわけじゃないんだと思った。その時、先に教室へ入った美琴が「、ちょっと来て」と教室から飛び出してくる。何事かと驚いて、美琴に腕を引かれるまま中へ入った。
「これ!」
「え…」
美琴が指す方向には黒板。そこには"HOTEL"と書かれた建物らしき絵と、ハートのマーク、その隣に髪の長い女の人のうしろ姿――どこかセクシー風――の絵が描かれていて、一番上には"五条悟と彼女のイケナイ関係―"とデカデカ書いてあった。驚いて言葉もない。何だ、これは。
「夕べさー見たんだって。先輩らが。出張帰りに寄った六本木で」
唖然としながら黒板を見てると、先に来てたらしい健太郎が溜息交じりで肩を竦めた。
「五条先生と女の人がホテル入ってくとこ。つっても、こんなラブホじゃなしに、高級ホテルだったみたいだけどな」
「……(げ)」
その説明に心当たりのあるわたしは、内心冷や汗が出る思いだった。何てタイミングだろう。よりによって彼からデートの話を聞いた次の日にこれじゃ、わたしが書いたと思われる。そこは目撃者の健太郎がいるから違うと分かっても、じゃあ二年の先輩にそのネタをリークしたと思われそうだ。二年なんて、まだ絡んだことすらないのに!
「…そりゃ…いないわけ…ないけどさー…」
隣で珍しくへこみだした美琴に「そ、そうだね」と声をかけるしか出来ない。もしかしてマジで彼のこと好きだったの?と驚いたけど、聞くと「そういうんじゃなく憧れてたから」と言われた。きっとアレだ。憧れのアイドルに彼女がいると発覚した時のファン心理ってやつだ。
「どんな人だったんだろー…」
「何かいい女系って言ってたぞ」
「えぇ…」
「なーんや。悟もフツーの男かぁ~」
健太郎、美琴、タクミが、それぞれの反応を見せる中、ふと振り向くと、ドアのところにモカが立っててビビった。彼女は黒板を凝視しながら、やっぱり驚いてる。でも美琴よりも彼女の方が重症っぽい。その大きな瞳が潤んでいたように見えたから。
「モカ…大丈夫?」
つい声をかけてしまったけど、彼女は我に返ったように息を呑んで、俯いたまま自分の席へ座った。また無視か、と溜息が出たけど、この様子だと、モカは彼のこと本気で好き、なのかな。ふと考えていると、教室の前のドアがガラリと開く。マズい。消す前に彼が来てしまった。タイミングが悪すぎる。これじゃホントにわたしがバラしたと思われてしまう。
彼は「おはよー」と教室へ入って来たけど、黒板を一瞥しただけで、いつものように教壇へ立った。そこへ空気の読めないタクミが、冷やかすように口笛を吹く。
「ひゅう~やるやーん、悟~」
「ちょ、タクミ…!」
「女子を泣かせたらあかんてー」
早速、タクミがからかうような声を上げるから、ますます心臓が痛くなってきた。彼はいたずら書きの件には触れず、チラっとこっちに視線を向けた。つい肩がビクっとなったのは、誤解されたくないからだ。そもそも、わたしは彼の婚約者がどういう人なのか知らない。こんな絵も描けるはずがない。
わたしが内心バクバクしてる間も、事情なんて知らないタクミが茶化すように騒いでる。なのに彼はしばらく俯いたまま何も言わなかった。いつもなら、ここでタクミを叱るか、一緒にチャラけるかするのに。だから無言はかなり怖――。
「……消せ」
不意に彼が発した一言で、タクミも急に静かになった。シーン…と空気が凍り付く。それを悟ったように健太郎が立ち上がり、黒板のいたずら書きを黙々と消していく。その間、この冷めた空気に耐えられず、わたしは呼吸をするのもままならないくらい苦しくなった。彼は手に持ってるボールペンをカチカチしながら、持って来たプリントに何やら書き込んでいる。顔が見えないから、怒ってるのかどうかも分からない。
「あー…今日の授業は夜蛾先生に代わってもらったから、先生が来るまでこの問題やってて。今の能力を見て個別に作ってもらったから名前書いとくし、自分の持ってってくれる?」
「あ…はい」
ふと顔を上げた彼がわたしを見るから、条件反射で返事をする。声の感じから機嫌は悪そうだ。やっぱり怒ってるんじゃ…と不安になった時だった。カチカチというボールペンの音が止まって、他のみんなも一斉に顔を上げた。
「…こんな…セクシー系じゃないから」
「へ?」
恐る恐る彼を見ると、そこにはいつもの"五条先生"がいた。俯いてた顔を上げると、彼の口元には緩く弧が描かれていて、みんながホっとしたのが伝わってくる。正直わたしも同じ気持ちだった。彼は深い溜息を吐くと、頭をガシガシ掻きながら、後ろの黒板を見上げたけど、健太郎がいい仕事をしたおかげで、あの下らない落書きは綺麗に消えていた。
「ったく。これ書いたの二年のヤツだろ。さっきそこの廊下ですれ違った時、何か僕を見てニヤついてたから何かと思ったけど」
「そーなん?だったら俺らに八つ当たりすんなや。怒った思てビビったやん」
「ごめんねー。イラっとしたら、つい。まあ、二年の奴らには夜蛾先生の方で注意してもらうわ。そもそも夜蛾先生の生徒だし」
彼はそう説明すると「んじゃー僕は今から仙台に出張なんで」と笑いながら教室を出て行ってしまった。ああ、だから今日は夜蛾先生か、と納得しつつ、わたしがチクったと思ってないか聞きそびれたことを思い出す。あの様子じゃ大丈夫の気もするけど、人の心の中なんて誰にも分からない。
「あれ…モカは?」
ふと後ろを見れば、さっきまでいたはずの彼女がいない。どうしたんだろうと思っていると、タクミが「どーせ保健室や」と苦笑した。何でも彼女はしょっちゅう保健室でサボってるらしい。
「悟の授業以外は仮病つこて保健室で寝てるで。ほんまに呪術師になる気ぃあんのか、あいつは」
「…そ、そうなんだ。モカも…先生のファン…とか?」
そこが気になって尋ねると、美琴が「そんな軽いもんじゃないって」と笑った。
「私なんかより、ずっと本気でしょ、あの子。いっつも五条先生のこと見つめてるし」
「え…本気って…」
「私が五条先生にくっついたりしたら、それこそ殺人鬼みたいな目で睨んでくるし、こわってなるもん」
「あ…」
その話を聞いて思い出した。転入早々、そんな光景を見たことがある。あの頃からちょっと気にはなってたけど、まさかそこまで本気とは。通りで変な勘違いをしそうになるわけだ。
夕べ彼にデート相手を確認してしまった自分を思い出し、溜息が出る。彼女のことがなければ、彼のプライベートを訊かずに済んだかもしれない。
「どーせ悟に彼女いたの知ってショックで寝込んでんちゃう?それか、また硝子さんに話を聞きにいったとか」
「…しょーこ…さん?」
聞いたことのない名前が出たから聞いてみると、それは彼の同級生という話だった。何でも反転術式を使える術師で、今年から高専で医師として働いてるらしい。それを知ってるモカは、時々硝子さんに彼のことを探りにいくようだ。
「めっちゃ綺麗なお姉さんやで」
「そうなんだ。先生の同級生なら挨拶しにいってみようかな」
そう言いながら、今は主不在の机を見た。わたし達の机より随分と後ろにある彼女の席は、モカの孤立をより顕著なものに見せている。何度こっちへ来たら?と誘っても、彼女自身が嫌がるのだから仕方ない、と諦めていたけど、もし彼のことを本当に好きなら、モカは今、ひとりでツラい思いをしてるんだろうな、と思った。
――みたいな子がモカと仲良くしてくれたら安心なんだけどね。
その時、ふと彼に言われた言葉を思い出した。出来ることなら、わたしだってそうしたい。せっかく仲間になったんだから、モカだけ孤立するようなことはして欲しくないし、今より親しくなれれば、任務の時だってスムーズに戦えるはずだ。
「あれ、、どこ行くの?」
「うん、ちょっと保健室」
「え?具合でも悪いの?」
「ううん。まだ夜蛾先生、来なさそうだから、モカの様子だけ見てくる。すぐ戻るから」
「え、早くねー!夜蛾先生、遅刻にうるさいからー」
美琴に保健室の場所を聞いて教室を飛び出すと、後ろからそんな言葉が追いかけてきた。夜蛾先生が遅刻にうるさいのは百も承知だから、急いでいかなければ、と廊下を走って行く。
この時、何故そんな行動に出たのか自分でも謎だったけど、ずっと気になってたモカのことを彼から頼まれたのは、いいキッカケになったのかもしれない。
もちろん、またウザいって顔をされるかもしれないけど、さっき彼に彼女がいると初めて知ったであろう彼女の肩が、かすかに震えていた。それを見てしまったら、やっぱり放ってはおけない。
――みたいな子が仲良くしてくれたら…
彼の言葉を胸に、一階の外れにある保健室の前へ立つ。いつだって初めての場所は緊張するし、初めて会う彼の同級生がどんな人か気になる。でもそれ以上に、どんな顔でモカに話しかければいいのか悩む…あ、それ以前に授業開始ギリギリでここへ来たことの理由も必要か?と言って、いい案が思い浮かばない。
"保健室"と書かれたプレートを見つめること数秒。モタモタしてたら夜蛾先生が来てしまう。
「よし…」
軽く深呼吸をしてから、意を決して保健室のドアを開けた。
「先生…!お腹痛い…んですけど…って、あれ?」
結論から言えば、保健室の中は誰もいなかった。モカも、そして彼の同級生だという硝子さんも。シーン…という静寂が、今のわたしの嘘を嘲笑ってる気がするくらい、恥ずかしい。今時お腹痛いって小学生か、と自分で自分に苦笑した、その時。奥にあるベッドを覆ったカーテン。その向こうに、ゆらりと人影のようなものが動いた気がした。誰かいる?とドキっとした瞬間、そのカーテンがシャッという音を立てて突然開いた。
「え…?」
そこから出てきたのは、さっき出張だと出ていったはずの彼、五条先生。そしてその後ろ。ベッドの上で俯いてるのは――モカ、その人だった。
「腹痛いの?そこに正露丸あるよ」
「…………」
彼は普段と変わらない態度で言うと、そのまま保健室を出ていく。そんな気配がした。数秒、再びわたしの脳がエラーを起こす。
な、何これ。何これ。何これ。何だ、これ!心臓が一気に稼働して、永遠にドキドキしてるの笑う。カーテンが半分開けられたことで、ベッドの上にいるモカの目に涙が浮かんでるのまで見えてしまう。っていうか、カーテン閉めてってよ、せめて。
「…だ…だいじょう…ぶ?」
どうにか絞り出した声が、かすかに震えてた。でも泣いてたはずのモカは手の甲で涙を拭うと、ふとわたしを見て――微笑んだ。
「あなたこそ大丈夫なの?顔が猿のお尻なみに真っ赤」
「………」
いや、猿のケツと一緒にされても!とは思ったけど、実際は彼女の言う通りだろう自覚はある。その証拠に、顏が燃えるように熱い。
モカは長い髪を掻き上げるようにして、ベッドから足を下ろした。その一連の動作を黙って見てたら、ふと目が合う。思ったのは、この子、本当に綺麗だなということ。素直に羨ましくなる。
それにしても、この状況って――。
(何か…エッチなこと想像しちゃった…かも)
バカだな、と自分に呆れつつ、どう声をかけようかと近くにある使用者名簿へ目を向けた。そこには"一条モカ"の名前がある。こうして字体で見ると、名前まで綺麗だなと感心してしまった。
「…モカって…可愛い名前だよね。誰がつけたの?」
これくらいなら応えてくれるかも、という淡い期待を乗せて尋ねると、彼女はいつものしかめっ面じゃなく、さっきみたいな笑みを浮かべた。
「パパ」
「そ、そうなんだ。モカのお父さん、センスある――」
「パパが入れ込んでる芸者の本名を私に付けたの」
「………ファンキーなお父さんだね」
そんな言葉しか思いつかない自分を殴りたい。でも今のはどう反応すれば正解だったのかも分からない。家が複雑って聞いたけど、ウチとは全然違う事情ってことだけは分かる。いや、名家の主人なんだから、懇意にしてる芸者の一人や二人はいるだろう。そうだ、そういうことだ。ひとり納得していると、モカの口撃はとどまることを知らなかった。
ゆっくり立ち上がった彼女は、動揺が顔に出てるであろうわたしを見て「ねえ」と初めてわたしに声をかけてきた。
「悟と何してたか知りたくない?」
「……は?」
いきなり彼のことを名前で呼ぶから、何をしてたかというより、まずそっちに驚いてしまった。
「さっき想像したでしょ?」
「え…えっと…」
「キスしてたの。悟は優しいから、私の話も聞いてくれるし、泣けばいつでもしてくれるの。いつも……ここに…だけど」
何を言いだすのかと言葉を失ったわたしを意にも介さない彼女は、その白い手を自分の額へと当てた。
――特定の生徒と親しくなっちゃうと…
彼の言葉がグルグルと脳内を回る、回る、回る。
彼女にわたしの心配なんか無用だったようだ。泣けば彼が優しく慰めてくれるらしい。それもオデコにキスという特典付きで。
わたしの彼女へのアプローチは、完全なる失敗に終わった。
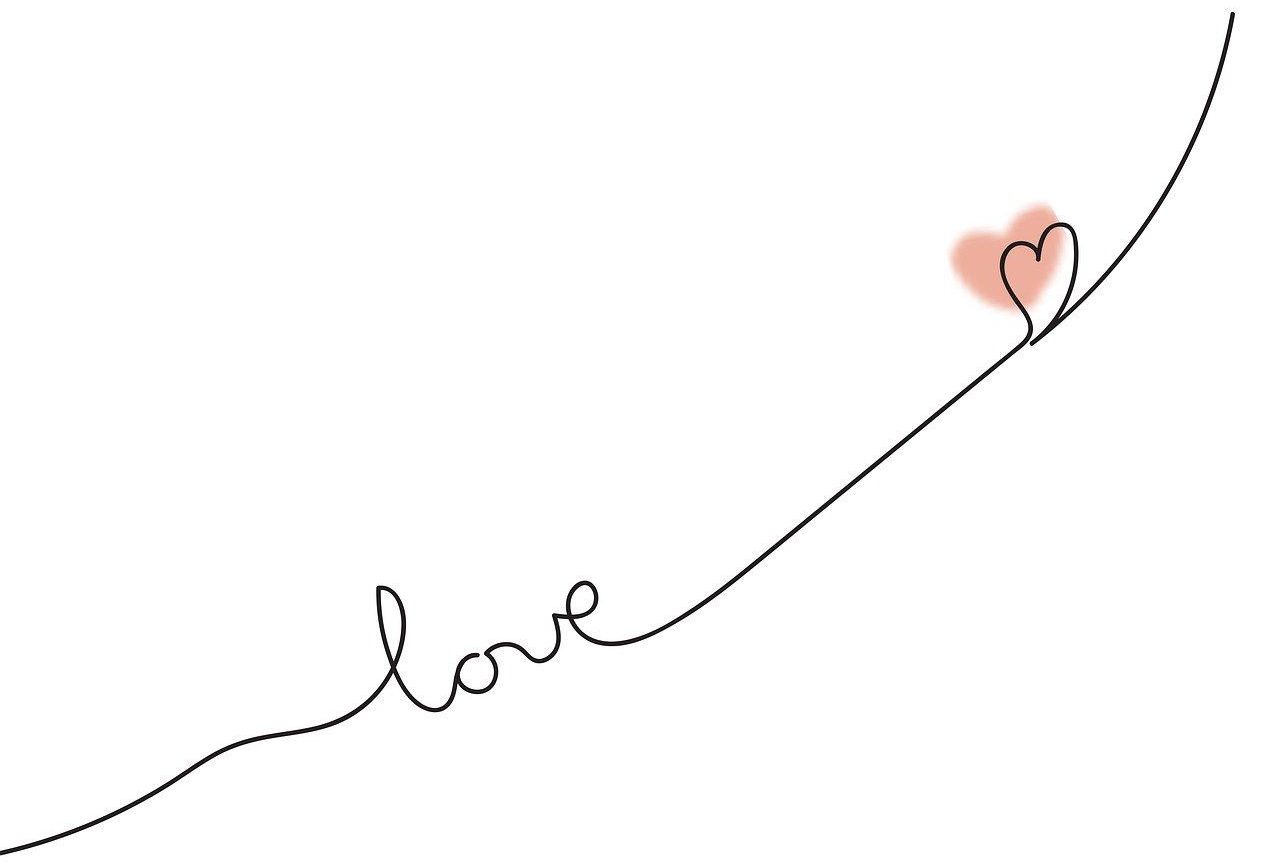
ひとこと送る
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
