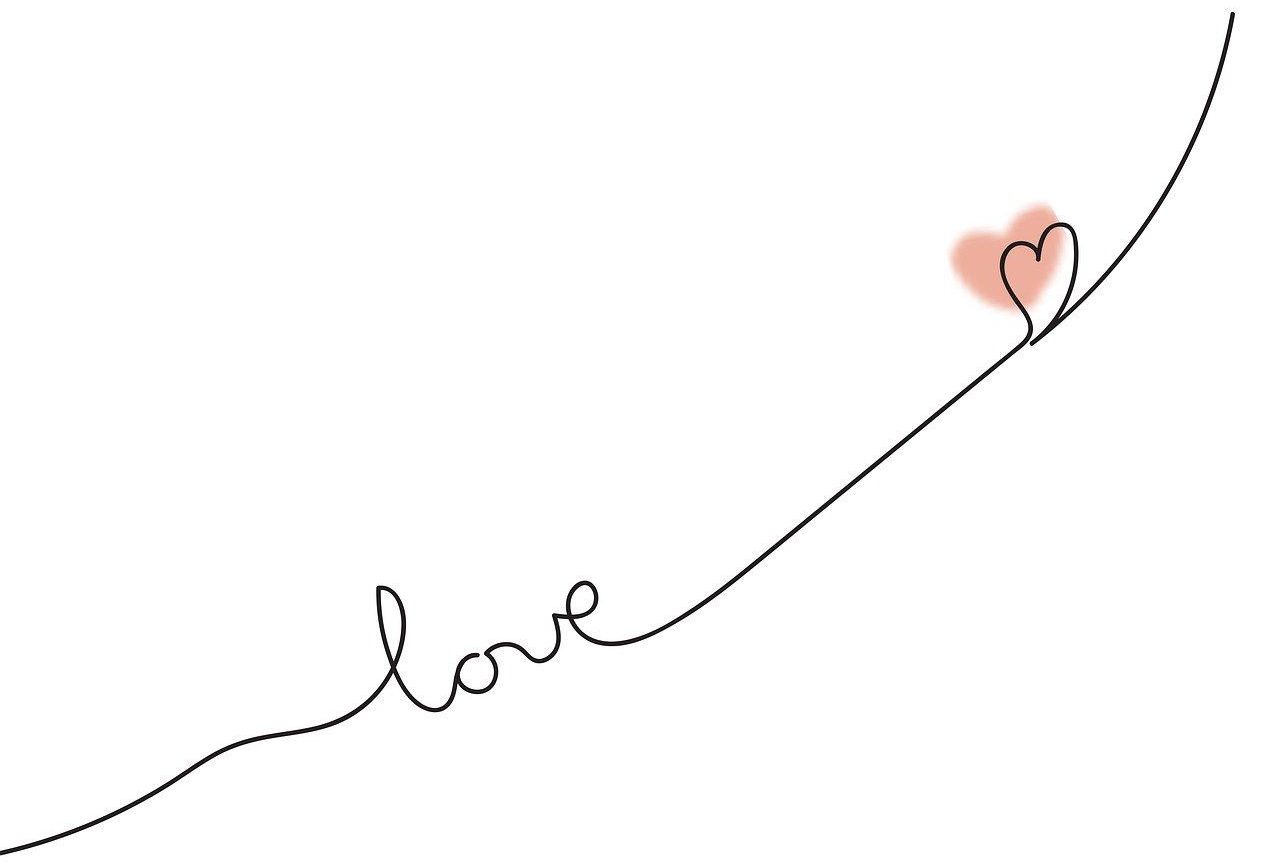君と私のビオトープ-01
都心部から離れた山脈地帯。その麓にあるのが呪術高等専門学校。
一見してお寺に見える古ぼけた校舎は、わたしのほろ苦くも、どこか甘い"青い春"を――全て知っている。
ついこの間まで青々としていた木々たちが、薄っすら紅葉してきてるのを見上げながら、ああ…もう秋なんだ、と感じた。そう言えば、あんなにうるさかったセミの声もしなくなって、夜になれば、どこからともなくリンリン…と鈴虫が鳴く音が聞こえてきてたっけ。仄かに香る金木犀すら夏の終わりを明確に伝えてくるようで、小さく溜息が漏れた。
「早いなぁ…もう今年も僅かなんて。ついこの前、お雑煮食べた気がするのに」
子供の頃に流れる時間と大人になって流れるそれは全然違う。昔は一年がとても長く感じてたけど、大人になった今は、字の如くあっという間に時は過ぎ去っていく。目新しいものが減って、当たり前が増えていき、だんだんと刺激がなくなっていくのは、大人の悲しい性なのかもしれない。
「さーん」
なーんて…まだそんな年齢でもないのに、少しだけ感傷に浸りながら校舎へ歩き出した時、校庭にいたらしい生徒の一人が、わたしに手を振ってるのが見えて、ふと足を止める。広い校庭には男の子ふたりと女の子がひとり。今年、高専に入ったばかりの一年生達だ。たった三人?と言われそうだけど、わたし達のような呪術師は少数派。昨今、少子化が加速する現代では、これでも多い方だと彼らの担任が喜んでいたのを思い出す。確かにわたしの時代は今より生徒数も多かったっけ。
「お疲れさまっす」
わたしに声をかけてきたのは一年ズのひとり、虎杖悠仁。彼は不運に不運が重なって、この高専にやってきた"特例"扱いの生徒だ。
「お疲れ様、虎杖くん」
「任務帰りっすか?」
「うん、まあ。そっちは?」
駆け寄って来た虎杖くんを見て、わたしも校庭へ足を向ける。太陽の光が徐々にオレンジへ変わったせいか、わたしの影が虎杖くんの足元まで伸びていた。
「オレ達は午前中に任務で、午後は体術の練習しろって五条先生が」
「そっか。で、その五条先生は?姿がないけど」
「あ~。何か用があるからお前たちだけでやってろって言って、どっか行っちゃって」
「え…任務でも入ったのかな」
「いやぁ…それなら任務だって言いそうなもんだけど…」
腕を組んで小首を捻る虎杖くんの様子を見ている限り、行き先は何も聞かされてないようだ。その時点でわたしは、"悟のヤツ、サボったな…"と内心溜息を吐いた。呪術界の要、五条悟は特級呪術師であると同時に、高専では一年担当の教師でもある。なのに時々生徒に自分の任務を押し付けたり――本人は愛のムチとか言ってたけど――、簡単な授業だと、生徒を放置してどこかへフラリと行ってしまう悪癖があった。
「また生徒放置してどっか行ったんだ…」
「え、やっぱオレら放置されてたんだ」
虎杖くんは天然素材で超素直な性格だ。16歳にしては大らかな一面も持ってるから、その性格の良さもあってか教師に放置されても、むしろ楽しげに笑い出した。
「五条先生って面白いよなぁ。昔からあんな感じ?」
「え?何でわたしに訊くの?」
学校内じゃ悟と少し距離を置いて接してたつもりだったから、彼の昔を訊かれて少し驚いた。虎杖くんはキョトンとした顔だ。
「ああ、だってさんって昔、五条先生の教え子だったって聞いたし」
「え、あ…ま、まあ…うん…そう、かな。といっても…わたしの担任は今の学長で、悟は教育実習って形だったけど――」
何だ、そこは知ってたんだと認めつつ、ついうっかりしてたらしい。不意にニヤケだした虎杖くんと目が合って、ハッっとした。
「ふ~ん。名前で呼ぶってことは、やっぱり付き合ってんだー。さんと五条先生」
「…う…」
わたしのバカ!と自分で自分をマジビンタしたくなった。こういう反応をされるのが嫌だから、ふたりの関係は秘密にしようって言いだしたのはわたしだったのに、何て間抜けなんだろうと頭を抱える。虎杖くんは青くなったわたしを見て、ますます顔がニヤけだした。
「何となく五条先生の態度とか口ぶりからして、ふたりは親しいのかなーと思ってたけど、そっかー!やっぱなー!釘崎お見事だわ」
「あ、あの…虎杖くん…?その話は…っていうか…え、野薔薇ちゃんがなに?」
最悪、虎杖くんだけなら、と思ったわたしが恐々尋ねると、彼はあっさり「ああ、最初にふたりが怪しいって言いだしたの釘崎なんすよ」と満面の笑みを浮かべた。彼の白い歯がやけに眩しい。
「オレと伏黒はねーだろって言ってたんだけどさー。釘崎に女の勘を舐めんなって言われて…」
「……は、ははは」
隠し通せてると思ってたのは、どうやらわたしだけだったらしい。子供と侮るなかれ。16歳でも野薔薇ちゃんはしっかり女だった。
でも、それもそうか。約7年前には16歳だったわたしも、そういう男女の微妙な空気とか結構気づいてた気がする。
――おら~。とモカ!あと100週な~!
――100週むり…!
――五条先生、鬼すぎる!
ふと脳裏に浮かんだ過去の光景が目の前の風景と重なって、ビビるくらい懐かしさを感じた。ついでにライバルの顔まで。
昔、わたしもこの場所で、今の虎杖くん達と同じように青春を謳歌してた頃が、確かにあった。
「でも…何で隠してんの?さんは教師じゃないし、別にオレらに隠さんでも良くない?」
引きつったわたしを見て、不思議に思ったらしい。虎杖くんは素朴な疑問ってやつをぶつけてきた。そう言われるとそうかもしれないけど、悟は彼らの担任でもあるから、そんな個人的な面を堂々と見せていいとは、わたしは思わなかった。まあ、悟は地味に不満そうだったけど。
「だ、だって…恥ずかしいじゃない…。みんなで顔合わせた時に変な空気になるのも嫌だし…」
それでなくても"元教え子"みたいな扱いをされてるわたしからすれば、やっぱり先生と教え子のカップルと見られるのが一番照れ臭ったりする。こういうのは悟の方が嫌がりそうなもんなのに、彼はその辺全く気にしないタイプだったのも誤算だ。先生の時はそれを理由に何かと突き放したクセに、いざ付き合ったら、わたしがビックリするくらいベタ甘になった。だから余計オープンに付き合うのはマズいと思ったのに。
「ってかさん可愛いっすねー。もしかして、めちゃくちゃシャイだったり?」
「う…。先輩をからかわないでよ」
真っ赤になったわたしを見て、虎杖くんが肘でつついてくる。昔は大胆なとこも多々あった気がするけど、大人になればなるほど、あの頃のような無茶が出来なくなって、代わりに照れ臭いが先に立つようになった。平気でやってた無謀な行動も、今はもう出来ないと思う。
「と、とにかく…五条先生とのことはどうか…」
といっても野薔薇ちゃんに薄っすらバレてるなら、これ以上隠す意味はないのかもしれない。でもハッキリ付き合ってるとバレるのは、やっぱり抵抗があった。その思いを乗せて虎杖くんにお願いすると、彼はニカッと笑ってピースを出した。
「大丈夫っす。これ言ったら釘崎のヤツに、まーたどや顔されっから教えてやらん」
「ほんと…?」
「本気と書いてマジ!約束する――」
と虎杖くんが、古風にもわたしに小指を差し出した、まさにその時。
「だ~れが、どや顔するって?」
「うお!」
虎杖くんの背後からヌっと顔を出した野薔薇ちゃんと伏黒くんを見た瞬間、わたしは「もうダメだ…」と深い溜息を吐いた。
「お前ら…今の聞いてたのかよ!」
「あんたがサボってるから呼びに来たら聞こえちゃったのよ。でも、当たってたわねー?私の勘!」
驚く虎杖くんを鼻であしらい、野薔薇ちゃんが「がっはっは」と声高らかに笑う。隣の伏黒くんに至っては「んなの本人に聞かなくても知ってたし…」と小さな声でぼそりと呟いた。まあ、伏黒くんは子供の頃にバレてるから、それは仕方ないけど。
「ほら、やっぱどや顔すんじゃん!」
「うるさい。っていうか鈍感の虎杖はともかく、伏黒!あんただって、五条先生とさんが付き合ってるはずねえって言ってなかったっけ?!」
「……あれは…」
急に話を振られた伏黒くんは、泳がせた視線をわたしに向けてくる。きっと言っていいんスか、的な顔だろう。でも当事者のわたしは、もう諦めの境地だった。
「なんとか言え、伏黒っ」
「口止め…」
「はあ?口止め?」
「…された」
伏黒くんもわたしと同じ心境だったのか、虚ろな表情を隠そうともしない。おもむろに顔を背けて、ぼそりと呟いた。
「何でカタコト?ってか、誰に口止め…」
「あーそれ僕が恵に頼んだの」
「…っ?」
今度は野薔薇ちゃんの背後から、黒いアイマスクをつけた男がヌっと顔を出した。やっと三人の担任がご登場らしい。
「ご、五条先生!」
「なになに~。僕がいない間にを問い詰めてたってわけ?」
悟はヘラヘラしながら項垂れてるわたしの方へ歩いてくると、徐に肩をぐいっと抱き寄せてきた。ああ、頭が痛い。
「まあ僕としては隠すつもりなかったんだけどさー。がどうしても秘密にしたいって言うから、恵にも口止めしといたんだよ。恵とは付き合い長いからねー。昔の僕を知ってるし」
「ちょ、ちょっと悟…手を放して」
「いてっ」
悟が呑気に説明しながら肩を抱き寄せるから、手の甲をパチンと叩く。わたしに触れてる時は無限がオート解除されてるからだ。
「何も叩かなくても…」
「せ、生徒の前だし…。っていうか、その生徒を放置してどこ行ってたんですか!五条先生!」
話題を変えたいのもあって大げさに怒りながら敢えてそう呼ぶと、悟は何かを思い出したように笑い出した。
「あの頃は叱るの僕の役目だったけど、大人になったよなー?も」
「ぐ…また子供扱いする…。もう生徒じゃないんですけど」
「それはそうだ。今やは僕の可愛い恋人だからね」
「……ちょ、そんなハッキリ――」
「もうバレたんでしょ?」
焦るわたしをいなすように、悟は微笑んだ。昔と違って怪しげなアイマスクはしてるけど、きっとその奥にある碧の宝石は、優しい輝きを放ってることだろう。想像するだけで頬に熱を持ってしまうのは昔からだ。
「うわー!ふたり仲いいんだー!さん真っ赤だよ」
「の、野薔薇ちゃん…からかわないで」
恐れていたことが今、現実となって起きてることに眩暈がする。悟と違ってわたしは教師じゃなく、ただの呪術師だ。けど、高専の生徒にプライベートを晒し、からかうネタを提供してしまったことは、術師の先輩として情けないものがある。なのに少しも気にしてない悟を見てると、嬉しい反面、やっぱり恥ずかしい気持ちが先に立ってしまう。
(でも…わたしも十代の頃は何でも興味を持って、些細なことでも騒いでたなぁ…)
目の前で楽しそうにはしゃぐ三人を見ていると、過去の青い春の記憶が鮮明に蘇ってくるようで、少しだけ胸の奥が苦しくなった。どうやら記憶は、昔の切なさまで連れてきたらしい。ふと隣に立つ悟を見上げれば「どうした?泣きそうな顔しちゃって」と笑われた。
「…ちょっと…あの頃のこと思い出した」
「ああ。僕の後を追いかけまわしてたこと?」
悟の艶々した唇が、意味深に弧を描くから、頬がまた熱を持った。
「そ…それは…モカでしょ」
「まあ、それも否定はしないけど」
悟はそう呟いて、そっとわたしの手を握った。きっと悟も思い出してるに違いない。聡い仲間を育てる為に、教師になろうと必死だった自分と、初めて受け持った生徒達のことを。
「ねーねー。どっちから告ったのか聞いてもい?」
不意に虎杖くんがそんな質問をしてきてギョっとした。なのに悟は平然と「あー…最初は…」と言いながら、わたしを見下ろし、ニヤリと笑う。最悪だ。
「かな~?」
「ちょっと悟――!」
「「マジで?!」」
虎杖くんだけじゃなく、野薔薇ちゃんまでが食いついて話に入ってきたから、どんどんわたしの顔は熱を帯びていく。出来れば忘れてて欲しかった。
「なんてなんて?」
「い、虎杖くん、そんなプライベートな質問は…」
思い切り身を乗り出してきた虎杖くんに、わたしだけが慌てたけど、悟は「教えな~い」と言って、虎杖くんのオデコにデコピンをかました。
「いてっ」
「あれは可愛かったから僕の記憶だけにしまっておくんだよ」
「えーますます気になるんだけど!ってか、ふたりはいつから付き合ってんの?まさか…先生と生徒の頃から?もしそうならエッチくない?」
「の、野薔薇ちゃん!そんな話はいいから…!っていうか悟も生徒を煽らないでよ」
思ってもないこと言っちゃって、と思いながら睨みつけると、悟は澄ました顔で「本心だし」と舌を出す。その憎たらしい感じが、昔の悟と重なった。
でも――そんな悟のことを、どうしようもなく、好きになったのはわたしだ。
あの頃のわたしは、親が離婚とか初彼に振られたとか、色んなことが結構どん底で、呪術師になること以外は未来に何の希望も抱いてなかった。知らない土地。知らない学校。親友とも離れ離れになった現実に、17歳になったばかりのわたしは押し潰されそうになってて、新しい環境に慣れるか凄く不安だった。
でも、そんな不安を消してくれたのが――教育実習を始めたばかりの五条悟だった。