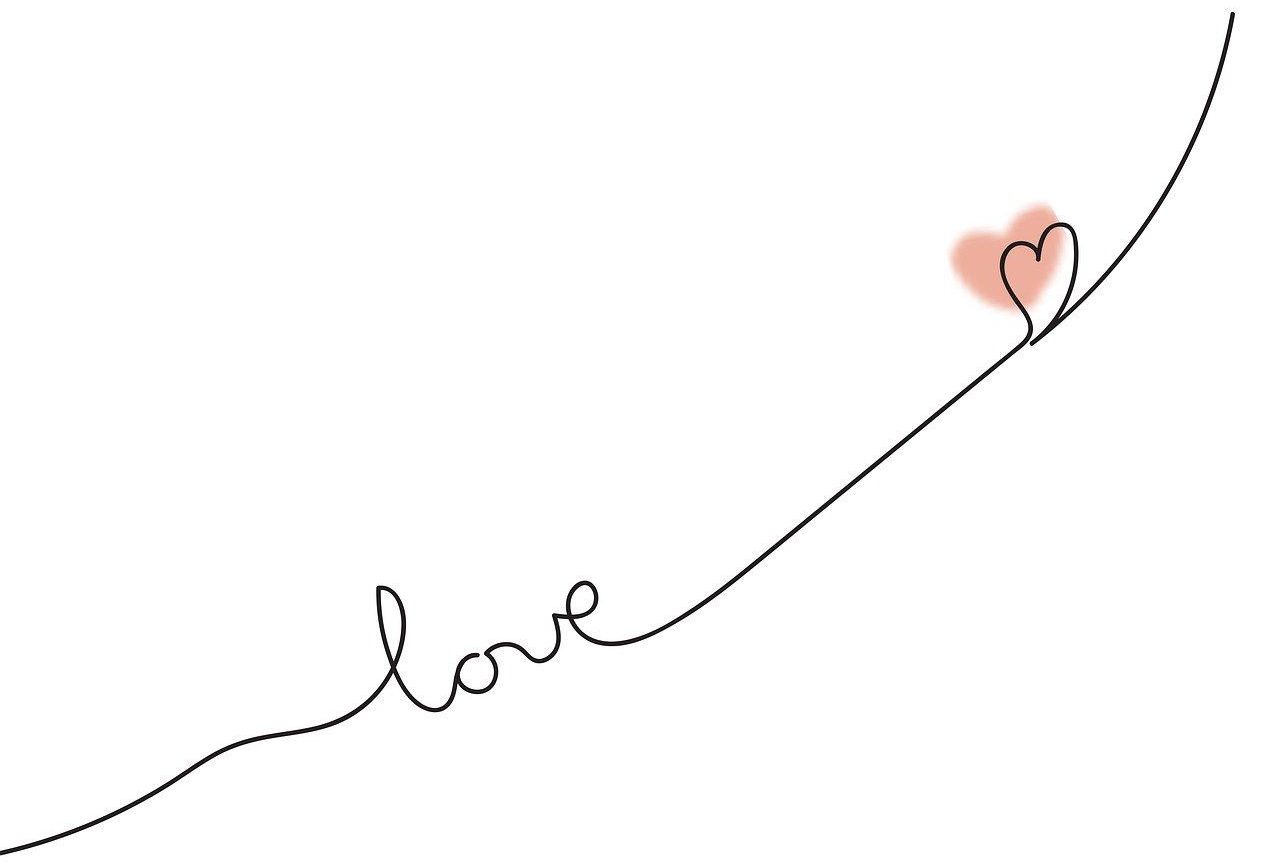君と私のビオトープ-02
"ねえ、ちゃん。これだけは覚えておいて。もし、ちゃんが持ってる側だったとしたら…ママとパパは離れて暮らすことになるかもしれないの"
それは幼い頃、母に何度も言われた言葉だった。
これまで当たり前にあった日常が、最悪の形で一変することになったら…――誰でも大なり小なり絶望感に打ちひしがれるんじゃないだろうか。
2011年、16歳最後の秋。わたしも今まさに、心が真っ暗闇に落ちていた。
「え、嘘…離婚すんの?!の親!」
放課後、ホームルームが終わった後に思い切って切り出したら、小学校からの親友は、わたしの想像以上に驚いた顔をした。青い春を謳歌中の16歳にしてみれば、親の離婚はそれなりに大事件。人の反応を見て、鈍いわたしでも改めてそれを実感した。
「うん、遂に。まあ、ほら…昔からわたしの将来のことでモメてたでしょ?そろそろかなーと覚悟はしてたんだ」
「そりゃ聞いてたけど、娘の将来のことでホントに離婚するなんて思わないよ。え、はどうするの?」
この場合の「どうする」とは、どっちに着いてくのってことだろう。その答えは離婚の話が出るずっと前から、とっくに決まってたようにも思う。
「お母さん。お父さんは…わたしのこと嫌ってるから」
「え~、前からそれ言ってるけどさー。娘を嫌う父親なんている?」
驚き半分、呆れ半分の親友の問いに、わたしは言葉を詰まらせた。出来れば「そうだよね」と相槌を打ちたいとこだけど、無理だ。親友の常識は、あくまで"普通の家族"内での話だから。だけど、うちは違う。この話はいくら親友といえど、話せないから今も秘密だ。
子供の頃から聞かされてきた世界のことは、内緒にしなくちゃならない。この世のバランスを、保つためにも。
「まあ…そういうことだから…さ。わたし、転校するんだ」
「えぇ?!」
ロッカーにしまいっぱなしだった教科書を、持って来た鞄に詰めながら言えば。親友はさっき以上に驚いた顔で固まった。こういう話の時、しんみりはしたくない。だからサラっと言ったつもりだったのに、事情を話す前から涙なんて浮かべるから、わたしもちょっと泣きそうになった。我慢したけど。
「ど…どこに?学区が変わるだけとか?」
「ううん、東京。お母さん元々、そっちの人なの。だから…年内に引っ越しって、二年からは東京の学校に通うことになって」
「嘘…東京に引っ越しちゃうの?めっちゃ遠いじゃん!え、じゃあダイチは?どーすんの?」
「…ダイチには夕べ話した。どうするかは…まだ話し合ってないけど、一応、この後に約束してる」
ダイチは付き合って三か月になる初めての彼氏だ。ここに入学して同じクラスになってから、何の腐れ縁かずっと隣の席だった男の子で、お互いを意識するのに、それほど時間はかからなかった。
――オレと付き合わねえ?
夏休み目前に告白をされ、わたしもダイチが気になってたから即OK。それ以来、わたしなりに楽しく青春を謳歌してたのに、まさか本当に親が離婚するなんて――いや、いつか離婚するかもしれないとは思ってたし、その「いつか」が今になっただけ。ただ単純にお互いの愛情が冷めたとか、性格の不一致とかだけならまだ良かったかもしれない。でも事情はもっと複雑だ。
「えー…ほんとに東京行っちゃうの…?転校する学校は?なんて高校?」
「あー…えっと…東京郊外にある田舎の学校…だよ、うん…。名前は…なんだったっけな」
親友の質問に曖昧な言葉を返したのは、事実を話すことが出来ないからだ。
(まあ…呪術専門の学校、なんて言ったところで、信じないとは思うけど)
派手に泣きだした親友を宥めながら、自分の運命を密かに呪う。でも呪ったところで簡単に変えられるものでもないから、今はお母さんの言う通りにしなきゃいけないというのも理解してる。
そもそも小学校に入学する前辺りから、お母さんの言う"持ってる側の人間"だと分かった時点で、わたしの未来はすでに決まっていたのかもしれない。
むしろ、お父さんが7年以上もよく我慢してくれたもんだ。
20歳という若さでわたしを産んだ母は、それまで呪術師という職に就いていた。呪術師とは、人間の心が生み出す"呪い"と呼ばれる化け物を祓うのが主な任務で、術師として才能のあったお母さんは呪術を学ぶ学校に通いながら、日々化け物を祓うといった生活をしていた。今の緩いお母さんを見てるとイメージすら湧かないけど、「ママ、なかなか強かったんだから」と、毎回ドヤ顔で言ってくるのが、地味にウザいと思ってたりする。
そんなお母さんが、ある時、北海道での任務で知り合ったのが、道警で働く2歳年上のお父さんだ。今じゃ想像もできないけど、当時のふたりは大恋愛をしたそうで、その結果、わたしを授かった。高専は5年制だから、当時はまだ学生でもあったお母さんは悩みに悩んだ結果、わたしを産むことを決意。周囲の反対を押し切って、非術師のお父さんと結婚するために一年残して呪術高専を中退したようだ。
その後はお父さんの住む札幌に移り住んで――今に至る。
でもそこで一つ問題だったのは、生まれてくる子供に術式なるものが授かっていた場合。
お母さんは自分の育った環境に倣って術師にすることを望んだけど、非術師のお父さんは大反対。もし術式を持って生まれてきたなら、そして術師にするつもりなら、一緒には暮らせないとまで言ったらしい。でもそれは当然のことだと思う。
そもそもの話。術師と非術師はよほどのことがない限り、理解しあえない。価値観が大きく異なるからだ。
警察関係者だったお父さんは秘匿とされてる呪術界のことを知ってはいたらしいから、お母さんのことも理解できると高を括ってたみたいだけど、やはり我が子までがその世界の住人になるのは耐えられなかったんだと思う。それほど悲惨な事件を見聞きしてきたんだろうし、自分の手に負えない化け物たちを日々近くで感じながら過ごすのは、非術師のお父さんからすれば地獄だったろう。それが娘まで、となればなおさらだ。
まあ、わたしから言わせると、呪術師のお母さんを妻に選んだわりに、その辺の覚悟が足りてなかったんだろうとは思うけど。
現にわたしが"視える"ようになった頃から、呪霊はハエの如く寄ってきて、それを肌で感じてたであろうお父さんのわたしを見る目にも、次第に怯えの色が滲んでいった。毎日そんな視線を向け続けられたら、子供の心なんて簡単に"傷"ができる。結果、「大好きなお父さん」が少しずつ他人のような遠い存在に感じられて。だから、やっぱり"家族"としては限界だったんだと思う。
それでも両親の間に愛情はあったんだろう。何だかんだと問題はあっても結婚生活は続けてたんだから。
だけどわたしが16歳を迎える頃。せめて高校卒業までは普通の子として育てたかったお父さんと、すぐにでも呪術を学ばせたいお母さんの間で、またしても意見が分かれた。
でも結論は出ずじまい。そのまま受験シーズンを迎えてしまったことで、一時はお母さんが譲歩して、わたしは今の高校に入学した。だけどお母さんはどうしてもわたしを高専に入れて、きちんと呪術を学ばせたかったようだ。それが原因で、お父さんとは今年に入ってからも毎日のようにケンカが耐えなかったけど、わたしの一言が決定打になってしまった。
"わたし、呪術師になる"
わたし自身、お母さんに色々と教わって育ったから、呪霊を見つけたら祓うのは当たり前になっていたのもあるけど、でも多分そう決めたのは、わたしの力を否定し続けるお父さんに対して、意趣返しみたいな気持ちがあったからかもしれない。
お父さんは何も言わなかった。ただ、わたしに背を向けただけ。その次の日、ふたりは離婚を決めた。わたしは当然のようにお母さんと家を出ていくことになり、お父さんは結婚前の生活に戻る。それだけだ。
わたしにしても、これまでの生活がガラリと変わる憂鬱さはあれど、呪術師になると決めたことはそれほど後悔してない。術式を持って生まれたからには、何か意味があると思うから。
ただ、一つだけ心残りがあるとしたら――。
「、こっち」
泣きじゃくる親友に送り出され、その足で校門に向かうと、わたしを見つけたダイチが軽く笑みを浮かべて手を上げた。サッカーで日焼けした顔が、なかなか男前だと今更ながらに思う。
「ごめんね。待った?」
「いや…ってか、どうせアイツが泣いて引き留めたんだろ」
「まあ…うん…」
隣に並ぶと自然に歩き出す形になって、わたしとダイチは学校近くの公園に向かった。わたしと彼の、いつもの寄り道コースだ。
北風が吹きつけてくるせいで、せっかくブローした長い髪も、すぐにグシャグシャになってしまう。初秋のはずなのに、どことなく冬の匂いがするから、そろそろ初雪が降るのかもしれないなと思った。それくらい、この街の冬は早い。
「…急な話で驚いたでしょ」
ふたりの特等席であるブランコに座りながら、沈む夕日を見上げた。さっきから何かを言いかけては口をつぐむダイチを見て、わたしから話を切り出したのは、すでにわたしの未来は動き出してるからだ。ここでウジウジしても仕方がない。そう割り切って、なるべく明るい声を出す。
「でもほら。飛行機で一時間半?意外と近いよね。東京と札幌って」
「…空港までの移動を入れたらもっとかかるって」
「あ、そっか。ダイチはサッカーの試合で夏に東京行ってるんだっけ」
「…まあ。一年だし補欠だったけどな」
「次は?あ、冬の大会だ。わたし、ダイチの試合見に行くよ。会場って国立?」
「どーせ、それも補欠で出れねーよ」
ダイチが呆れたように笑う。その笑顔を見てると、やっぱり好きだなって思った。この先も一緒にいたら、きっともっと好きになってたかもしれない。
ううん、傍にいられなくなっても、今の想いは持続していける、はず。
「…は…随分とアッサリしてんだな」
「泣いて欲しかった?」
「…うぜ」
軽くブランコを揺らしてダイチの顔を覗き込むと、彼はスネたようにそっぽを向いた。ほんとは色んな言葉が頭に浮かんだし、気を緩めたら泣いてしまいそうだから、何一つ言葉には出来なくて。
湿っぽいのは苦手。だから、わたしは笑うことを選んだ。
本音を言えば、わたしだって引っ越したくない。でも呪術師になるには、わたしもまだまだ学ばなきゃいけないことが沢山ある。
そんな残りたいと思う気持ちと、新しい未来の自分を育てたいという気持ちが、今はせめぎ合ってる状態だ。結局、お父さんにはあんな風に言っておきながら、わたしの心はギリギリで揺らいでるんだから情けない。
だから――きちんと覚悟ができるよう、ダイチにはせめて笑顔で見送って欲しい。
「今時、東京なんて近いじゃん。まあ交通費は高いけど、格安便だってあるし――」
「絶対…引っ越さなきゃダメなやつ?」
ダイチがふと顔を上げてわたしを見るから、つい目を伏せてしまった。そんな捨て猫みたいな顔するのはズルい。
「…うん、ごめん」
「…ふ~ん」
ダイチは俯いて、小さな溜息を吐いた。その横顔はあまり見たことがないくらいに元気がない。
だけど、この時のわたしはまだ続けていけると、心のどこかで信じてた。
「いつ…発つんだっけ」
「…明後日の昼の便」
「マジで急だよな…。ハンパな時期に転校って、行ってもすぐ冬休みじゃねーの」
「まあ…でも転校先の学校は年明けすぐに始まるから、今から行って色々準備もしなくちゃなんだ」
「…年明けから?変な学校」
そう言ってダイチが笑った。まあ呪霊はクリスマスだろうが正月だろうが関係なく生まれるわけで、呪術を学ぶ高専だって、普通の学校のようにはいかない。冬休みなんて呑気なものはないし、何なら、行ってすぐに通えるようにはなっている。でもその辺の事情はダイチに話せない。
「出来るだけ…電話するね」
そう、今はケータイもあるし、メールだって出来る。昭和でも平成初期でもないんだから、遠距離を繋ぐものはいくらでもあるんだ。そう思えば少しは気持ちも楽になった。
なのに――ダイチはしばし無言のまま。でも唐突に「ごめん」と呟いた。
「オレ…無理だわ…」
北風が吹いて、ダイチの絞り出した言葉が秋の空気に溶け込んでいく。冷えた音が鼓膜を揺らして、彼の言葉を理解した時、一番大事なことを失念してた自分に気づいた。
わたしは"持ってる側"で、ダイチは"持っていない側"だということを。ダイチは何も知らないけど、ここで別れなくても、いつかきっと、その関係性に歪みが生じるのは、両親を見て分かってたはずなのに――。
16歳のわたし達にとって、東京は日本の裏側に位置するブラジルくらい、遠い距離。そして、術師と非術師という関係は、二次元と三次元のような、次元の違う存在。それは決して、交わらない関係なのかもしれない。
わたしはもう、笑うことすら出来なかった。