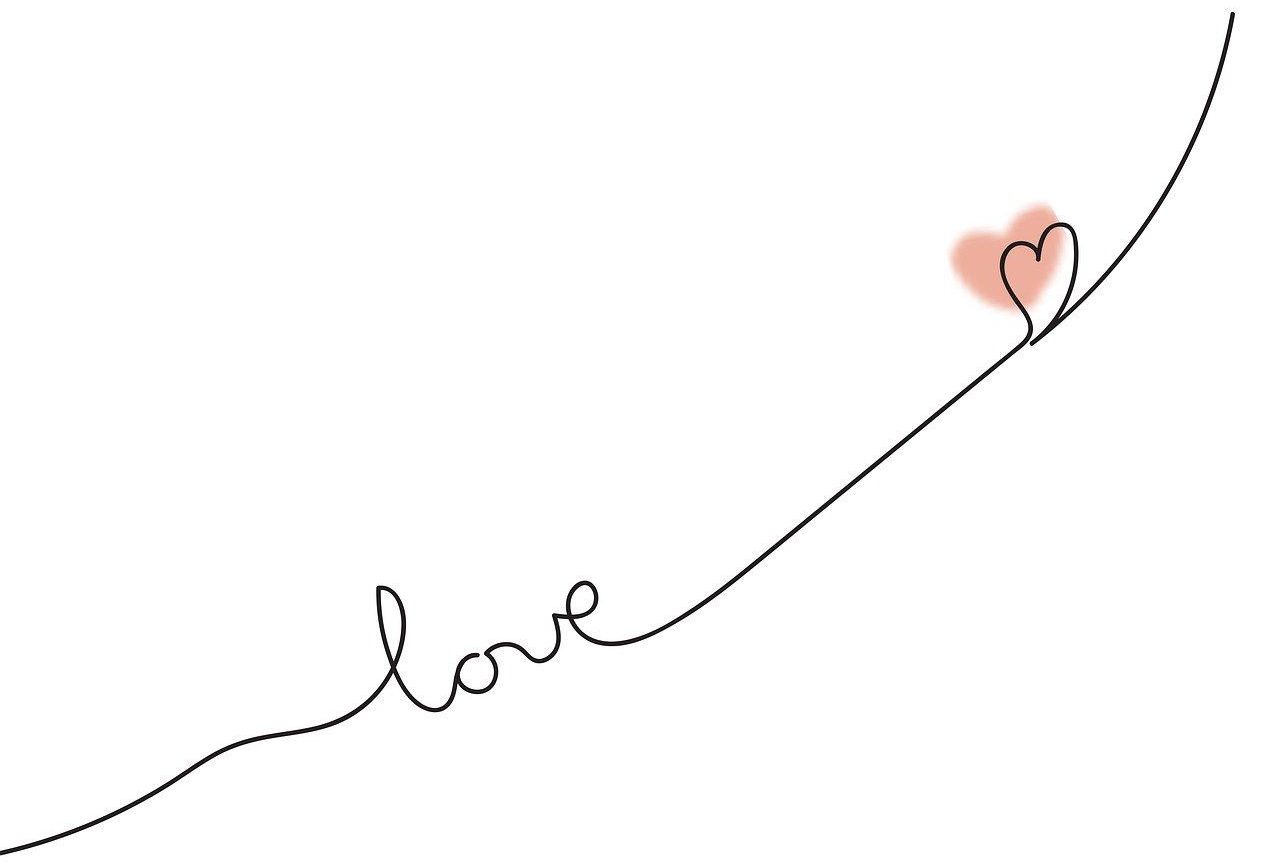君と私のビオトープ-03
「ねぇ、ちゃん~。ママのお気に入りのコート、どこに入れたのー?襟がふわふわのやつ」
「知らないよ。自分でつめてたじゃない」
「えー?そうだっけ…」
お母さんはとぼけた顔で、再び積まれた段ボールを一つ一つ漁りだした。それを見ていると、こんなんで今日中に荷解きが終わるのか…?と心配になる。
一旦、手を休めて自分の部屋の窓を開けると、最初に出したサンダルを履いてベランダへ出た。リビングにも続く長いベランダだ。最初に自分の部屋を見た時、こっちにまでベランダが続いてるのはテンションが上がったけど、目の前に広がるのは東京らしかぬ景色。町を囲むように聳える高い山、山、そして山。想像以上の田舎だ。
わたしとお母さんの引っ越し先は、東京郊外にある呪術高専のすぐ近く。山に囲まれた町の駅前にある比較的大きな20階建てマンションだった。今日からそこの最上階に住めるのは地味に嬉しい。これまで住んでた家は戸建てだったからだ。ただ、見える景色が大自然のみなんて、ちょっともったいない気もする。都内だったら確実に見えたであろう煌びやかなネオンもないだろうし、夜は真っ暗で何も見えなさそうだ。
「あれが高専か…」
正面に見える山々の合間に、お寺のような建物も僅かに視認できる。あそこがお母さんの母校――中退したけど――でもある呪術高専らしい。どんな人達がいるんだろうと考えると、やっぱり少し不安になってきた。わたしの場合、お母さんに呪力コントロールや、呪いの祓い方の基礎は教えてもらったけど、全て付け焼き刃でしかない。とりあえず視えるようになったわたしに、お母さんが身を守る為の方法を即席で教えてくれたにすぎず、きちんと一から教わってるであろう高専の生徒についていけるのかどうか、今更ながら心配になった。
「しかも二年からだしなぁ。すぐ落ちこぼれそう…」
こうなってくると、やっぱり一年から入学したかったとシミジミ思う。
「はあ…サッサとと片付けよ…」
重苦しい溜息を一つ落としながら窓を閉めると、再び荷解きに戻る。こっちについたのは昼過ぎだったせいか、すでに夕方近い。お腹も空いてきたわたしは、そこから黙々と荷物を出し、空いた段ボールを畳む、といった作業を繰り返した。すると二時間ほどでガランとした部屋がやっと人並みの状態まで片付いていた。
「終わったぁ~…」
両腕を伸ばしながら整えたばかりのベッドへ寝転ぶと、ついでに両脚も伸ばしておく。慣れない作業を一気に済ませた体は筋肉痛で悲鳴を上げていた。
「いたた…ここ一カ月は荷造りと掃除ばかりしてたもんなあ…」
というか、ずっと住んでた場所から引っ越すってこんなに大変なんだと実感した。出来れば二度としたくない。しばしベッドの上でゴロゴロしてると、疲れもあってか少し眠くなってきた。そこへお母さんが顔を出す。
「ちゃん、終わった~?って、何よ。自分だけ寛いじゃって」
「だって片付けたもん。そっちは?終わった?」
上体を起こして尋ねると、お母さんは「とりあえずはねー」と言いながら息を吐いた。お母さんもかなり疲れてるみたいだ。でもそれも当然か。今年に入ってからは常にお父さんとバチバチ状態だった上に、離婚手続きをして、引っ越し先を決めたり、移転届を出したり、わたしのことで色んな準備もしてくれてたんだから。
「はあ…もうすっかり夜ね。今夜のご飯どうする?何かデリバリーでも頼む?」
「えー。すぐ近くに大きなスーパーあるんだし、買い物に行こうよ。わたし、色々買い揃えたいものあるし」
「そんなの後々でいいじゃない。ママ、作るの面倒だし」
「じゃあ焼肉は?さっきプレートも出したし、肉と野菜だけ買えばすぐ食べられるでしょ」
そう提案すると、お母さんは「いいわね、焼肉」と笑顔になった。少しは行く気になってくれたようだ。そこで出かける用意をすると、ふたりで徒歩数分の大型スーパーへと向かった。田舎だけど、マンション下にはコンビニもあるし、立地的にはなかなか便利そうだ。
「ねえ、ちゃん。お肉どうする?牛の他に豚や鶏も買おうか」
「うん。わたしは何でもいいよ。お腹ペコペコだし」
「そう?じゃあ…ちょっと奮発して高いの買っちゃお。パパの安月給じゃ、あまり贅沢できなかったし」
お母さんはサラリとお父さんをディスりながら、ウキウキしたように高級肉を次々カゴへと放り込んでいく。元々は良い家の出らしく――家族全員が呪術師らしい――お父さんと結婚する時に勘当されたとはいえ、中身は昔からお嬢様気質だったっけ。
(ま…公務員のお父さんの給料じゃ、Aランクのお肉はしょっちゅう食べられないよね)
家族で焼肉する時に食べてた安いお肉を思い出し、苦笑いが零れる。愛があるうちは何でも我慢できてたんだろうけど、今はその我慢してた分の反動が出てるみたいだ。
でも、お父さんだってお母さんの誕生日や、わたしの誕生日には奮発して高級レストランへ連れて行ってくれたこともあった。そういう嬉しかった時の気持ちも、愛が消えたら忘れちゃうのかな。
ふとそんな思いが過ぎった瞬間、ダイチの顔が浮かんだ。あの公園で会ったのが最後で、三日後、千歳空港へ向かう際のお見送りに集まった友達の中にダイチの姿はなく。完全に終わったんだと言われた気がして悲しかった。
きっと、わたしのことなんてすぐに忘れて、また違う恋を見つけるんだろうな。ツラいけど、この道を選んだのはわたしなんだから仕方ない。
「…っと。ねえ、ちゃんてばっ」
「え?」
気づけばボーっとカートを押してたらしい。後ろからお母さんが走ってくるのに気づいて足を止めた。夕飯時で混雑してる中、何人かにぶつかっては謝ってる姿を見て、そんなに離れてどこに行ってたんだと苦笑が漏れる。
「もう…ちゃんってば勝手にどんどん行かないでよ~」
「ごめん…。ってか…それ何?」
見ればお母さんの手に箱が3つほど持たれている。きちんとラッピングされてる感じから、食材とかじゃない。
「ああ、これ。引っ越しの挨拶用にどうかと思って」
「…引っ越しの挨拶ぅ?」
「そうよー。最上階に三つしか部屋がないんだし、やっぱり挨拶はしとかないと。このスーパーの二階に雑貨屋さんとか服屋さんとか百均ショップがあるの見つけてね。ついでにお隣に配る物を選んでたの。どれがいいか聞こうと思ったのにちゃんってばついてきてないんだもん」
「……声かけてよ」
相変わらず呑気な人だと溜息を吐きながら、改めてお母さんの手にある箱を見る。それはありふれたタオルのようで、わたしは若干顔が引きつってしまった。
「え、待って。この何の変哲も工夫もないタオル持ってく気?」
「え~ダメ?」
「今時こんなもの貰って喜ぶ人いないでしょ。もうちょっと使えるものにしなよ」
「…何よ。そこまで言うならちゃんが選んでよ」
「…(あ、スネた…)」
大人げなく唇を尖らすお母さんは、36にもなって未だ少女みたいなとこがある。美人さんでスタイルもいいし、髪なんかふわふわ。娘のわたしから見ても可愛いんだから嫌になる。逆に娘のわたしは、悲しいかな、お父さんに似たらしい。身長はそこそこもらえたけど、髪だって直毛。巻いたところですぐ落ちちゃうから、今はもうふわふわの髪にするのは諦めてる。性格だってそう。素直になれないわたしと違って、お母さんは自分に素直で無邪気で誰からも愛される。まあ、娘からすると少し頼りないけど。その反動なのか、わたしがシッカリしなくちゃと思わされる。男に振られても素直に泣けない可愛げのない性格に育ったのは、案外この人のせいかもしれない。
「仕方ない…。じゃあこれ買ったら選んであげる」
「そう?じゃあママ、二階で待ってるね」
今の今までぶーたれてたお母さんは、満面の笑みで去って行った。全く、この大量の食材を押し付けないで欲しい。
言いたいことはあれど、お腹が空いて限界のわたしは、すぐにレジへ行って会計を済ませた。その足でスーパーの二階に行くと、お母さんの言ってた通り、雑貨屋さんやちょっとした服屋などがある。これは便利すぎるかもしれない。
「えっと…お母さんは…」
と辺りを見渡せば、一際目立つコートが視界に入った。さっきお母さんが探してた襟がふわふわのお気に入りコートだ。東京では必要ないんじゃないかと思ったけど、山に囲まれた場所のせいか、意外と寒いのは誤算だった。
「お母さん」
「あ、ちゃん!こっちこっち」
声をかけると、お母さんは笑顔で手を振ってくる。さっき手にしていたタオルは戻したようで、今は何故かマグカップのコーナーにいた。
「ねえ、これなんかどう?可愛いし使えるでしょ」
「…引っ越しの挨拶でカップはないんじゃない?それにこういう物は好みもあるし」
「あ、それもそうか。じゃあちゃんはどれがいい?」
カップを戻すお母さんにホっとしつつ、わたしは店内を見渡して、それらしいのを探してみた。雑貨屋にしては、なかなかお洒落な物が置いてある。
「うーん…そうだなぁ…これは?みんなお風呂には入るんだし、意外と使うんじゃない?」
そう言って手にしたのはバスグッズの類だった。手のひらサイズのカラフルな石鹸や、スクラブの容器が詰められていて、値段も手ごろだし、何よりギフトセットというだけあって見た目も可愛い。それにこういった物はそれほど好みも気にしなくていい気がした。お母さんもそれには満足したようで「これにしよう」と早速二つ購入していた。
「ところで…両隣はどんな人か聞いた?」
スーパーからの帰り道、ふと気になって尋ねてみると、お母さんは満面の笑みで頷いた。
「もちろん。管理人さんに挨拶した時にね。手前の部屋は老夫婦が住んでて、奥は若い男の人だって」
「…何よ、その顏」
変にニヤつくお母さんに呆れた視線を向ける。何となく言いたいことは分かった気がした。
「だってちゃん、彼氏と別れたんだし、新しい出会いになればいいかな~と――」
「バカ言わないでよ。何でそんな身近なとこで探さないといけないわけ?」
「え~…元カレだって同じクラスで身近な子だったじゃない。それに何か隣人ってだけで運命感じない?」
「……(少女漫画のヒロインか、この人は)」
じっとりした視線を向けると、お母さんは「すぐ怒る子はモテないんだから」と憎たらしい返しをしてきた。
「モテなくて結構です」
ウザい返しをサラリと交わすと、お母さんは面白く無さげに唇を尖らせた。でもすぐ何かを思い出したように怪しい笑みを浮かべるんだから嫌になる。
「あ、その男の人は最近入居したばかりだって。因みに独身らしいのよ。イケメンだといいわね~」
「……あっそ。っていうか、その情報いる?」
「何で?大事じゃない。ちゃんの運命の相手かもしれないんだし」
「もう……運命はいいってば。それにわたしは男と恋愛する為に東京来たわけじゃないし!」
「何よ、そんなに怒らなくてもいいじゃない。冗談でしょー?」
つい怒鳴ってしまったことで、お母さんはスネモードに突入したらしい。サッサとオートロックを解除してマンションのエレベーターに乗ってしまった。
わたしだって冗談っていうのは分かってる。でもダイチのこと吹っ切れてもいないのに、他の、それも顔も知らない男の人のことで運命だの何だの言われたくない。そもそも非術師相手に恋愛できないのは、お母さんが立証済みだ。
「ちゃん、寒いんだから早く早く」
「…分かってる」
急かされるようにエレベーターへ乗り込むと、お母さんはすでに機嫌が戻ったのか、「お腹空いたねー」なんて言いながら笑ってる。おかげでキツい言い方したことを謝り損ねてしまった。こういう時、お母さんの大らかな性格が羨ましくなる。
「ああ、先に挨拶しとく?」
「あーそうだね。夕飯後じゃ遅くなっちゃうし」
最上階につくと、手前の部屋を通り過ぎる時に挨拶を済ませてしまおうということになった。まずはお母さんがインターフォンを鳴らして声をかける。出てきたのは優しそうなおばあさんだった。引っ越しの挨拶に、とさっき買ったバスグッズを渡すと「あらあら、ご丁寧に。ありがとう」と言って笑顔で受け取ってくれた。
「今後とも宜しくお願いします」
「まあ、可愛らしいお嬢さんねぇ。こちらこそ宜しくね」
さらりと褒めて微笑むおばあさんは、どことなく品がある。きっと裕福な家庭で育ったんだろうなと思った。
「じゃあ、次行こう」
おばあさんに挨拶を終えた後、お母さんが張りきって奥の部屋へと歩いて行く。若い男と聞いたから品定めしてやる気満々なんだろう。でもそうそうお母さんが期待するようなイケメンなんているわけがない。それも都合よく隣に。
「あれ~?留守なのかな」
奥の部屋はインターフォンを鳴らしても誰も応答せず、お母さんはガッカリした顔でわたしを見た。
「仕事から帰ってないんじゃない?まだ午後の7時すぎだし」
「そうねえ。じゃあ、もう少し後で来てみよっか」
お母さんはどこか諦めきれない様子で言った。でもわたしはお母さんほどお隣さんに興味はない。
「…別に今日中じゃなくても――」
「ほら、ちゃん!早く帰ろ。ママ、お腹空いちゃった」
「……(この人は…)」
気持ちの切り替えが早すぎる。サッサと家に戻って行く母親に、わたしは盛大な溜息を吐きながらついて行った。
それからすぐに夕飯の支度――と言っても買ってきたお肉と野菜を並べるだけ―をして、少し遅めの焼肉パーティとなった。ご飯は炊くのが面倒でチンご飯でいいというから、二人分をレンジで温めておく。お母さんは早速買ってきたばかりのビールをグラスに注いで「女だけの生活にカンパーイ」なんて言いながら楽しそうだ。離婚したばかりの女にはとても見えない。わたしは当然飲めないから、ペットボトルのほうじ茶をグラスに注ぐ。
「ちゃん、もっとお肉食べてお肉。呪術師は体力勝負でもあるんだから」
「分かってるけど…そんなに一気に食べられないってば」
焼けた肉からどんどん皿に盛っていくのを見て、苦笑交じりに言ったけど、お母さんには届かない。やっと新居に落ち着いたからなのか、缶ビール数本でほろ酔い気分らしい。そう言えば、酔っ払ったお母さんとふたりで食事をするのは初めてだった。お父さんと仲が良かった頃は、ふたりでよく晩酌してたっけ。
「あまり飲まないでね。明日、お母さんも久しぶりに母校に行くんでしょ」
「分かってるわよ~。はあ~それ考えると緊張しちゃう。きっとわたしの知ってる人は殆どいないんだろうけど」
お母さんはグラスを傾けながら、少しだけ寂しそうだ。呪術師はいわば死と隣り合わせの仕事でもある。だからこそ常に人手不足なんだと教えてもらった。
「ねぇ、ちゃんは本当に良かったの?これで」
黙々と焼肉をやっつけていたら、不意にお母さんが聞いてきた。心の余裕ができたからなのか、やっと娘の心情が気になってきたらしい。
「何を今さら。お母さんはわたしを呪術師にしたかったんでしょーが。わたしもせっかく術式授かったんなら呪術師になりたいと思ったし」
ご飯にタレのたっぷり付いたお肉を乗せて食べるわたしを、お母さんは黙って見つめてる。この期に及んで迷ってるなんて言わないで欲しい。でもお母さんはそんなこと言わなかった。不意に「そっか。そうだよね」と笑いながら、ビールを一口飲むと、頬杖をついて目を瞑る。頬が薄っすら色づいてるから、いい感じに酔いが回ってきたのかもしれない。
「ちゃんは術師の才能が溢れてたからママ嬉しくて、つい無理強いしちゃったかなーと思ってたの」
「…そんなことないよ。誰かがやらなきゃ、呪いで溢れちゃうんでしょ?」
「そうねえ…。結局逃げたところで呪いは生まれてくるし…娘を危険に晒すことになるって分かってても、だからこそ、それに抗う力をつけて欲しかった。パパには理解してもらえなかったけど」
お母さんはやっぱり少し悲しそうな顔で溜息を吐いた。お父さんに言われたことを思い出してるのかもしれない。でもわたしはお母さんの言ってることが間違ってるとは思わなかった。わたしの呪力が強ければ強いほど呪霊は寄ってくるし、呪術師にならなくても危険なことには変わりない。だからこそ、きちんと戦う術を学んで、人を守るだけじゃなく、自分の身を守る力もつけて欲しかったんだと思う。
「だいじょーぶ。わたしが理解してるから」
お茶でご飯を一気に流し込んだ後、きっぱり言うと、お母さんは嬉しそうに微笑んだ。この笑顔を見ていたら、わたしの選択は間違ってなかったと思える。たとえ友達と初めての彼氏を失っても、結局はみんなを守ることに繋がっていく。そう思えるから、寂しいけど、悲しいけど、わたしは明日から呪術師を目指して頑張れる。
「あ~何かふわふわしてきちゃった。久しぶりに気持ちが穏やか~」
お母さんは「もう一本飲んじゃお」と冷蔵庫から缶ビールを出す。こんなに楽しそうなお母さんはわたしも久しぶりに見るから、少しだけ安心した。
「あら、お隣帰ってきたかな」
「え?隣?」
お母さんが玄関の方へ顔を向けるから、わたしも釣られて意識を向ければ、確かに何やら物音がする。それもウチの前を通過したような気配だ。
「ちゃん!チャンスよ。これ持って挨拶してきて」
「は?今?」
お母さんはさっき買ったバスグッズをわたしに押し付けると「早く早く」と腕を引っ張ってくる。こうなると何を言っても聞き入れてくれないのは分かってるから、仕方なく椅子から立ち上がった。とりあえず挨拶をするという過程を終わらせれば気が済むはずだ。
「行くから引っ張んないでよ…ってか…お母さんは?」
玄関に行こうとしてふと振り向けば、わたしを急かした張本人はちゃっかり戻って椅子に座っている。しかも新しく開けたビールをグラスに注ぎ始めて、わたしの目が半分まで細くなった。
「もしかして…わたしだけ行かせようとしてる?」
「だって~ママ、酔っ払っちゃったし…お酒の匂いをさせて挨拶もないじゃない?」
「…ないじゃない?じゃない!だったら明日でもいいじゃん」
「明日はママの実家に顔出さないといけないし何時になるか分かんないじゃない。いいから早く行ってきて」
「はぁ…分かったよ」
これ以上、ゴネても無駄。盛大に溜息を吐いて、仕方なく玄関へ向かう。非術師のお父さんと結婚したせいで、お母さんは親から勘当されてたけど、このたび晴れて(?)離婚をしたと報告したら「孫を連れて帰ってこい」と言われたらしい。だからわたしも初めて祖父母に会うことになっている。術式を持った孫ができて、たいそう喜んでたらしいけど、わたしとしては初めて会うママ以外の呪術師――元だけど――だから、ちょっとだけ怖い。
(なかなかの良家というし、堅物だったら嫌だなァ…)
そんなことを思いながら靴を履いてドアを開ける。お隣さんがどんな人とかも、すでにどうでもよく。ただサッサと挨拶をして焼肉の続きを食べたい。それだけだった。
でも廊下に顔を出した時、ギョッとしたのは、奥の部屋のドアに長身の男がオデコをくっつけて突っ立っていたからだ。とっくに部屋の中に入ってると思ってただけに、かなり驚いた。
「あ、あの~。2003号室の方…ですよね。大丈夫…ですか?」
恐る恐る声をかけると、ドアに凭れていた男がゆっくりとこっちを見た。そこでまたしてもギョっとした。その男は夜なのにも関わらず、ラウンド型の黒いサングラスをかけ、あげく全身黒づくめ。髪は何故か真っ白で、若いのか若くないのかも分からない。ただ、やたらと身長があるせいか、威圧感がハンパない。男はわたしに気づくと、ドアからゆっくり離れて何かを呟いた。
「…あー…悪いけど…み…」
「え…?」
不意に口を開いたかと思えば、聞き取れないほどの声でボソボソ話す男を見て、一瞬危ない人だったらどうしよう、なんて不安が過ぎったけど、声をかけてしまった手前、家に逃げ帰るというのも何か違う気がした。とりあえず挨拶を済ませてしまおう。
「え、えっと…わたし、隣の2002号室に引っ越してきたと言います。これ、つまらない物ですけど良かったら…」
一気にそこまで言って、バスグッズの入った箱をずいっと差し出す。ここで普通なら「どうも」とか言いながら、相手が受け取って終わるはずだ。でも男は受け取るでもなく、ふらふら歩いてくると、何故か箱を持つ私の手首をガシっと掴んできた。その恐怖で体が一瞬フリーズする。
「じゃなくて…み、みず…」
「は…?水?」
やっと聞き取れたかと思えば、よく分からないことを呟く男は、どこか顔色が悪いように見えた。でも手首を掴まれたままの恐怖は消えず、必死に引き離そうと藻掻く。
「あ、あの放して下さいっ。大声出しますよっ」
知らない相手に触れられてるという不快感もあり、ついキツい口調になってしまった、その時。不意に男の手から力が抜けて、するりと離れる。かと思えば――。
「え、ちょ、ちょっと!待っ…」
男は凭れ掛かるように倒れてきて、わたしに抱き着く形になった。と同時に、その重さに耐えかねたわたしの体が後ろへ傾き、そのまま尻もちをつく。
「…痛っ!!」
男の全体重を受けたわたしのお尻が悲鳴を上げるように、思わず叫ぶと、お母さんが慌てたように飛びだして来た。
「な…何してるの?ちゃん!」
お母さんは男の下敷きになってるわたしを見て酔いが吹っ飛んだらしい。何とかわたしを引っ張り起こすと「どういう状況よ、これ」とオロオロし始めた。
「そんなのこっちが聞きたい…この男が急に…」
とお尻を擦りつつ、足元を見る。だけど男は未だに床の上で倒れたままだった。
「え…死んでる?」
お母さんが青い顔で呟く。
「ま、まさか…」
「え、ちゃんがやったの?」
「ちょっと!誤解されるような言い方やめてよ!コイツが勝手に倒れたんだってば」
「そうなの?え、ど、どうすればいい?このまま放っておくのもマズいとママは思うんだけど…」
「そ、それは…」
確かに言われてみればそうだ。引っ越したばかりの新居の前で死なれても後味が悪すぎる。っていうか、この人いったい何なんだ。
「きゅ、救急車…よね。こういう時は」
「そ…そう、だね。救急車…呼ぼう」
わたしもお母さんも相当動揺してたらしい。こういう場面で一番にしなきゃいけないことを思い出す。
かくして、東京一日目の夜、派手にサイレンを鳴らす救急車が、新居のマンションを騒がす羽目になった。