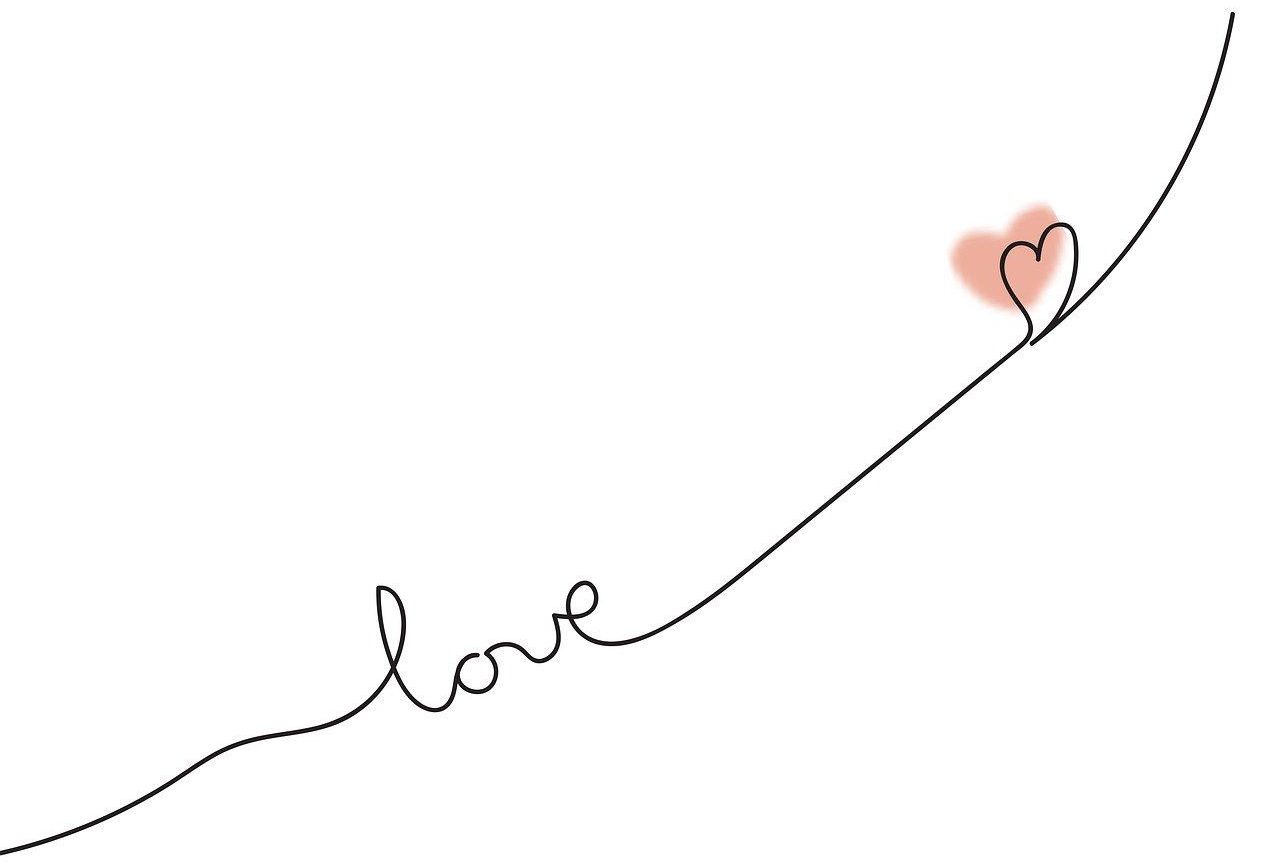君と私のビオトープ-04
呪術高等専門学校は、予想以上に広かった。全てが和の世界で彩られ、歴史を感じる空間の数々は、少なからずわたしを緊張させた。そして現在、対面してるわたしの担当教師の顔が、地味に怖い。ついでに圧が凄い。いかついサングラスをして生徒と面談する教師なんて初めて見た。いや、教師というより、もはや「ヤ」のつく世界の住人なのでは。
変わった家庭環境で育てられたと思ってたけど、今までは一応、普通の学生生活なんてものを送ってたせいか、まだ呪術界のノリ(?)についていけてない感が凄い。わたしの中の常識が色んな意味で崩壊していく。
「君が小百合くんの娘さんか。話はお母さんから聞いてる。来年、君の担当教師になる夜蛾正道だ」
古いけど趣のある校舎の上階、応接室。最初に面談してたお母さんと入れ替わる形で通され、開口一番、そう言われた。
"小百合"とはお母さんのことだけど、この夜蛾先生が高専を卒業する頃にお母さんが入学したから、今日までお互い面識はなかったという。でも近い後輩の中退話は夜蛾先生の耳にも届いていたようで、「才能があると聞いてたから残念に思ってた」と言われた。
「は…初めまして…です」
圧の凄い夜蛾先生のおかげで、緊張が解れるどころか増す一方、どうにか自己紹介を終え、面接と言う名の雑談的なものに入った。どうして呪術師になりたいのか、と聞かれたから、つい「自分の為です」と即答してしまったけど、夜蛾先生は怒るでもなく、薄っすら笑みを浮かべてる。やっぱちょっと怖い。
「何故、呪術師になることが自分の為だと思う?」
また質問された。何だろう。これは試されてる?
何故、呪術師になるのか。そんなの持ってる側だから、としか今は言いようがないけど、何故、自分の為になるのか。だって、それは――。
「…持って生まれた側にしか出来ないことをするのは…わたしの生きる証だと思ってるからです」
これまで明確な理由なんてないと思ってたけど、漠然とした思いを言葉にするとそんな感じだった。夜蛾先生は黙ってわたしを見たまま。サングラスのせいで表情も分かりにくい。でも、不意に口元が僅かながら緩んだ気がした。
「ほう…自分が死ぬかもしれない任務に就く理由がそんなものでいいのか?」
呪術師はいつでも死と隣り合わせ。それはお母さんから何度も聞かされてきた。ハッキリ言って耳タコ状態だ。
「…自分が死ぬかもしれない戦いに身を置いたとしても、それはわたしが選んだ未来の中で起きたことです。その結果、もしかしたら巡り巡って誰かを救う可能性もあるし、どんな結末を迎えてもそれがわたしの生きた証になります。逆に持ってる側なのに何もしない方がわたしは怖いので」
「怖い…?」
「はい…。あ、でも別に人様を救おう、なんて崇高な理念があるわけじゃなくて…。もし自分に出来ることを何一つしなくて、何か取り返しのつかない事態が起きた時、わたしはわたしを許せなくなると思うから…それってキツいですよね。わたし、まだ16なんで。あ、来年の春には17になりますけど…自分を嫌ったまま未来を生きてくなんて、想像しただけで地獄というか…」
そう、結局は自分の為というのが一番の答えで、もし仮に呪い殺されることがあったとしても、自分で選んだ道なんだから仕方ない、とは思う。出来れば死にたくないし、口が裂けても「任務なので死んでも後悔しません」とは言えないから、呪術師の気構えとしてはどうなんだと思うけど。
わたしが話してる間、夜蛾先生は黙って聞いていた。あまりに何も言わないから怒ってるのかと心配になってくる。だけど、一分は過ぎようかという時、夜蛾先生は突然「ぶははははっ」と笑い出した。だから怖いってば。
「なるほど…自分を嫌いになりたくない、か。16歳らしい理由だ」
「は、はあ。あの…すみません。そんな理由で」
「いや、普通にイカレててホっとした」
「……え」
イカレてる、とあまりに自然にディスられたから、腹が立つより前に呆気にとられてしまった。きっとそんな思いが顔に出てたんだろう。夜蛾先生はいかつい顔ににんまりとした笑みを浮かべた。
「ん?何だ。不満か?死ぬことより、自分を嫌いになりたくないなんて、しっかりイカレてるだろう」
「そ、そう…なんですか?」
「その歳で人様の為だと言われた方が嘘くさい。まあ、まだ迷いがあるのか明確なものが見えてない気もするし、若さゆえの可愛い理由だがな。――お前は合格だ」
「え、合格…って…」
もう入学は決まったものじゃないのか?と首を傾げたくなったけど、夜蛾先生は「気にするな。これはオレなりのテストだ」と豪快に笑った。何でも次期学長候補らしく、自分が学長になった際は、入学する生徒の心構えを合否の決定に加えたいと思ってるらしい。勝手に人をテストに使うなと思ったけど、もちろん怖くて言えなかった。
「まあ本格的な入学は年明けだが、君が望むなら年内から授業に参加しても構わない。来年、同級生になる今の一年と少しでも交流して関係を深めておくのもいいだろうし、ちょうど今、オレの教え子に一年の教育実習をさせてる最中だから融通もきく。の好きにしていい」
「はあ…(すでに名前呼び…)」
「ああ、それと…家が近いから寮ではなく、しばらくの間は自宅から通うと学長から聞いたが…それでいいのか?近いと言っても、駅前だろう?高専までは歩いて30分はかかる」
夜蛾先生が書類に目を通しながら訊いてきた。この高専には敷地内に学生用の寮があるらしく、例外を除き、殆どの教師や生徒は家が遠いという理由で、寮住まいをしてるとのことだった。わたしも例外のひとりになりそうだ。
「大丈夫です。その分、早起きするので」
「そうか。まあ、それならいいが…もし遅刻しても言い訳にはできんからな?」
「分かってます。それに母の方が落ち着いたら寮に入るかもしれないし…」
「…そうか。分かった」
夜蛾先生は事情を知ってるのか、それ以上何も言うことはなかった。
わたしが寮に入ることを躊躇ったのは、もちろんお母さんが原因だ。本人は近いんだし一人でも平気だと言ってたけど、やっぱり離婚したばかりの母親をいきなり一人暮らしさせるのは心配だった。今後どうするかはまだ聞いてないけど、術師に戻るにしろ、他の仕事を探すにしろ、そういう先のことが落ち着いてくるまではそばにいようと思った。そもそも呪術師を辞めて結婚したお母さんは、長いこと専業主婦をしてたから、普通の仕事に就いたことがない。元々お嬢さまということで、世間一般の常識があるかも疑わしい。
(…まずは今日おじいちゃんに会って、この先のことを決めるって言ってたけど…どうなることやら)
面接を終えて応接室を出ると、廊下で待っていたお母さんが笑顔で手を振ってきた。久しぶりの母校は落ち着くのか、帰る際も「懐かしい!」を連呼しながら、自分の青春時代を楽し気に語ってる。最近のお母さんはいつも元気がなく、お父さんとケンカばかりしてたから、青春を思い出すことで消耗した心が潤うなら、娘としても安心だ。
「じゃあ早く帰って、ママの実家に行こうか」
「そうだね」
「ママのお父さん、首を長くして待ってるみたいだし、久々にお洒落しなきゃ。も可愛い恰好してよね」
「…はいはい」
わたしより女らしいお母さんに呆れつつ、初めて会うお母さんの両親を思うと、怖い反面、やっぱりどこか楽しみだった。
2.
初めて行ったお母さんの実家は、都内の一等地にある大きなお屋敷だった。あんな家、ドラマでしか見たことがない。
「…そ、想像以上だった…」
「えー?何か言った?」
夜の7時を過ぎた頃、やっと我が家に帰宅。祖父母に持たされたお土産の数々を放り出して、わたしはベッドへ倒れ込んだ。気を遣いすぎて心身共に疲れはてたのが原因だ。
「何よ~もう寝るの?夕飯は?」
帰って早々、部屋に引っ込んだら、すぐにお母さんが顔を出した。
「…食べるけど」
「じゃあほら、おばあちゃんに霜降り和牛もらったんだし、今夜はすき焼きにしない?」
「…そうだった!」
ベッドに寝転んだ時はもう起き上がれないと思うくらい脱力してたくせに、霜降り和牛と聞いてガバリと起き上がるわたしは、かなりゲンキンだと思う。でもそれくらい魅惑的なお肉をお土産にくれるなんんて、さすがはお金持ちのおばあちゃんだ。呪術師って儲かるんだと改めて驚いた。
お肉以外にもアレコレと高級そうなお菓子を筆頭に、洋服やアクセサリー、帰り際にはお小遣いまでもらえたんだから孫冥利に尽きる。これまで会えてなかった分、思い切り可愛がりたいそうだ。よく孫は目に入れても痛くないとか聞くけど、まさにそんな感じだった。孫としての自分なんて初体験だったけど、控えめに言って…最高かもしれない。
「でもアレだね。お母さんはおばあちゃん似だ」
「え~そーお?」
簡単に部屋着に着替えてからリビングに行くと、お母さんが早速木箱に入ったお肉を広げていた。安いものでも一箱5万は下らないという霜降り和牛を5箱もくれたんだから恐れ入る。お母さんは想像通り、筋金入りのお嬢様だったということだ。
「そうだよ。おばあちゃんって呼ぶの気が引けるくらい綺麗だったし、見た目も若い。おじいちゃんも渋くて男前だったし着流し似合いすぎ」
「でもちゃんだってその血は引いてるわけだし、ふたりとも"可愛い可愛い"ってデレデレだったじゃない」
「あんなの…初めて会う孫にリップサービスしてくれただけでしょ」
「また、そんな捻くれたこと言っちゃって」
お母さんは笑いながら「ちゃんは可愛いわよ。ママの子だもの」と、どこか自慢げに言った。そんな恥ずかしい台詞を素で言えるのはある意味凄いし、こっちが照れてしまう。
「でも…やっぱり、このマンションもおじいちゃんが用意してくれてたんだね」
「そうよー。だって離婚の理由はママの我がままだし、パパから慰謝料なんてもらえないじゃない。仕事もしてなかったからママはお金ないし、だからおじいちゃんに連絡したの」
あっさり認めたお母さんは手際よくテーブルに鍋や小皿を置いて、ついでに冷蔵庫から卵を出す。そんな姿を見てると、あんなお屋敷に住んでたお母さんが、よく専業主婦なんかできてたな、と苦笑が漏れた。まあ、料理はわたしより下手だけど、お手伝いさんのいるあの家で育ったんなら、納得だ。座ってるだけで次々に豪勢なお料理が出てくるんだから。
「ほんとは怒鳴られるかと思ってたんだけどね。二人の反対を押し切って家を出たわけだし…」
小皿に卵を割りながら、ふとお母さんが呟いた。これでも気にしてたらしい。
「ちゃんのおじいちゃんね、ああ見えて呪術師ファーストな人だから、挨拶に来た時はそりゃもうパパなんか、けちょんけちょんに怒鳴られてたなぁ」
「へえ…そうだったんだ。確かに強そうなオーラはビンビン感じたけど」
おじいちゃんを思い出すと、今でも現役いけるんじゃないかと思ってしまう。それくらい強い呪力を感じた。
「あ~いい匂い」
お母さんがすき焼き用のタレを温めた鍋に入れると、途端に甘い香りがわたしの鼻腔を刺激してくる。ついでにお腹が鳴ってしまった。おじいちゃんちで散々美味しいランチを食べてきたはずなのに、夜にはシッカリお腹が空くんだから不思議すぎる。
「でも、5箱はさすがに多いよね。ふたりで食べきれるかな」
「何言ってんの。ちゃんは若いんだから、これくらい食べられるってば」
「太りそう…。あ、余ったら隣のおばあちゃんにおすそ分けする?」
お母さんの代わりにキッチンへ立って、ネギや豆腐を切りながら、ふと隣人の老夫婦を思い出す。最初に挨拶に行った時も好印象だったし、それもいいかなと思ったのだ。
「そうねえ。それでもいいけど…」
と、お母さんは早速ビールを開けながら、ふと黙り込んだ。
「何?やっぱ自分で食べたいの?じゃあ冷凍して後日焼肉にする?」
「そうじゃなくて…」
「じゃあ何よ」
切った野菜や豆腐をお皿に盛りつけ、テーブルに置くと、お母さんは何とも言えない表情でわたしを見上げてきた。
「お隣で思い出したけど…あの人、大丈夫だったかしら」
「あの人…?」
わたしも椅子に座って、早速野菜を鍋に投入していく。すき焼き独特の香りが、余計に空腹を刺激してきた。
「だから…あの人よ。奥の方の隣人」
「……ああ」
お母さんが身を乗り出し、声を潜めながら右側の壁を見る。そこで黒づくめのサングラス男を思い出した。引っ越しの挨拶をしようと声をかけたら、勝手にぶっ倒れて、焦ったお母さんが慌てて救急車を呼んだことも。
「もう…ちゃんってば忘れてたの?ママなんか心配で心配で…さっきも部屋が真っ暗だったみたいだし、あの後どうなったのか気になっちゃって」
「そんなに気になるなら、あの時ついて行けば良かったのに」
「だって知らない人だし…ただの隣人が救急車に同乗するのもおかしいじゃない」
「そうだけど…もうお肉できてるよ。食べてい?」
ぐつぐつと煮えてきたのを確認して、お肉に箸を伸ばす。そんなわたしを呆れたように見ながら、お母さんは溜息を吐いた。
「若いっていいわねえ…。細かいことなんて気にしないでいられるんだから」
「そんなこと言われても…知らない人だし…何か怖かったし…」
昨夜のことを思い出すと、それくらいしか思い浮かばない。そもそも体調悪いなら倒れるまで放置せず、自分で病院に行けば良かったのに。
「冷たいわねえ…もし死んでたらどうするのよ」
「死…って…変なこと言わないでよ。そりゃ…何か凄く顔色悪かった…けど…」
柔らかい極上の霜降り和牛を口に運びながら、あの時の男の様子が頭に浮かんだ。顔はあまり見えなかったけど、廊下の明かりの下で見た感じ、真っ青だったように思う。
「そうでしょ?意識なかったみたいだし…昨日の夜に病院運ばれてったのに、まだ帰ってないのも何か怖いじゃない…あの人と最後に会ったのがママとちゃんなんてことも…」
「だから変な想像するのやめてってば…」
「だってママ、最近まで運悪かったし…最悪、引っ越し早々お隣でお葬式なんてこともあると思うのよ…」
お母さんは何気に怖いことを言いつつ、深い溜息を吐くもんだから、思わず持ってた箸をバンっとテーブルに置いた。悪い想像はしすぎると現実になると聞く。まあ、それが呪いの仕業の時もあるから何とも言えないけど、お母さんは地味にネガティブな一面があるから、ここら辺で止めておかないと、せっかくの豪華な夕飯が台なしになってしまう。確かにお隣さんも心配だけど、今はお肉の方が大事なのだ。
「もう…この話はやめ。せっかくのお肉がマズくなる――」
ダメ押しとばかりにそう言いかけた時だった。不意にインターフォンの音が室内になり響き、わたしとお母さんはビクリと肩を揺らした。
現在午後8時。こんな時間に尋ねてくる人は誰もいない。この町に知り合いがいないんだから当然だ。それに――。
「…下のインターフォンの音じゃ…なかったね」
「え…そ…そ…葬儀屋…?隣に遺族が来てるとか…」
一拍置いて、またしてもお母さんが怖いことを呟いた。何が何でも隣人を殺したいらしい。でもわたしにもお母さんのネガティブが伝染したのか、あまりのタイミングに少しだけ怖いことを想像してしまった。いや、曲がりなりにもこれから呪術師になろうというわたしが、幽霊なんじゃ、と思うだけでアウトな気がする。でも、やっぱ怖い。
「お、お母さん、出てよ…――」
「えー…ちゃんが出てよ…っママ怖くて無理!」
「え、ズルい!わたしだってやだ――」
と母娘でモメ始めた時、再びインターフォンの音が響く。お母さんはすっかり怯えた顔で、実家から持ってきたという過去に愛用してた猫型クッションを抱きしめながら、いやいやというように首を振った。こうなると娘のわたしが引くしか術がない。
「…ほら、早く…待たせちゃ悪いじゃない。葬儀屋さん」
「……」
お母さんの中で、お隣さんはすでに死んだことになってる。実際、あの人に何が起きたのかも分からないのに、思い込みが激しいのは昔からだ。
「もー…分かったよ」
お肉の煮える美味しそうな匂いに後ろ髪を引かれつつ、わたしは溜息交じりで立ち上がった。だいたい、仮にお隣さんが死んでたとして、葬儀屋がウチに来るはずないのに。少し冷静になって考えたら分かることだ。でも、まあ、そうなると突然の訪問者は誰かってことになるけど――。
「はい。どちら様ー?」
声をかけながらドアを開ける。同時にドアスコープで確認すれば良かったかも、という思いが過ぎったけど、もう遅い。
「あ…どーも。こんばんはー」
ドアの向こうに立っていたのは、お母さんが想像してるような葬儀屋でも、隣人の遺族でもなかった。全身黒づくめではあるけど、喪服には見えない。
「…あ!」
思わず声が出た。目の前に立っているのが、死んだことにされてる張本人だったからだ。白髪の長身に、何故か夜なのに真っ黒なサングラス。間違いなく、昨日ぶっ倒れた人だ。
「え、大丈夫だったんですか――?」
「ちょっと…ちゃん…!呑気に話しかけてるけど…ちゃんと足ある?もろもろ透けてない?」
「「………」」
わたしの言葉を聞いて察したのか、奥からお母さんのアホ丸出しな問いが聞こえてきた。念のため、彼の足元を見たけど、長い足を強調するようにしっかりと立っている。幽霊じゃないっぽい。っていうか、この人、マジで足ながっ。
ポカンとした顔で目の前の男の人を見上げると、彼は徐にかけていたサングラスを指で下げた。
「昨日、何かお世話になったみたいで…どーもすみませんでした」
「い、いえ…お元気そうで何より…」
と、そこまで言って言葉が途切れた。昨日は怖いと感じた彼の素顔が、あまりにぶっ飛んでいたからだ。
(な、何、この人!めちゃくちゃイケメンだ…!しかも目が青いんですけどっ?)
180以上はありそうな長身の上に、顔面偏差値が高すぎるご尊顔。生まれて初めて見るといっても大げさじゃないほど綺麗な顔立ちで、わたしは文字通り言葉を失った。そんなわたしに微笑みながら、彼は夕べの事情を説明しだした。
「いや~僕、下戸なのに昨日はジュースと間違えて酒を一気飲みしちゃって。フラフラで何とか家まで辿り着いたはいいけど、急に気持ち悪くなって…その辺はあんまり覚えてないんだけど、今朝気づいたら病院だし、何か一晩がっつり点滴打ってもらってたからすっかり元気に…」
と、一気に話しまくってた彼は、急にトーンダウンしたかと思えば「いい匂い…」と眉尻を下げて呟いた。同時にお腹の虫がぐぅぅっと鳴る音。
思わず吹き出したのは、照れ臭そうに鼻の頭をかく彼が、お腹を空かせた子犬のように見えたからかもしれない。