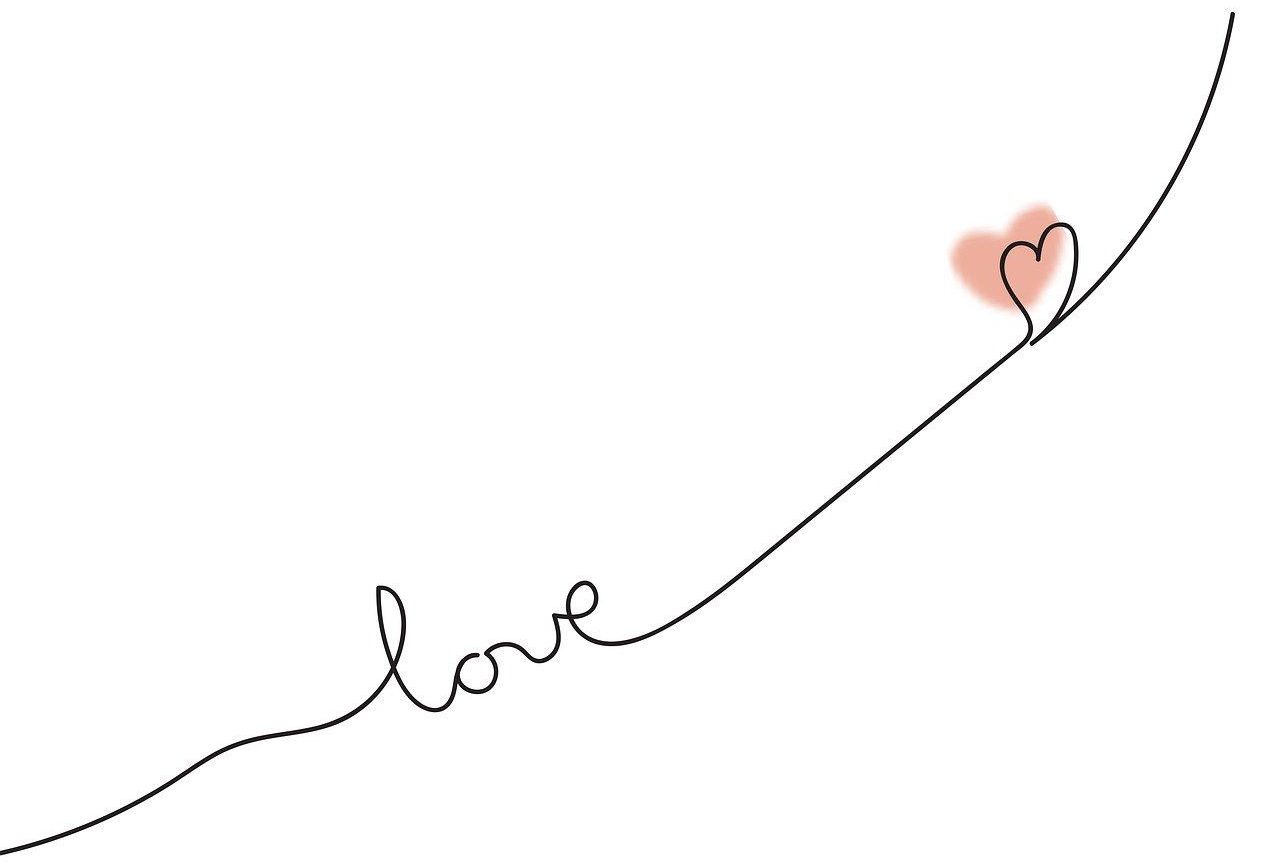君と私のビオトープ-05
「いや~すみませんねー。何か催促したみたいになっちゃって~」
「どーぞ、どーぞ。うちは娘だけだし、二人でお鍋ってのも寂しいでしょう?お肉もこんなにあるから食べきれないと思ってたのよ~」
「これ、めちゃくちゃうまそ~なお肉ですねーお母さん」
「……(お母さん?)」
初対面の二人はそんな会話を繰り広げつつ、お母さんは見知らぬ隣人に霜降り和牛を取ってあげるというサービスまでしている。っていうか、普通知らない男を夕飯に招くか?という疑問や怒りが、まるで炭酸ガスのようにポコポコと下腹からこみ上げてくる。いや、別にオナラがしたいわけじゃないけども。
(まあ…さっきはちょっと可愛い…なんて思っちゃったけど)
綺麗な顔が情けなく見えるほどに眉を下げた隣人さんは、夕べから何も食べてなかったらしい。すき焼きの匂いに触発されたのか、ぐぅぐぅと鳴りやまない腹の虫に苦笑しながら、彼は「お腹が空きすぎて死にそう…」と呟いた。まあ急性アルコール中毒?という症状で丸一日点滴打たれてたなら納得だ。詳しく聞いたところ、昨夜は後輩くんと久しぶりに食事に行き、その後にバーへ移動。下戸のくせに何でそんな場所、と思ったけど、そういう場や空気は好きらしい。でもそこで後輩くんが頼んでたカラフルなカクテルを、自分のノンアルドリンクと間違え、一気飲み。ノンアルカクテルとはいえ、見た目が本物と違いはなく、ついでに後輩くんの飲んでたカクテルと同じ色合いだったために何の疑いもなく飲んでしまったようだ。
下戸の人が度数の強いカクテルを飲めば、そりゃぶっ倒れるよな、と納得はしたものの、その後にお母さんがしゃしゃってきたのは誤算だった。
「まあ、お腹空いてるの?それならちょうど夕飯とるとこだから一緒にどうぞ」
最初は彼が死んでるだの何だのと散々ビビってたくせに、本人が登場、それもとびきりのイケメンだったからって、その変わり身の早さにはマジで脱帽する。
この男も男だ。いくら点滴で良くなったからって、退院してきたその足で人様んちの夕飯に呼ばれるとか、どういう神経してんだろう。
「…ん?僕の顔に何かついてる?」
ジトっと見てたら不意に目が合った。というか、この男は家の中でもサングラスを外さないから合った気がしただけだ。
「別に…それより大丈夫なんですか?急にお肉なんて消化に悪いもの食べて。夕べは真っ青で死んでるのかなって思うくらい具合悪そうだったのに」
「ああ、それが全く。まあオデコぶつけたのか、ちょっと腫れてるけど」
「…オデコ。ああ…前のめりに倒れてきたからぶつけたのかも」
ふとその時のことを思い出した。この人がわたしに向かって倒れてきて、それを支えきれなかったことで、したかかお尻を打ったんだった。ついでにお母さんに引っ張り起こされた時、意識のなかった彼はそのまま重力に逆らうことなく、地面に直撃してたのを思い出す。そう説明したら「え、マジ?」と酷く驚いてた。
「すみません。あの状況でわたしが動いたらどういう結果になるか考えてなかったお母さんのせいです」
「え~…何よ、ちゃん、その言い方~」
「だってホントのことでしょ?」
つかさず口を挟んできたお母さんに言い返すと、隣人の彼は愉しげに笑った。良かった。怪我させてしまったことを怒ってるわけではないらしい。まあ、あれも不可抗力だから仕方ないし、元々は彼のドジが原因だから怒られても困るんだけど。
「ちゃん?」
ブツブツ言ってるお母さんをスルーしてお肉を食べていると、彼が笑みを浮かべながらわたしの名を呼んだ。名乗った覚えはないから、お母さんがそう呼んだのをキャッチしたんだろう。彼の微笑みにちょっとだけドキっとしたのは、やっぱり、いつの世も女子はイケメンに弱いということかもしれない。
「可愛い名前だね」
「そ…」
「そうでしょう?生まれてきたこの子を見た時に、この名前だってピンときたって主人が言うから」
"そんなことない"と言おうとしたのに、それを押しのけるようにお母さんが割り込んできた。何かイラっとしたのは、あの人のことを未だに"主人"と呼ぶせいだ。わたしの力を全否定するあの人と散々ケンカしてたくせに、まだ好きなのかなと疑いたくなる。
「もうホントに可愛いがって、あちこちで"が生まれたー"って大騒ぎ。もう私も笑っちゃって――」
「やめてよ、そんな話聞きたくないっ」
気づけば怒鳴っていた。名前を付けてくれたとか、凄く可愛がってたなんて、そんな話を今更したって意味がない。あの人はわたしの父親であることを、拒否したのに――。
「え……ちゃん…?」
今日までギリギリで耐えていたものがプツリと切れたみたいに、涙がポロポロと零れ落ちていくのが分かった。二人が別れを決めた時も、学校を転校すると決まった時も、ダイチに振られた時でさえ、泣かなかったのに。
何で今なのか全然わからない。なのに、一度溢れたものは簡単に止まってくれなくて、隣にいるお母さんがオロオロする姿に、また泣けてきた。
「どうしたの…?何か気に障ったならごめんってば…」
戸惑いながらわたしの肩を抱くお母さんの手は、かすかに震えていて、動揺してるのが伝わってくる。わたしはいつも元気だったから、こんな風に泣くなんて思わなかったんだろう。
でもね、わたしだって、本当は素直に泣きたかった。お母さんとお父さんの前で、親友の前で、ダイチの前で、ちゃんと泣けたら良かったのに。
――ママと東京に行こう。
――えっ転校しちゃうの?!
――ごめん…。オレ、無理だわ…
ぐちゃぐちゃの頭の中に、浮かんでは消えるこれまでの光景が、きっと、その一つ一つが、凄く悲しかったんだと教えてくれた。
「…ちゃ…」
お母さんがもう一度何か言いかけた時、今まで黙っていた隣人が、唐突に椅子から立ち上がった。それも当然かもしれない。初対面の人間が、我が家の複雑な事情を見せられて、呑気にすき焼きなんて食べられるはずがない。案の定、白髪サングラスのイケメンは「じゃあ…僕はこの辺で――」と言いかけた。きっと今すぐ帰りたいに違いない。当たり前だ。こんな空気に耐えられる他人はそうそういない。だけど、その後の展開は、わたしの予想の斜め上をいくものだった。
「待って…!その…まだお肉もあるし…」
泣き出した娘と二人きりにされるのは相当気まずかったらしい。まずはお母さんが隣人さんを引き留めた。
「え、いや、でも」
「いーえ!いいの!食べてって!悪いのは私なんだから――」
と叫んだお母さんは、何を思ったのかわたしを見ると「ママが出ていくから!」と徐に立ち上がり、ソファに引っ掛けてあったコートを羽織った。驚きすぎて目が点だ。娘のわたしでもそうなんだから、白髪イケメンなんて更にハニワみたいになってる。これはさすがに泣いてる場合じゃない。
「え、ちょ、ちょっと待って、お母さ――」
「いいから二人で食べててちょうだい!ちょうど卵も切れそうだから買って来たいの!じゃあね、行ってきます!!」
そう叫ぶと、お母さんは閃光の如き速さで、玄関から飛び出して行った。いや、卵は売るほどあるじゃない。
テーブルの上に卵が沢山入ったお皿を見下ろし唖然とする。その時、固まっていた隣人さんがボソリと呟いた。
「マジか…あの人」
驚きすぎて思い切り素がでたらしい。その言い方が、今、わたしが脳内で思ったことと重なって、思わず吹き出してしまった。その瞬間、彼は「うわ、嘘泣き?」とわたしの顔を覗き込んでくる。そんなわけないじゃん、と返しながらも、ツボに入った笑いは止まらない。不思議なとこが多々あるなとは思ってたけど、お母さんはやっぱりお母さんだった。あんなに泣いてた女が笑い転げるさまに、目を極細にした隣人さんは「そーいうの、さっき泣いたカラスがもう笑うって言うんだよな~」と、急にさっきまでのしおらしい態度が一転。ラージサイズくらいにデカくなった。お母さんの前で猫かぶってたな?
「ったく…変なママだよね~君のママは」
さっきまでちゃんと座ってたくせに、今じゃ大股開いて椅子に寄り掛かりながら、天井を仰ぐ隣人さんは、どこの不良だと突っ込みたくなる。サングラスも相まって、少しガラの悪いイケメンだ。でも、お母さんに対する感想は激しく同意する。
「…それは否定しない」
「はは、そーなんだ。いつもあんな感じ?」
「…まあ。お母さんがあんなだから、わたしは子供のままじゃいられないこと多くて」
つい本音がポロリと出てしまった。知らない人にこんな愚痴を言ったところで仕方ないのに。
隣人さんは「聞いた風なことを…」と苦笑いを浮かべた。何かちょっと偉そうでムカつく。
「お兄さん、いくつなの?」
「あーもうすぐ22になる」
「ふーん…意外といってるね」
「あ?どこがだよ」
「16歳から見れば、ハタチ過ぎなんておじさんの域だよ」
「…チッ。クソガキに言われたくねぇわ」
途端に口が悪くなった隣人さんに驚いたけど、きっとこれがこの人の素顔なんだろうなと思った。言い方が何か板についてるし、どう見ても今が自然体っぽい。
彼は手持無沙汰なのか、ゆらゆらと椅子を後ろへ倒しながら、深い溜息を吐いた。
「何で泣いたんだよ」
「……別に関係ないでしょ」
「あ~あれか。親の離婚で急に引っ越すことになって、彼氏と離れ離れ~とか?」
「……泣くぞ」
「……スミマセン」
憎たらしいほど図星をさされ、ジト目を向けたら意外にも素直に謝ってきた。大人なのか子供なのか、よく分からない人だ。
「ってか…マジで別れたのかよ」
「まあ…ちょっと距離に負けたっていうか…やっぱり東京は北海道の人からすれば遠い遠い街なんだよ」
「北海道?のどこ?」
「札幌」
「へえ…いい街じゃん。僕も仕事でたまに行くけど」
「そうなんだ」
「ジャガバター好きでさー。わざわざ買いに行くよね、大通公園に」
「あ、あそこの美味しいよね、確かに」
…って、何を呑気に話してるんだ、わたしは。一瞬、会ったばかりの人だと忘れて、つい余計なことまで話してる気がする。すると僅かな沈黙の後で、隣人さんが苦笑いを零した。
「でもさぁ、何もブラジルほど遠いってわけじゃあるまいし、好き同士が別れる理由にはならないでしょ」
「……それは」
「なーんてね、僕も遠距離とか全然ダメ~無理だわ」
「…(ムカッ)」
不意に隣人さんが「無理」とか言うから、よく分からない怒りがこみ上げてきた。わたしは離れても付き合っていけると思った。なのに男ってやつは四六時中、そばにいないとダメらしい。この隣人さんがそうみたいに、ダイチもきっと同じように「無理」だと思ったのかな。そんな想像をしてたら、ついムキになってしまった。
「何でダメなの…?さっき自分で言ったんでしょ。ブラジルほど遠いわけじゃないって」
「何キレてんだよ。ってか、一緒にいてもダメになることだってあるんだし、一概に言えなくない?男女の仲なんて。なのにずっと会えない状態で上手くいくとは思えない」
「……単純な頭でいいね」
正論を言われて何も返せない腹立たしさから、そんな悪態をついてしまった。これじゃただの子供の癇癪だ。隣人さんは少しムっとしたように目を細めたのが気配で分かった。
「誰かさんのせいでオデコ打ったしな…脳みそ揺れたかもなー」
「う…」
サングラスをズラしてジト目を向けられ、わたしは言葉に詰まってしまった。でもあれは…お母さんが悪い。
「大人のクセに…スネないでよ。あ、ガキなのかな?」
「…わーるかったな、ガキで。僕も久しぶりだよ、昔の自分に戻るのは」
「え…昔って――」
と顔を上げた時、隣人さんは不意に「か~えろ」と言って立ち上がった。
「ご馳走様~。ママに宜しく言っておいて」
「あっそ…」
サッサと帰れと思いながらそっぽを向く。これまた子供っぽい気がしたけど、何か腹が立って仕方がない。かすかにコートを羽織るような音と、玄関の方へ歩いて行く気配。ほんとに帰るんだ。そう感じた時、この大量に投入されたお肉をどうしよう、と考える。
でも一向にドアの開く音がしないから、恐る恐る顔を戻すと、彼は玄関口に立ってジっとわたしを見ていた。しかも、わざわざサングラスをズラして。
「な…何?」
「いや…さっきから思ってたんだけどさ。いいもん持ってるよ、ちゃん」
「は…?」
突然何を言いだすのかと驚いた。何がいいもん?と一瞬首を捻ったけど、すぐにハッとして息を呑む。男が女に「いいもん持ってる」という下りは、前に親友とこっそり読んだエロ漫画にも出てきた気がする。
そこに気づいた時、わたしは自分の体を抱きしめるようにしながら彼を睨んだ。女子高生の体を品定めするなんて許せない。そう怒鳴ろうかと思った瞬間、ぶはっと盛大に吹き出され、呆気にとられる。
「いや、そのお子ちゃま体型のことじゃなくてね」
「だ、誰がお子ちゃま体型よ!見たことないクセに!」
「んー…見せてもらうのはマズいでしょ。そこはやっぱり」
「…ハァ?」
ニヤリと笑う彼の言葉に呆れてしまう。というか、この人は女子高生の裸なんか絶対キョーミなさそう。中身はムカつくけど、あの外見だ。いわゆる"いい女"には困ってないはず。
その時、出ていこうとした足を止めて、彼は再び振り向いた。
「そう言えば…夕べ、僕に何かくれようとしてなかったっけ」
「あー…」
何だ、覚えてたんだ。絶対覚えてないと思ったから自分で使おうと思ってたのに。でもまあ、自分の分も買ってあるし、ここは仕方ない、とばかりに、昨日渡し損ねたバスグッズを出して「今後とも宜しくです」と突き出す。彼は「あ~引っ越しの挨拶ね。なるほどなるほど」と笑顔で受け取った。
「今時、こういう物を配るんだ。へえ~律儀だね。都会のマンション住まいだと、意外に隣人同士でも挨拶しないことの方が多いのに」
「すみませんね。田舎育ちで」
「いや、そんなことは言ってないじゃん。札幌は田舎じゃないし」
そう言って肩を竦めた彼は、最後に「ありがたく使わせてもらうよ」と微笑んで、今度こそ帰って行った。今時のイケメンはバスグッズで釣れるらしい。あの憎たらしい性格を考えれば「いらね~」くらいは言われると思ったのに。案外いい人…なのか?
…とは言え、人のことお子ちゃま体型と言ったことは忘れてない。
人のことをガキ扱いするなら、ほんとにガキみたいな嫌がらせしてやろうかな。
「夜中にピンポンダッシュして郵便受けにスライム入れちゃう?」
一昔前の悪戯や、小学生の頃に男子の間で流行ってたタチの悪い悪戯を思い出し、黒い笑みを浮かべる。その瞬間、目の前のドアが急に開いたから、彼が戻ってきたのかと本気で驚いた。でもそこにいたのは、強い北風に吹かれて鼻を赤くしたお母さんだった。その腕にはしっかり卵のパックが入った袋を抱きしめてる。あ~あ、ホントに買って来ちゃったんだ。
「…彼、帰っちゃったの」
「うん…」
「そう…残念」
気まずそうな顔で入ってくると、お母さんは無言のままキッチンに立つ。ガサガサと音がして卵のパックを取り出す気配はしたけど、どことなく元気がない空気は伝わってきた。もしかしたら、まだわたしを泣かせてしまったと気にしてるのかもしれない。そう思った時、お母さんが不意に呟いた。
「ちゃんは…」
「…え?」
「小さい頃からパパの方に懐いてたもんねぇ…ううう」
「泣かないでよ!そんなことないし」
両手で顔を覆ってお母さんまで泣きだすから、今度はわたしが宥める側になった。何だかんだ言っても、お母さんはやっぱり寂しがり屋だから、わたしが傍にいてあげないと。
お母さんと生きていく――。
あの壮大な大地を飛び立った時、わたしはそう心に誓ったんだから。
わたしは明日、呪術高等専門学校に、正式に入学する。