13-こころというもの、言葉というもの
――泣けばいつでもしてくれるの。いつも……ここに…だけど…
ほんのりと頬を赤らめたモカの顏や、あの言葉が頭から離れない。そうか。これがエンドレスリピートというやつか、と変に納得する。おかげで二日も寝不足が続いてる。
って言うか――。
(――どこにしようが、チュウはチュウだ!!)
…なんて朝から脳内で大ツッコミ祭りを開催してたら、出張から帰ってきたのか、朝、通学途中にあるコンビニで彼とばったり出くわした。
「お、、おはよ~。いつもの時間に出てこないから、もう先に行ったのかと思った」
「………」
彼はホットミルク缶コーヒーを手に歩いて来ると、いつもと変わらない様子で声をかけてくるから、思わず顔を背けて歩き出してしまった。当然、一昨日の気まずい場面ぶりに会うから、どんな顔をすればいいのか分からなかったのもある。
よって――隣に並んだ状態にも関わらず、わたしの顔だけが明後日の方角を向いたまま歩く。
さすがに不自然すぎたのか、彼は「何か嫌なことでもあった?」と若干、身を屈めてわたしの顔を覗き込んできた。なのでわたしの顏は更に横へ横へと向いてしまう。
「ねー。三つ編みちゃん。今日も寝癖ついちゃった?」
「………」
更に更に前かがみになった彼が顔を覗き込んでくる気配がしたので、わたしも負けじと更に顔を――って、これ以上、首を曲げたらエクソシストだろ。そもそも人の首は360度も曲がらないのだ。というより曲げたら普通に死ぬ。
「何で…こっち見ないの…?」
「………」
さすがに異変を感じたのか、彼の声のトーンが変わった。だけど、そっぽを向いてしまった手前、簡単には戻せないし、今は彼の顔も見たくない。
あの夜のことと、モカのこと。一度ならず二度までも。
もう、これ以上、五条悟先生に「男」を意識して、顏がおサルのケツになるのは――や、なのである。
結局、わたしが無視を続けてたら、彼も諦めたのか話しかけてこなくなった。そのうち学校について、わたしは先に教室へと走る。最後まで彼と顔を合わせることはなかった。
後から変に罪悪感が襲ってきたけど、無視をしてしまった事実は消えないし、彼とモカのしてたことも消えない。この日の授業は全く頭に入ってこなかった。
わたしの家に泊りがけで隣人を襲撃しようという話も、例の彼女騒動の件で有耶無耶のままお流れになったようだ。その後は彼の誕生日があるとかで、みんなは「何あげる?」なんて盛り上がってたけど、わたしはそこに参加すらしなかった。
彼は12月7日で22歳になったそうだ。来年の春までは、わたしと6歳の差ができることになる。たかが6歳でも、やっぱり少し遠い存在のように感じた。
そして気づけばクリスマスで、任務帰りに美琴とケーキを買って、一緒に食べて、次の日からはまた任務や授業に明け暮れて、そんなことをしてたら、気づけば今年最後の日になってた。
「ねえ、ゴホッ…ちゃん。寒いから窓閉めてよ~ゴホッゴホッ。乾燥してるから喉がイガイガする~」
リビングの窓と保護用の窓まで開けて、ベランダから真っ黒な景色を見てたら、お母さんの苦情が飛んできた。北風がビュービュー吹きつけてくるから確かに寒い。でもずっとモヤモヤした頭を冷やすのにはちょうどい――。
「…へっぷし!」
「あら、可愛いクシャミ。って、風邪引くから早く閉めなさいってば」
「…ふぁい」
ずずっと鼻をすすりつつ、窓を閉めてリビングに戻る。これ以上芸人並みのクシャミが出ても困るから、そこは素直に言うことをきく。っていうか、自分のクシャミがお母さんとソックリすぎて、クシャミの仕方も遺伝するのかな、と自分でおかしくなった。
「それにしても、このおせち料理、ほんと美味しそう。ちゃんってばすっごく上達したわよねー」
お母さんは重箱の蓋を開けて、中のおせちに目を輝かせてる。あれを作るキッカケになったのはお父さんだった。わたしはおせちの料理全てが嫌いだけど、お父さんが好きだって言うから、作れないお母さんの代わりに作るようになって、それが毎年恒例になってしまっただけ。今年は作らなくても良かったのに、お母さんが「ちゃんのおせち食べないと正月って気がしない」と我がまま言うから、仕方なく今朝は早起きをして準備をした。学生のみ、大晦日と元旦は休みってことになってるから、どうせ暇だったんだけど。
「16やそこらで、ここまで煮物を作れる子なんていないわよね~。きっとおじいちゃんも喜ぶわ」
お母さんがおじいちゃんにも食べさせたいなんて言うから、おせちは二つ作った。明日はそれを持って、お母さんの実家に行く予定だった。
「ちょっと食べたいな~」
「ダメ!それは明日!今夜はおそばでしょー?」
早速つまみ食いをしようとするから、その手をパチンとはたく。その手をすりすりと撫でながら、お母さんは悲しそうな顔でわたしを見た。そんな顔してもダメなものはダメだ。でもお母さんは、ふと何かを思いついたように、突然笑顔になった。
「そーだ!これ先生に持ってってあげれば?」
「………!」
「きっと喜ぶわよ~。買ったおせちとは全然味が違うんだから。えっと…タッパーはどこしまったかしら――」
本気で持って行こうとしてるのか、お母さんがキッチンの棚を漁りだし、わたしは慌てて「やめてよ」と言った。あれ以来、彼とはまともに話してもいないのだ。
「あの人にだっているんだから。料理を作ってくれる婚約者が」
「え~~……そうかなぁ~…先生の婚約者より、ちゃんの作った料理の方が、ぜ~ったい美味しいと思うなぁ、ママは。もう保証付き!」
「………」
お母さんに保証されても…と思いつつ、婚約者のことを教えてくれた日の彼を思い出す。彼の婚約者って、どんな人なんだろう。やっぱり良家のお嬢様術師かな。
なんて考えてたら、お母さんの咳がいっそう酷くなってた。
「ゲホッゲホッ…」
「もー大丈夫?おせちに風邪菌まき散らさないでねー」
「雪降ってるのに窓全開にするからじゃなーい。バカ~」
「はいはい。悪うございましたー」
言いながら、もふもふのカーディガンを貸してあげると、お母さんはティッシュでビービー鼻をかみながら「ありがとー」と言って喜んでる。可哀そうだから暖房も温度を少しだけ上げてあげた。
――キス、してたの。悟は優しいの。
ふとベランダを見たら、ガラス窓にあの日のモカが映った気がした。
別に、何でもいいんだけど、ただ、ね。それが身近な子すぎて、ちょっと動揺してしまっただけ。あの日の朝も、どんな顔で彼を見たらいいのか、分からなかっただけ。
――何か嫌なことでもあった?
――何で…こっち見ないの?
ふと彼のことまで思い出して、また罪悪感を覚えそうになった時。ふとテーブルの上にある重箱が視界に入った。
――ちゃんの作った料理の方が、ぜ~ったい美味しいと思うなぁ。もう保証付き!
ほんとは話すキッカケが欲しかったのかもしれない。お母さんの言葉が後押ししてくれた気がして、わたしはすぐにキッチンへ向かった。便利な大きさのお気に入りタッパーを取り出し、そこへ料理を詰めていく。彼が和食好きかは知らないけど、とにかく全種類を入れていった。
お母さんは風邪を引きかけてるクセに、年越し前は必ずお風呂に入らないと気が済まないらしく、「体あっためてくるねー」と恒例のバスルームへ向かった。それを確認した後、わたしは薄手のコートを羽織ってタッパーを手に外へと出る。廊下は北風こそ入ってはこないものの、かなり冷んやりとしていた。
「…よし」
彼の部屋のドアを見上げながら、軽く深呼吸をする。確か昨日、大晦日まではまだマンションにいるとタクミ達に話してたから、出かけてなければいるはずだ。小さな罪悪感を消すために、お詫びとしてこれを渡す。何度もシミュレーションをしながら、最後にもう一度だけ深呼吸をしておいた。
意を決してインターフォンを押すと、ウチのと同じキンコーンという独特の音が中で響いている。でも応答はなく、わたしはもう一度だけそれを押した。その瞬間、応答するより先にドアが開き、彼が顔を出す。予想外の出迎えにひくりと頬が引きつったけど、どうにか「こ、こんばんは」と言うことが出来た。彼は「んあ、びっくりした」と言うほど驚いてもない感じで返しながら、手に持っていたコートを羽織り出す。いつもなら笑顔を見せてくれるけど、今はきっと笑ってない。相変わらずサングラスはしてるけど、口元は固く引き結ばれたままだ。機嫌、良くないのかな。
「どっか…行くの?」
「………ん…」
「………」
テンションひくっ!と突っ込みたくなるほど、抑揚のない「ん」だった。もしかして…まだ無視したこと根に持ってる?と内心イラっとする。22にもなって仮にも可愛い生徒が訪ねてきたと言うのに、その態度は何なんだ。
こんなやつ、絶対に意識なんかしない。そう心に決めて、持っていたタッパーを差し出す。
「あの…これっ」
「ん?」
「わた…お、お母さんが作って…作り過ぎたみたいで」
何も言うことを考えてなかったせいでグダグダになりながら説明する。この空気じゃとても自分が作ったなんて言えないから、小さな嘘をついてしまったけど、彼は少しビックリしたような顔で、タッパーを見つめてる。
「え、くれんの…?」
「…う、うん」
「うっそ、嬉しーっ」
表情のなかった彼の顔に、いつもの笑みが浮かぶ。それを見たらわたしもホっとしてしまった。彼は蓋を開けて中を見ると「すげぇ。うまそー」と喜んでいる。
「えっと…煮物とか好き?」
「大好き、こういうの」
彼はそう言いながら手づかみで里芋を一つ口へと放り込んだ。まさか目の前で食べられるとは思わず、呆気にとられていると、彼は食べた瞬間、嬉々とした声を上げた。
「ん~~~っま~!」
五条家のお坊ちゃんの口に合うのか?と緊張して見ていたら、意外にも彼は悶えながら「天才か?」と言ってくれた。それが凄く嬉しくて、つい「でしょでしょ?自信作だもん!」と口走る。あ、マズい。
耳ざとい彼がふとわたしを見るから「……お母さんの」とすぐに付け足した。危なかった。素直すぎでしょ、わたし。
動揺を見せまいと嘘くさい笑顔を見せれば、彼は無言でわたしを見ている。でも不意にふっと笑みを浮かべて何を思ったのか、ウチの方へ歩いて行った。
「じゃあーママにお礼言ってくるわ」
「え!あ…お、お母さん、今お風呂だから…!」
わたしの家の方へ歩き出す彼のコートをぐいっと引っ張れば、「んじゃ…あとで言う」と笑いながら振り向いた。良かった。ここでお母さんと話されたらバレてしまうとこだ。それは今更感満載で、かなり恥ずかしい。
彼は「これしまってくる」と一度部屋へ引っ込み、すぐに戻ってきた。その手にはマフラーがある。北風が冷たすぎて無理だと判断したようだ。でもこんな寒い大晦日に出かけるなんて、どこ行くんだろう。そう思った時、ああ、この人、婚約者いるんだっけ、と思い出した。
「じゃあ…また来年なー」
「あ、うん、良いお年を――」
定番の挨拶をして、わたしも部屋へ戻ろうとドアノブに手をかける。でもすぐに「」と呼ばれて振り向くと、彼はマフラーを巻きつつ、意味ありげな笑みを浮かべていた。
「な、なに――?」
「さぁ。僕が保健室でモカとエッチなことしてたと思ったんだろ」
「な…」
まさか彼の方からその話を持ち出すとは思わない。不意打ちすぎて一気に顔の熱が上がっていく。彼のせいでおサルのケツみたいになるのは嫌だったはずなのに、どう考えても今のわたしはソレになってるはずだ。
「そ、そそそっちこそ!わたしが婚約者のこと二年にチクったとか一瞬でも思ったんじゃないの?!」
動揺しすぎて変なことを口走ってしまった。彼は「はあ?」と呆れ顔でサングラスをズラしながら首を傾ける。わたしもムキになって彼に詰め寄ると、
「「そんなこと思ってないもんねー!」」
見事にハモるとはこのことで、タイミング、台詞に至るまで全く同じ返しになった。それにはお互いにきょとんとした顏で目が合う。先に吹き出したのは彼の方だ。
「ぶ…ははっつくづくとは気が合うねー」
「な、何それ…っていうか…早く行きなよ。婚約者の人、待たせたら可哀そうだし」
わたしも釣られて笑いながらも、彼の背中を押す。その時、彼が「ふふン」と何故かどや顔で振り向いた。何だ、その顏は。
「別れたよ。終わったんだ、あの日に」
「………へ?」
それまで笑顔だった彼が意外なほど真顔で言うから、その言葉は本当なんだと、何となく分かった。
「って言っても、僕がガキの頃に家同士が勝手に決めた婚約でさ。相手は幼馴染だったんだけど…よくあるでしょ。こういう世界じゃ」
「…な、ないよ。センセーの家がそうなだけで…」
「そお?家も相当名家だから、そのうち見合いさせられんじゃない?も」
「ま、まさか…って、そんな話より…何で別れたの…?」
踏み込んではいけないと思いつつも、そこは何となく気になった。家同士の繋がりで婚約したのに別れたというのはおかしな話だと思う。しかも相手が幼馴染というなら、知らない仲でもなかったはずだ。
わたしの不躾な質問に、彼はちょっと笑ったようだった。
「まあ…ぶっちゃけ僕は結婚相手がどこの誰でもいいと思ってたから放っておいたんだけど…トワ…ああ、彼女の方が…僕に本気だったから」
「え…?相手が本気なら何も問題ないんじゃ…」
「あるでしょ。僕は同じ気持ちで彼女を見れないんだから」
彼はしごく真っ当なことを口にした。彼にとってその幼馴染の人は妹みたいな存在らしい。でも互いに家のためと割り切ってたなら別れたりはせず、結婚してたかも、と彼は言った。何だそれ、と驚いたけど、五条家ともなれば愛のない結婚なんて当たり前ってことなのかもしれない。
でも彼は言った。
「だって地獄でしょ。惚れてる相手から女として見てもらえないのも、一生自分のことを好きにならない男と結婚するのも。僕は彼女にそんな思いはさせたくないし。かといって、やっぱり気持ちには答えてあげられない。だから別れた。まあ、そういう背景もあり、余計にあの落書きはイラっとしたんだけど――」
苦笑気味に言いながら、その横顔はどこか寂しそうだった。でも別れを決めた理由は、彼の優しさだ。幼馴染の彼女を少なくとも大事に思ってる。一方が本気なら、確かにそんな結婚は地獄かもしれない。彼女を家の犠牲にしないために、彼は別れる道を選んだ。
「ってことで、グッドルッキングガイ・五条悟先生はフリーになりました」
「な、何それ…わたしに言う?そういうこと」
思わず苦情を言えば、彼は愉しげに笑いながら「だから言えるんだよ」と、またズルいことを言う。
そして、そのズルい先生はと言えば「じゃあ、行ってきまーす」なんて明るく手を振り、出かけて行った。その後ろ姿を見ていたら、何とも言えない思いがこみ上げてくる。
「…んで…?」
何でそんな大事なこと、わたしに言うの。
分かってる。聞いたのはわたしだ。でも、そうじゃなくて。
「…先生なら…先生らしくしてよ」
聞いてしまった小さな後悔が、胸の奥に痛みとして刻まれてしまった。
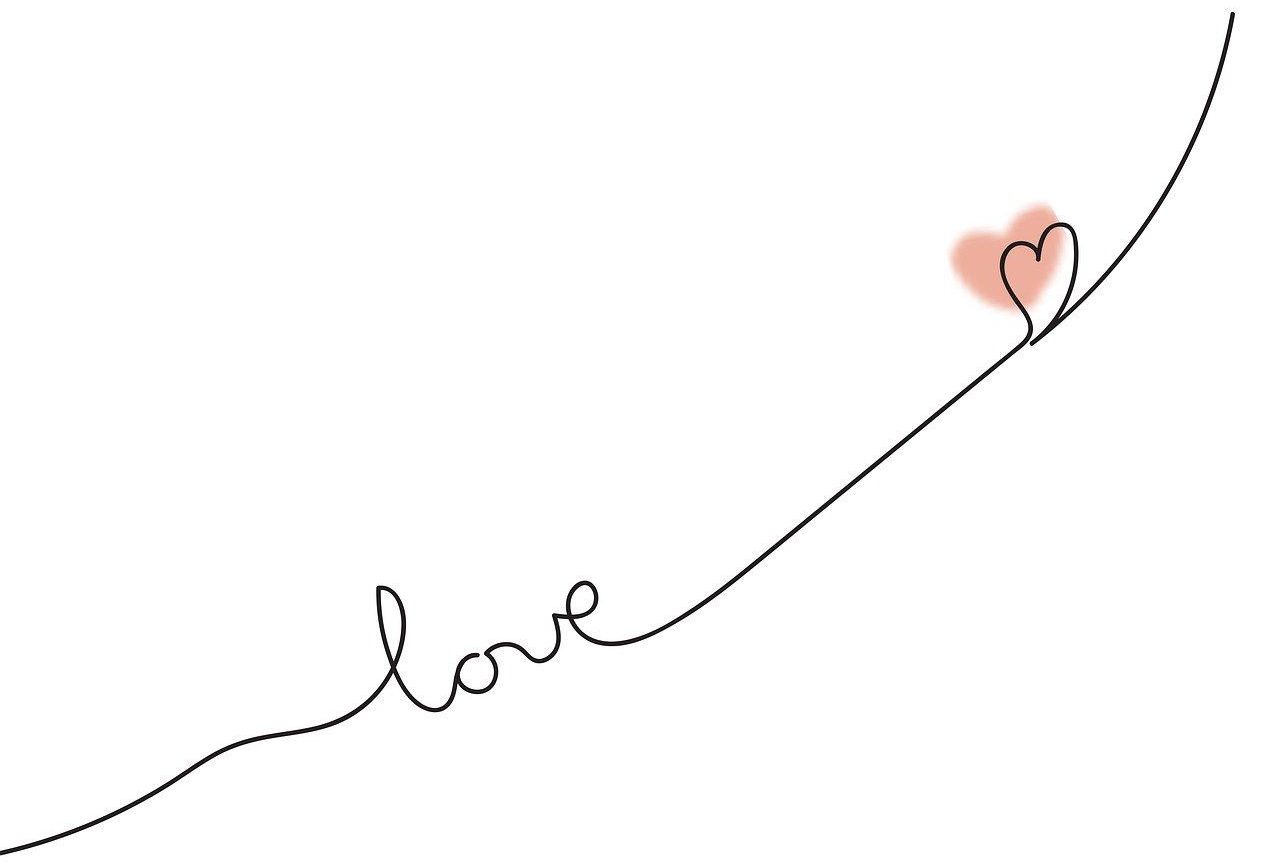
ひとこと送る
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
