14-こころというもの、言葉というもの
明けて2012年、元旦は予定通り、おじいちゃんちで正月を過ごした。お節料理はだいぶ好評で、また来年も作ってくれと頼まれてしまった。それがちょっとだけ憂鬱だ。あれを食べるお父さんはいないから、もう作らなくていいと思ってたから余計に。
でも、その時ふと彼が美味いと言って破顏した時の光景が頭に浮かんで、また作るのも悪くないかなと思い直した。何でそう感じたのか自分でもよく分からないけど。
そして今日、二日は高専に顔を出したあと、特に任務が入ってなかったこともあり、帰りは近くの神社まで美琴と初詣にやって来た。
「う~さっぶー!東京で元旦から雪ってありえないっ。まだあの雪だるま呪霊の影響受けてんのかー!」
吹きつける粉雪に、美琴が寒そうに首を窄めている。札幌の時みたいに足首まで埋まるほど積もりはしないけど、路面が凍結してるから足元は危ない。こっちの人は、ほぼ滑り止めのある靴なんか履いてないから、あちこちで「きゃー」「滑る~!」という絶叫が聞こえてきた。革靴じゃそりゃスケートリンク並みに滑るよね。
「はぁ…甘酒飲みたい…」
美琴が境内に出てる甘酒売り場を見ながら呟く。確かに美味しそうだけど、一応あれも飲酒になるのかなと疑問に思う。子供の頃から家では普通に飲んでたけど、さすがに外で飲むのは気が引けた。その隣には"おしるこ"と書かれた暖簾があるし、それもまた捨てがたい。
「ね、おしるこ食べない?空いてるし」
「あ~おしるこもいいね。じゃあ、そっちにしよっか」
美琴も乗り気らしく、すぐにお店へ走って行く。足元気をつけてと声をかけようとしたら、案の定。美琴はアイスバーンで足を滑らせ、「ぎゃぁぁぁああ」と叫びながら見事なスライディングをしたまま店先へと辿り着いた。「大丈夫?」と慌てて駆け寄ると、「頭は死守した」と美琴が盛大に笑いだす。自分の滑りっぷりがツボに入ったようで、「正月早々滑るとか、受験生なら涙もんだったね」と笑った。おしるこ屋のおじさんも「大丈夫かい?」と訊いてきたけど、顏は必死に笑うのを我慢してるようだった。それくらい美琴のスライディングは圧巻だったんだろう。
「あーお尻真っ白」
「ああ、払ってあげる」
そう言って美琴の真っ白にあった背中やお尻についた雪を手で払っていく。こういうのは札幌時代もよくやってたから、地味に懐かしい。
「でもさー。何では転ばないの?さっきも普通に走ってきたし」
無事におしるこを買って、ふたりで近くの階段に座り、アツアツのおしるこを「はふはふ」しながら食べてると、美琴が不思議そうな顔で訊いてきた。そう言われると走った気もする。
「ああ、それは慣れてるからとしか…体が覚えてるんだよね。雪道とか凍結した道の歩き方や走り方とか」
「マジ?そんなので歩き方とかあんの?」
「あるよー。足の力の入れ具合とかね。こっちの人って踵に重心置いて歩くのクセになってるんだと思う。だから足を出す時とか踵から滑ってステーンっていくんだよ」
「な、なるほど…私もさっき踵からいったわ。ってか、よく見れば似たようにコートの後ろとか白くなってる人、結構いるっぽい」
言いながら美琴が人混みへ視線を移す。釣られて見れば、確かにコートの後ろが雪まみれの参拝客があちこちにいた。ちょっと笑える。
「こういう時、きっと五条先生なら転ばないんだろうなー」
美琴も笑いながら、ふと彼の名前を出す。言ってる意味が何となく分かったから、つい笑ってしまった。
「あー…でも足元だし、術式関係なくないかな?」
「だってもし滑ったとしても無限発動したら雪まみれにはならないでしょ」
「…なるほど。ズルいな、それ。半分だけ白いとこ見たい気もするけど」
「黒板消し事件の時はなってたよ、それ」
美琴の一言で、脳内にあの日の情けない姿が思い出され、つい吹きだしてしまった。確かにあれも白黒だった。
「あーあー。五条先生は彼女さんとお正月過ごしたのかなぁ。今日は任務とか言って来なかったし」
「…あー何か別れたみたい」
と言った瞬間、しまったと思った。つい流れで口から出てしまった感じだ。美琴は「え、うそ!」と驚いた顔でわたしを見る。これはマズいかも。
「え、別れたって…何で知ってるの?」
「え、あー…まあ…チラ…と風の噂で…」
「あ、おじいちゃん経由?のおじいちゃんって御三家とも仕事してるんだよね」
「ま、まあ……うん」
どうにも誤魔化せない状態になり、そういうことにしておいた。これは完全にプライベートな事情だから、さすがに理由は言えないけど、ふと見れば美琴は「やった~」と、どこか嬉しそうだ。
「人の不幸を笑っちゃダメでしょ」
「だって~。五条先生は私の永遠のアイドルみたいなもんだし」
「…アイドルってガラじゃなくない?あの人」
「えー顔はその辺のアイドルよりイケてるじゃん。その辺歩けばみーんな振り返るし。しかも最強だよ?」
「性格はチャラいけど」
「えー親しみやすいじゃない。タクミなんか友達だと思ってるよ、五条先生のこと」
「あー名前呼びしてるもんね」
そう言ってから、ふとモカの顏が浮かんだ。彼女も彼のことを「さとる」って呼んでたっけ。それがやけに親しい空気を出すから、ちょっとだけ嫌な感じだ。
「ねえ、私たちも今度から悟って呼ぶとかどう?」
「え?」
「だって先生も私たちのこと名前呼びだし、そっちのが親しみやすくていいかなって」
「あー…まあ…そう…かな」
「ね、そうしよー。先生もきっと喜ぶって」
美琴は案外本気でそんなことを言っている。わたしも悟…と心の中で呼んでみたけど、何か少しだけむず痒い気がした。
おしるこを食べたあと、美琴は「また明日」と寮に帰っていき、わたしはひとり、帰路へ着く。曇天からは相変わらず小さな雪が延々と落ちてきて、その中をのんびり歩きながら、何となく彼のことを考えていた。
――は親しみやすいから。
そう言ってもらった時は嬉しかった。婚約者のことも、わたしを信用してくれてたから話してくれたかもしれないのに。何で別れたなんて言っちゃったんだろう、と溜息が出る。
頭へ、肩へ。雪と共に小さな後悔が降り積もる。はぁ、と息を吐けば、白いモヤとなって、それは冷たい空気に消えていった。
「…何か疲れた」
おじいちゃんちに一泊したその足で今日は高専に行ったから、一日ぶりのマンションだったりする。今日はお母さんも遅くなるみたいだし、早めにお風呂に入って寝ちゃおう。
お母さんは今夜、こっちの友達と新年会だそうで、おじいちゃんちから直接行くと話してた。まあ地元なんだし、久しぶりに帰ってきたんだから、会いたい人は山ほどいるんだろう。娘のわたしは友達と離ればなれになったというのに、という小さな恨み言はあれど。それはそれで羨ましい限りだ。ただ風邪気味なんだから飲みすぎるなよって、あとでメールを送っておかないと。
(あー…夕飯どうしよっかな…お母さん居ないなら適当にカップ麺でいっか。あー…洗濯もしとかないと)
こうして主婦みたいなことを考えるのは、今のわたしにとっては日常だ。母親がああいう人だと、娘は大人の階段を一気に駆け上がるしかなくなる。
マンションについて、一階のコンビニに立ち寄ると、適当に目についた商品をカゴへ放り込む。まずは目当てのカップ麺、ついでにジュースやお茶の類。あとは食べたいと思った時にすぐ食べられるような冷凍食品だ。
「あ…鍋焼きうどん美味しそう…」
冷凍食品の中に、今時期ぴったりな物を見つけて、つい手に取る。これはこのまま火にかけるだけでいいやつだから、これも買っておこう。お母さんの分もと考えて二つカゴへ入れた。最後に見にいったのはもちろんスイーツコーナーだ。さっきおしるこを食べたクセに、ついつい甘い物を物色したくなる。コンビニとはそういう場所だ。
「あ、クリームコーヒーゼリーある…」
それは出た時は必ず買ってるコーヒーゼリーで、上にふんわりした生クリームが乗っている。ゼリーはぷるぷるで味はほろにがだけど、クリームと合わせて食べると絶妙に美味しいのだ。思わず二つとって、それもカゴへ直行した。そのままレジに行って会計を済ませると、ずっしりとした袋を手に外へ出る。ちょっとカップ麺を買うだけのつもりが、結局こうして余計な物も買ってしまうのだから、やっぱりコンビニとは恐ろしい場所だ。いや便利なんだけど。
「ハァ~ほんと疲れた…」
夕べは散々大人達に付き合わされ、気疲れしたのかやけに足が重たい。高専はどうだ、とか、体力着いたのか、とか、五条のボンはちゃんと教えてくれてるか等々、親戚連中も集まったから質問攻めにされてしまった。まあ彼の名誉のために褒めちぎっておいたけど。次期五条家の当主だというし、普段、生徒のノリでバカやってるよ、とは言えなかった。
(もう、帰ってきたのかな…)
何となく思い出したことで、ふと彼の顔が浮かぶ。と、同時にマンションエントランス前によく知る顔を見つけて、ギクリとしてしまった。
「え…モ、モカ…?」
「…あ…」
エントランスの前で立っていたのは鼻を真っ赤にしたモカだった。
「な、なな何してんの…?」
「……お年始」
「え、うちに?…って、そんなわけないか…。あ、五条先生?」
急な展開で変なテンションのまま話しかけると、彼女はふと俯いてしまった。この寒空の下、ひとりで彼を待ってるなんて、なかなか根性がある子だと思う。
「まだ…帰ってなかった?」
「………」
またシカト状態に戻ってる、と溜息が出た。別にわたしには関係ないんだから通り過ぎてしまえばいい話なのかもしれない。だけど、雪は強くなってきてるし、そのせいで気温もかなり低い。彼女を放置して家に帰るのは何となく気が進まなかった。
「ね、良かったらウチで待てば?先生にはメール送っておけばいいでしょ。甘いものもあるし、あ、お腹空いてるなら何か作るし」
「………」
「ほら、こんなとこいたら寒くて風邪引いちゃうよ…って、何この冷たい手!」
モカの手を掴んだ瞬間、あまりの冷たさにビックリした。見れば手袋もしていない。
「指先真っ赤じゃん。何で手袋してないのー?も~早くおいでよ」
彼女の手を包んで温めながら、中へと誘導する。モカは何も応えなかったけど、大人しく着いて来てくれた。きっと寒さも限界だったんだろう。
「上がって。今日誰もいないから気にしないでいいし」
部屋についてすぐ暖房をつけると、玄関に突っ立ったままのモカを招き入れる。
「すぐあったまるから。あ、コーヒーと紅茶とココア、どれがいい?」
「……何でも…」
「そう?じゃあココアでも作るね。ミルクたっぷりのやつ」
コートを脱いで、すぐにミルクを入れた鍋をIHで温める。ココアが玉にならないようマメに掻きまわしてると、部屋に甘ったるい香りが充満してきた。出来上がったのをカップに注いで、最後に即席の生クリームをぐるぐるとのせていく。
「はい、どうぞ。あ、あとコーヒーゼリーもあるんだけど食べる?」
モカが小さく頷いたから、さっき買ったばかりのコーヒーゼリーとスプーンを彼女の前へ置く。ココアとコーヒーゼリーって変かなと思ったけど、間が持たないから、つい訊いてしまったのだ。
でもこの感じだとモカも甘い物が好きそうだ。
「えっと…先生にメール送っておくね」
一応、声をかけてから、ケータイでアドレスを開く。一応、何かあった時のために、と生徒全員が彼の連絡先を知っていた。でもわたしは彼に未だ連絡などしたことがない。
「えーと…モカがうちにいます……と。これでいっか」
端的に短い文を送ると、リビングに戻る。モカはココアのカップを両手で包んで、上品に飲んでいた。
「連絡しておいたから」
わたしも椅子に座ると、まずはココアで体を温める。疲れてるせいか、ココアの甘さが身に沁みた。
「あ、このコーヒーゼリーめちゃくちゃ美味しいの。食べてみて。ほろにが平気?あ、でもクリームと一緒に食べるとそんな苦くはないから。コーヒーゼリーと言えば、やっぱセブンだよねー。ゼリーのぷるぷる感と甘すぎないふわふわクリームが最高だし――」
「………」
「……(どつぼにハマってる?)」
あまりにモカが静かだから、ついつい無駄に喋りまくってる自分にどっと疲れてきた。部屋の真ん中に"シーン"という漫画でよく見るアレが浮かんで見える。
でもその時、ふとモカがわたしを見て「お母さんって元術師だったの?」と訊いてきた。会話する気はあるんだと、少しだけホっとする。
「うん、まあ。若い頃ね」
「お父さんは…?」
「あー…うち、お父さんは非術師で…警察関係者だったんだけどね。でもわたしが術師になるって言ったら大反対で遂に離婚までしちゃったの。お父さんは呪いが見える娘が怖かったみたい」
余計なことまで話してる自覚はあったけど、場の空気を持たしたくて口が止まらない。そんなわたしをモカは黙って見ていた。
「何でそんな話、笑って話せるの?」
「…泣きながら話せって?」
コーヒーゼリーをすくって口へ入れると、今の気持ち同様、ほろにがい香ばしさが口内に広がった。モカは途端に俯いてしまったけど、少しすると静かに自分のことを話し始めた。
「私…私は…早く家を出たいの…。あんなところ何一つ未練なんてない。でも…ひとりでは暮らせないでしょ…?だから、結婚したいの」
「…え?」
「…悟と結婚したいの」
は?と思った瞬間、部屋のインターフォンが鳴った。きっと彼が来たに違いない。開いてるって声をかけると、ドアが静かに開いて、案の定、彼が顔を見せた。
「…信じらんねえ。僕が強盗だったら、ふたりともアウトだよ」
いつもの軽口を叩きながら、彼は「モカ」と彼女の名を呼んだ。
「帰ろう。送るから」
彼が言った瞬間、モカが急に立ち上がって玄関へと駆け出出した。その勢いのまま彼の首に腕を回して抱き着く。その光景がやけにリアルで、さっきのモカの言葉を思い出す。
彼女は、彼と、五条悟と結婚したいと言った。
「いてて、抱き着くな!靴を履け、靴を!」
ぎゅうぎゅうとモカに抱きしめられて、彼が呆れたように叱ってるのを、わたしはただ見ていた。
「、悪かったな。じゃあな」
「………」
何その軽い感じ、と思ってると、モカはわたしをチラっと見てから、更に甘えるように彼にしがみつきだした。
「…さとる…」
「スッポンか、お前は~…」
彼はモカを引きずるようにしながら出て行った。また部屋に静けさが戻る。テーブルの上には食べかけのコーヒーゼリーが無惨な姿で残されていて、それを見てたら無性に腹が立ってきた。
「…ちゃんと食べてってよ…」
楽しみに買って来たわたしの好物はモカの口には合わなかったらしい。スプーンがささったまんま、グチャグチャになっていた。そのままベランダへ出ると、窓を開けて遥か下を覗く。少しすると彼がモカの背中を支えるようにマンションから出てくるのが見えた。モカも同じように彼の背中へ手を回し、どう見ても生徒と教師には見えない。
雪の中、ふたりは駅の方へと歩いて行って、次第に見えなくなった。
さっきまでの重くて冷たい後悔の雪が、ふたりの姿と共に消えていく。消してやる――。そう思った。
「…結婚って…何それ…」
モカと彼には、わたしの知らない半年間がある。それが大きな壁となって立ち塞がったように思う。
だけど――ここへ引っ越してからの日々、彼との会話を思い出していたら、ふと、自分の中の傲りに気づいてしまった。
わたしは隣に住んでるから、みんなの知らない彼との時間は、わたしだけの特権のような気がしてたんだって。
長い時間、そんなことを考えていたら、玄関の方で鍵の開ける音が聞こえてきた。無意識に時計を見れば、すでに午後11時近い。
こんな時間まで飲み歩いて、と思いながら玄関へ行くと、そこには知らない男の人に支えられたお母さんがグッタリしてて、凄く驚いた。
「えっと…お母さん、凄い熱があって。それとだいぶ酔ってるから。止めたんだけど、もう殆ど吐いちゃって」
「え…あの…」
「ああ、僕は小百合ちゃんの幼馴染で武井です。ちゃん、だよね?」
優しそうな人だった。お母さんに幼馴染がいたなんて聞いたことがない。でも、今はとにかくこの酔っ払いを寝かせなければ。武井さんからお母さんを受けとって、お礼を言うと、彼は「お大事にと伝えて」と優しい微笑を残して帰って行った。うーん、なかなかのイケメンだったかも。お母さんってばやるな。とはいえ――。
「もぉー…熱があるのに飲まないでよ」
「だってぇ…久しぶりにみんなに会いたかったんだもーん…」
「そんなに酔ってたら薬も飲めないじゃない」
「…いらーん…寝るぅ…」
引きずるように寝室まで運ぶと、お母さんはそのままベッドへ転がるようにダイヴした。仕方ないと布団をかけてあげると、寒いと言ってそれに包まる。こうなると子供みたいでタチが悪い。
「…みんな勝手なんだから」
自分の部屋へ戻ってドアを閉めると、そんな言葉が零れ落ちる。色々あって心身ともに疲労困憊。こういう日はサッサと寝るに限るから、わたしも歯を磨いてすぐにベッドへ潜りこんだ。
でも一時間後――何となく目が覚めてしまった。部屋は静かで何の音も聞こえない。それが逆に気になってベッドを抜け出す。
酔っ払いのお母さんは時々イビキをかくから、わたしの部屋までかすかに聞こえてくることがある。でも今夜はそれが聞こえなかった。
「…お母さん…?」
そっと寝室を覗けば、さっきと同様、お母さんが布団に包まってるのが見えた。だけど寝息は聞こえなくて、代わりに苦しげな息が不規則に聞こえてきた。
「え…お、お母さん…?」
すぐにベッドへ近づくと、顔を覗き込む。お母さんは意識がないのか、はぁはぁと断続的に荒い呼吸を繰り返していた。そっと額に触れてみると物凄く熱い。全身がぶわっと総毛だつような感覚になって、恐怖にも似たものが全身を巡っていった。お母さんのこんな姿は初めて見たから、酷く動揺したのだ。
「あ…きゅ…救急車…」
ただの風邪かと思ってたけど、そうじゃないのかもしれない。そんな思いが過ぎった時、急に怖くなった。
だから――つい家を飛び出して彼の部屋のインターフォンを鳴らしていた。いるかどうかも分からなかったけど、数回鳴らしたところでドアが開く。彼は寝てたのか、サングラスもせず、目を擦りながら顔を出した。
「な…どうした――」
彼の顔を見た瞬間、わたしは無意識にさっきのモカみたくしがみついてしまっていた。怖くて勝手に体が震えてしまう。お母さんに何かあったらどうしようって、そんなことばかり頭に浮かぶからだ。
「お、お母さんの…意識がなくて――」
そこまで言った瞬間、彼は理解してくれたらしい。すぐにわたしの家へ入って行くと、お母さんの様子を確認したあと、放心してるわたしの代わりに救急車を手配してくれた。
「、すぐに着替えて。僕も着替えてくるから、出かけられるようにしといて」
「え…」
「何でもいいから着替えて。すぐ救急車が来るから」
「せ、せんせーも…」
「僕も行くから」
肩をぐいと掴んで、彼はわたしを真っすぐに見つめながら言った。
「大丈夫だよ」
「……ほんと…?」
「ああ、大丈夫」
彼の綺麗な虹彩が見たこともないくらいに真剣にわたしを射抜いてくる。その言葉が、わたしの不安な心を消してくれた。
「…う…」
安心した瞬間、わたしの目からボロボロと涙が零れ落ちて来て、最後には子供みたいに泣いてしまった。そんなわたしを、彼はそっと抱き寄せて、救急車が来るまでの間、ずっと背中をポンポンと叩いてくれてた気がする。これまで色んなことがあっても殆ど泣かなかった分の涙が、今頃になって一気に溢れてきたのかもしれない。彼に肩を抱かれながら救急車に乗っても、わたしはひたすらお母さん、と呼んで泣いていた。その声でお母さんが僅かに意識を取り戻したあと「どうしたの…?」と不思議そうな顔で微笑むから、それを見てまた泣けてしまうの繰り返しで。その間も――ずっとわたしは彼の腕に守られていた。
「あれ、帰るの?」
お母さんを入院させ、医者の話を聞いたあと。ロビーに行ったら、彼はまだそこにいてくれたらしい。うーんと伸びをして立ち上がった。
「ん…付き添いは必要ないって…。体弱ってるから一週間の入院になったけど」
「ん。じゃあ、帰ろうか」
彼はかすかに微笑むと、わたしの頭をふわりと撫でて歩いて行く。自然とわたしもその後から着いて行った。あんな大泣きをしてしまったから、ちょっとだけ恥ずかしい。
「しっかし風邪で弱ってる時に大酒飲めば、誰でもぶっ倒れるって証明したな、ママは」
タクシーを待つ間、彼がそんなことを言いながら笑う。ほんとにその通りだと思いながら、ふと彼を見て気づいた。
「せんせ…コート着てない…ごめん…」
「謝ることないでしょ。こないだ煮物ももらったし。あ、タッパー返してない。あげくお礼言い忘れてるし」
「…いいよ、そんなの」
ほんとはね、アレはわたしが作った――。
「ありがとー」
「……え?」
何が?と思って顔を上げると、彼は優しい笑みを浮かべながらわたしを見下ろしていた。
「いい嫁さんなれるわ、ちゃん」
「……っ?」
ふふんと鼻で笑う彼を見て、わたしの顏が真っ赤になった気がした。あの日の嘘を、彼はとっくに見抜いてたらしい。この人は――知らんぷりするのが超絶得意だったようだ。
それからタクシーに乗って、ふたりでマンションに帰ってきた頃には、すでに朝の四時になるところで、あと数時間もすれば学校へ行く時間だった。
「じゃあ…またあとで」
彼が自分の部屋に入り、顏だけ出して微笑む。そうか、またあとで会えるんだ、とふと思った。
「…うん」
「ちゃんと鍵かけて」
「…うん」
「あ」
「え?」
わたしも家に入ろうとした時、何かを言いかけたのが聞こえて体を後退させる。彼はわたしと目が合うと、ふっと笑みを浮かべた。
「寝れる?」
「……うん。あの…ありがとう」
この時、初めて彼に対して素直になれた気がして、自然に笑みを返していた。
今は、壁を隔てて眠る。それだけで安心することが出来る気がしていた。
でもいつか――今夜、守ってくれた彼の手を。わたしはきっと、欲しくなる――。そんな予感がしていた。
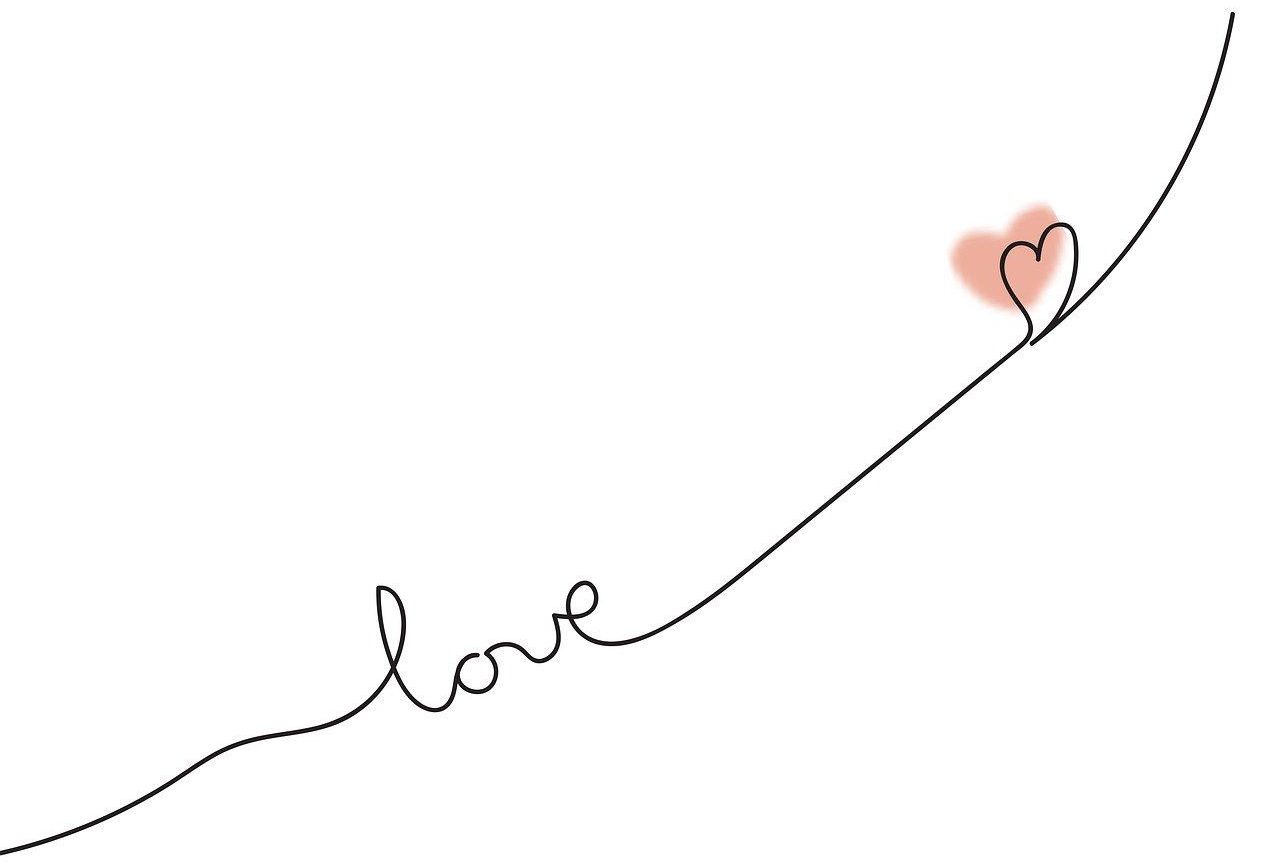
ひとこと送る
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
