code:05 / A worthy rival
「―――やれやれ。まさか寝てるとこを叩き起こされるとはね」
苦笑気味に言いながら、モリソンは慣れた手つきでハンドルを切った。
そんな彼の苦情も、助手席に座る男には通用しない。
夜の街並みを眺めていたダンテはその視線を運転手に向けると、綺麗な青い目を楽しげに細めた。
「0時前に寝てるなんて年じゃねえのか?」
「夕べから寝ないで依頼人のお守をしてたんだ。早寝くらいするさ。あと二時間は寝かせて欲しかったな」
「久々に楽しそうなパーティだ。早めに行きたいだろ?最近大した敵も現れなくて体が鈍ってたところだしな」
「ま、気持ちは分かる…が。今回の仕事は俺が仲介した仕事じゃないし、俺としては関係ないんだがね」
「そう言うなって。車持ってんのモリソンしかいねえんだよ」
「…買えよ、車くらい。これから仕事始めるのに必要だろう」
「今回の仕事の依頼料で買うさ」
ダンテは澄ました顔で応えると、「港についたら起こしてくれ」とシートを倒した。
「おいおい。人を起こしといて自分は寝るのか?ったく、お前って奴はホントいい性格してるよ」
「"寝る子は育つ"ってね」
「成人過ぎてもまだ育つ気か?」
その横暴ともとれる態度に苦笑いしつつも、どこか憎めない男だ、とモリソンは思う。
普段はいい加減で、どこまで本気なのか測りかねるところも多々あるが、複雑な運命を背負い、
その自らの運命に翻弄されながらも、やっと自分の目指す道を見つけつつある。
軽口を叩いていても、今現在、父スパーダの志を誰よりも理解しているのはこのダンテだろう。
この性格上、最初は理解されにくいが、実は優しい心の持ち主でもある。
現に突然訪ねて来た良く知りもしない少女を、兄に頼まれたからと言って面倒を見るくらいだ。
モリソンもの事を紹介された時は、少なからず驚いたクチだった。
(兄の為…それもあるだろうがダンテも意外なとこで"同胞"に会って兄と同じ気持ちになった、というとこかもな)
半人半魔という存在は、どちらの世界でも疎まれる傾向にある。
それに、どこにでもいる、というほど当たり前の存在でもない。
故に彼らは生まれながらに"孤独"という運命と戦う羽目になるのだ。
唯一の味方である両親がいないなら、それは尚更だ。
モリソンはバックミラーに映る少女に視線を向け、かすかに微笑んだ。
「ま、いいさ。今日はちゃんもいる事だし」
「ごめんね、モリソン。関係ないのに運転なんか頼んじゃって…それも仕事から戻ったばかりなのに…」
モリソンとミラー越しで目が合うと、後部座席に座っていたは申し訳なさそうに言った。
(この子も優しい子だ。きちんと他人を気遣える"心"がある…)
普通の人間だとか悪魔の血を引いている、とか、そんなものは関係ない。
要は全て、そこに心があるかどうかだ。
モリソンは内心そう実感しながら優しい笑みを浮かべる。
「私は明日にしようって言ったんだけど、どっかの甘党が言う事きかなくて」
「……俺の事かよ」
「あら。起きてたの」
目を瞑ったまま応えるダンテに、はぺロリと舌を出す。
ダンテは体をのいる方に向けると、腕を枕にしながら目を細めた。
「そもそも今回の依頼、お前の事情にも関係あんだろーが。焦ってるように見えたから俺は―――」
「…はいはい。ありがとう御座います。でもモリソンを巻き込むって知ってたら今晩くらいは我慢したわ」
「チッ…俺一人悪者かよ」
の態度にダンテは呆れたように息を吐くと、今度は背中を向けてフテ寝に入る。
その姿には密かに笑いを噛み殺し、窓の外を流れる景色に視線を向けた。
これからモリソンに港まで送ってもらい、そこからインチェ島近くの街、ボルゴまで向かう予定だ。
奇しくもダンテがレディに頼まれた仕事内容と、が確かめようと思っていたものが同じだと知った二人は、食事を終えて事務所に戻ると、すぐに出発の準備を始めた。
は朝一番で発つつもりだったが、港のある街までかなりの距離がある為、ダンテがそれだと一日損をする、と言ってモリソンに連絡したのだ。
そんな事情で三人は夜中にドライヴをする事となった。
といって、関係のないモリソンには悪いが、一刻も早く事実を確かめに行きたかったのはも同じだ。
先に島へ行ったというサガロ達の事も心配だった。
ダンテがそれを察し我がままを言ってモリソンを呼んでくれたのは先ほどの言葉を聞いたら明らかで。
彼の気遣いを知ったは、憎まれ口を叩いたものの心の中で彼に感謝をしていた。
「―――しかし凄い荷物だな。それ全部食料かい?さっきからハンバーガーのいい匂いがするが…」
ふとモリソンが、の脇に置いてある大量の紙袋を見た。
「ああ、これ?これは…」
も紙袋に目をやり、思わず苦笑する。
「例のグロリアからダンテに差し入れ」
「…なるほど」
モリソンも"グロリア"と聞いて苦笑いを浮かべる。
当然ダンテが街で有名なドラァグクイーンに追いかけまわされてるのは良く分かっているのだ。
「いつも突然来るんだけど今夜もね…モリソンに連絡するまで大変だったの。事務所に戻って出かける準備をしてたら―――」
は眠気覚ましにちょうどいい、というように、先ほどあった事を話しだした。

「―――はあ?お前もそのインチェ…何とか島に行こうと思ってたのかよ?」
ダンテはの話を聞いて多少は驚いたようだったが、「なら話は早い」と楽しげに笑った。
互いの目的が同じである以上、すぐに準備をしようと、マスターに支払いを済ませ、「仕事なら手伝うぜ」と声をかけてきたエンツォを無視し(!)二人は事務所に戻った。
「で?その何とか島ってどんなとこなんだ?」
事務所に戻るとダンテは早速、愛用の二丁拳銃<エボニー&アイボリー>の手入れを始めながら、に問いかけた。
も自分の銃<イリーナ>専用のマガジンを並べて弾を込め始める。
「"インチェララッカーレ島”よ。通称インチェ島。いい加減覚えたら?」
「そんな言いにくい名前、覚えるのも面倒くせえ」
想像通りの答えが返って来た事で、は呆れつつも銃にマガジンを戻すと、予備の弾もコートの内側へと装備した。
もし悪魔との戦闘になっても困らない弾数を普段から用意してある。
「インチェ島は古くから"悪魔を封印する島"として知られてる無人島よ。スパーダが倒した上級悪魔を封じる為に作ったって言われてる」
「へえ…親父がねえ…。で、普段は誰もその島に近づかない、と」
「ええ。そういう謂れがあるからなのか…その島の近くでは悪魔の出現する率が多いの。封印されていても、その悪魔達の禍々しい魔力を僅かに感じて寄ってくるんじゃないかって言われてたわ」
「なるほど、ね―――」
ダンテはの話を聞きながらも、最後に弾を込めたマガジンを戻すと、二丁の銃を構え、壁にあるダーツボードに狙いを定める。
右手用の白い銃、アイボリーは速射&連射用、左手用の黒い銃、エボニ―は遠距離射撃用だ。
稀代の名工と呼ばれた銃職人、ニ―ル=ゴールドスタインが、ダンテの為に設計し、ダンテ自身が組み上げたこの二つの銃は、長年愛用してきた良き相棒でもある。
「なら、その島にいる悪魔全部ぶっ殺せばいいって事だろ」
「…ちょっと!壁に穴増やさないでよね。また工事費用が重なるでしょ」
壁に照準を定めているダンテに気付き、が苦情を訴える。ダンテは僅かに銃をおろし溜息をついた。
「撃たねえよ。照準合わせただけだろ。これ以上、工事が長引くのは俺もごめんだぜ」
ダンテは二丁の銃を軽く指で回すと、背中のホルスターへと軽快な手つきで収めた。
そして机に立てかけてあったダンテの身長以上もある大剣<リべリオン>を握る。
これは父スパーダの形見であり、これもダンテにとってなくてはならない、もう一つの相棒だ。
前にが"どこかで見たような気がする"と感じたのも当然で、スパーダの伝書にはこのリべリオンの絵が詳しく載せられている物もある。
ダンテの素性を聞いた時、はそこで改めて納得したのだった。
同時に、ダンテが本当にスパーダの息子なのだという事実も、の中では不本意ながら(!)信じざるを得なかった。
「で、今から出たらどれくらいで着くんだよ。その何とか島に」
ダンテはトレードマークの真っ赤なロングコートを翻しながら振り向くと、両手を広げて楽しげに言う。
その姿に、本当に悪魔と戦うのが好きなのね、とは少々呆れつつ、苦笑いを零した。
「今からじゃ最終には間に合わないし無理よ。港に行くまでの交通手段が―――」
「んなのモリソン呼べばいいじゃねえか。それにこの時間帯なら道は空いてるし車の方が早い」
ダンテは当然という顔で机の上にある電話へと手を伸ばす。
それにはも慌てて止めた。
「ダメよ。モリソンは今回関係ないじゃない」
「じゃあどうすんだ?明日の朝まで待って、お前の知り合いの騎士長さまが殺されたら?」
「…それは…」
それを言われるとも辛い。
フォルトゥナから船でインチェ島へ移動するにも丸一日はかかるはずだが、サガロは今朝、島へ経ったとシェスタが言っていた。
すでに島からほど近い港街、ボルゴへ到着しているといっていいだろう。
しかし街からインチェ島へ向かう船など出ているはずもない。好き好んで悪魔の出現する地域に出かける物好きなどいないからだ。
インチェ島へ向かう為には街で観光客相手に船を出している命知らずな船乗りを探さなければいけない。
お金さえ払えば、多少危険な場所にでも案内をしてくれる人間はいくらでもいる。
ただそれも昼間なら、という意味で、より危険が伴う夜中に出航してくれる船乗りがいるとは到底思えなかった。
(もしサガロ達がそれで時間をくっていたとしたら…何とか間に合うかもしれない)
夜10時過ぎ。この時間、車で飛ばして港まで3時間半といったところか。
そこから船に乗りボルゴまで4〜5時間はかかるが上手くすれば夜明けまでにはつける。
「な?車の方が確実だろ?」
考え込むの様子に気付いたダンテが肩を竦め笑う。
そしてそれに不本意ながら、が頷こうとしたその時。豪快に"Devil May Cry"のドアが開け放たれて、野太い声が事務所内に響いた。
「―――ヤッホー!ダンテちゃぁーん!会いたかったぁ?」
「…げっ!!」
ドアに背中を向けていたものの、条件反射なのか、ダンテはその声だけで徐に顔をしかめの背後に隠れようとする。
しかしより大きなダンテにとって、それは隠れた事にはならない。
当然、その賑やかな訪問者も目ざとくダンテを視界に入れると、グロスで艶々の唇を嬉しそうに歪め、腰を振って歩いて来た。
いつものように体の線が全て出るような真っ赤なボディ・コンシャスドレスに、今日はブロンドのウィッグを被っている。
いつ見ても迫力がある、とは内心呆気にとられていた。
「やぁーね!そんなとこにいたの?ダンテちゃん」
自分から隠れるようにしていたダンテを見ると、この街では有名人でもある彼女――男だが――グロリアが、呆れたように微笑んだ。
「な…何しに来たんだ?俺たちはこれから仕事で出かけんだけど―――な?」
「…ちょっと…私を盾にしないでよ…」
「バカ。お前がいねえと俺の身が危険だろーが…っ」
悪魔にはめっぽう強いダンテも、このグロリアだけは苦手らしい。
を盾にし(!)青い顔で口元を引きつらせている。
しかし小声でモメてるそんな二人の様子に気付く事もなく、グロリアは筋肉質な巨体をくねらした。
「あらー残念。そうなの?って言っても私もこれから、お・し・ご・と・よ!」
長い付け睫毛で飾った大きな瞳でウインクをかまし、グロリアは机の上に持っていた袋をどさりと置く。
それは近所にあるバーガー屋の袋だった。
「お店の前にダンテちゃんの顔、見に来ただーけ。それといつもの差し入れ!」
「……わ、わりぃな、いつも…そんな気遣いはいらねえんだけどよ」
ダンテは顔をひきつらせながらもお礼を言う。
それを見たグロリアは嬉しそうに頬を緩めると、怪しい目つきでダンテを見た。
「やだ、お礼なら言葉じゃなくて体で受け取るっていつも言ってるじゃなーい?」
「………そ…それは…無理だろ。ほら俺こう見えて何気に病弱っつーか――――」(!)
「大丈夫よ!私がリードしてあ・げ・る!」
「……って、人の話聞けよ!」
思い切って突っ込んだダンテの言葉も、グロリアには届かないのか――マイペースで人の話は聞かないタイプ――彼女はふとダンテの前にいるに目を向けた。
「…あら、あんたまだいたの?」
「…え?あ、いや…他に行くところもないし…」
怖い目で睨まれ、今度はの顔が引きつる。最近顔を合わせると、いつもこうだった。
このグロリア、女であるがダンテと一緒に働き、なおかつ一緒に住み始めたのが気にいらないらしいのだ。
最初の頃は「あんた、本当にダンテちゃんとは何でもないんでしょうね」と会うたび怖い顔で凄まれた。
「だから前にも言ったじゃない?住み込みで働ける店、紹介してあげるわよ。だからサッサとここから出てって」
「い、いや出てけと言われても…」
いつもの脅迫が始まり、は口元が引きつりつつ、後ろに隠れたままのダンテを睨む。
オーナーなんだから何とか助けろ、という意味を含めて、だ。
しかしダンテは関わりたくないというように、視線を反らしていつでも逃げられるよう、少しづつ後ろに下がっている(!)
全く頼りにならないとは呆れつつ、「オーナー!時間がないんですけど」と怖い顔で振り向いた。
「あ、あ〜そうだった!モリソンに電話しないとって事でグロリア、わりぃんだけど仕事があるし、その話はまた今度って事で―――」
に軽く足を蹴られ、ダンテはやっと重たい口を開いた。
そう言わなければ、後でからグチグチ文句を言われるのが目に見えている。
グロリアも怖いが、何気にも本気で怒らせると怖いというのは、この一週間で学習したのだ。
「あらやだ、ごめんなさいねえ、ダンテちゃん!お仕事なら仕方ないわね。それを邪魔するなんて野暮な女の真似はしないつもりよ」
ダンテの勇気が報われたのか、意外にもグロリアはあっさりと引き下がる。
こういうところは女心(?)なのか、仕事の邪魔をして嫌われたくないという気持ちが少しはあるようだ。
「じゃあお仕事から帰ってきたら教えて!今度は手料理ご馳走しちゃうから」
「あ、ああ……そう、だな」
「それか寂しくなったら、いつでも電話して。私の電話はダンテちゃん専用よ〜。もちろんか・ら・だ・も!うふふ」
「………は、ははは」
グロリアの一方的な求愛に、さすがのダンテもタジタジのようだ。
それを見ていたはコッソリ笑いを噛み殺していたが、不意にグロリアに睨まれ、慌てて口元を隠す。
「ちょっとそこの貧弱女」
「……は?ひ、ひん?」
「…ぶはっ―――いってぇ!」
そこで思い切り噴き出したダンテの足を、は思い切りブーツのヒールで踏んづけた。
そして自分を睨んでいるグロリアを睨み返し、「貧弱女って…私の事?」と腕を組んで首を傾げる。
出来ればあまりケンカしたくない相手だったが、こうまで言われちゃ女がすたるとでも言いたげだ。
その一触即発な空気を感じ、ダンテはこそこそと机の後ろに隠れた。
「女なんて低俗な生き物、今ここにあんたしかいないでしょ?」
「て…低俗ぅ?!それはいくら何でも言いすぎじゃ――――」
「あら。当たってるじゃない?女なんて男に媚びて生きてくしかない弱っちい生き物じゃないの」
「……弱っちい?」
さすがにカチンとしての目が細められる。怒りのオーラが沸々と彼女の周りから出ているようだ。
これまで数々の悪魔と戦ってきたにとって、貧弱女よりも弱っちいと評された事の方が屈辱的という顔だ。
それに気付いたダンテはマズイと言った様子で「おい」と小声で呼びかけた。
「…こらえろ。アレでも一応、"人間"だ…(!)」
半魔であるダンテは悪魔以外、極力手は出さない、という――向かってくる人間は別だが――概念がある。
しかしはそんなダンテを無視して、グロリアを睨んだ。
「で、何が言いたいんですか?」
腕を組んだまま一歩前に出るに対し、グロリアも腰をくねらせ歩いてくると、長めのウイッグを軽く掻き上げ、上からを見下ろした。身長が190以上はあるグロリアの迫力は相当なものだ。
「前にも言ったと思うけど…ダンテちゃんに色目使ったり、その貧弱な体で迫ったりしたら私が許さないわよ」
「…私も前に言いましたけど!それは絶対、永久に!"ありえません"!!から!!」
グロリアの失礼な物言いにカチンとして、思わずそう言い返す。
「それに私、好きな人いますし!!」
「……あら、そうなの?」
「ええ。ダンテなんかよりも凄く素敵な人なの!」
そして「フン!」と顔をそむければ、グロリアも同じように顔をそむける。その中で一人ダンテだけは複雑そうな顔をしていた。
「それじゃ安心したとこでダンテちゃん!私お店もあるし行くわ。バカな女を相手にするのも疲れたし―――」
「……バカァ?」
「我慢しろ…!――――お、おう……まあ、頑張って」
それまでの引きつった顔から一転、ニッコリ微笑むグロリアに、熱くなっているを抑えつつダンテも引きつった笑顔を見せる。
「いくら溜まったからって、その女で抜いたら、私泣いちゃうから。――――じゃあね」
グロリアは最後にを睨むと、ダンテに投げキッスを送り、そのまま腰を振りつつ店を出て行った。
途端に静寂が戻った事務所内に、ダンテはホっと息をつく。
しかしだけは納得いかないような真っ赤な顔で、机をドンっと殴りつけた。
「なーにがバカ女よ!自分だってバカ男じゃない。だいたいダンテのどこがいいの?」
「……おい、俺に八つ当たりすんじゃねえよ。こっちだって被害者だぜ?」
「いいえ!関係のない私が被害者です!何であんなゴリラに侮辱されなくちゃいけないわけ?失礼しちゃう!――何よこんなの」
怒りが収まらないはブツブツ言いながら机の上にある差し入れを捨てようとした。
が、ダンテが慌ててそれを止め、「食いもんには罪はねえだろ」と、の手から袋を奪い返す。
「それに今から長距離の移動だ。メシないと困るしな」
「……それもそうね」(!)
怒りはあるものの、食欲の方が大事らしい。はあっさり認めると、大げさに溜息をついて机の前の椅子に座った。
「何だか出かける前に疲れちゃった……」
「……俺もだ」
一気にテンションも下がったのか、ダンテも机の上に腰をかけ、盛大な溜息をついている。
グロリアが来るといつもこうだ、と内心思いながら、はダンテを見上げて肩を竦めた。
「こうなったら付き合ってあげれば?案外"あっちの世界"もいいかもよ」
「…あ?何で俺が男と付き合うんだよ。俺はノーマルだ」
「でもあの様子じゃ心は女と同じじゃない?」
「俺はグラマーな女がいいんだよ!どんなに溜まっても男とはヤらねえ!男にケツ貸すくらいなら最悪お前で我慢する―――うっ」
笑い気味に話していたダンテは、お尻のあたりに堅いものを突き付けられ、言葉を切った。
「…その前にコレでお尻の穴、増やしてあげましょうか?」
「あ、いや…悪い…今のは言葉のあやだ…」
机の上に腰掛けていたダンテは、自分のお尻に銃を突きつけられている感触に、笑顔をひきつらせる。
そして話を誤魔化すかのように電話へと手を伸ばし、すぐにモリソンへと電話をかけ始めたのだった。
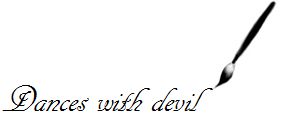
「それにしても…心配だろ?ちゃんの知り合いが絡んでるなら」
グロリアの話で盛り上がったあと、不意にモリソンが口を開き、はハッとしたように目を開けた。
窓に頭を預けたまま話していたはずが、いつの間にかウトウトしていたらしい。
「ああ、悪い。寝てたかい?」
「ううん、大丈夫」
「…大丈夫、という顔じゃないな。その分だと今朝も早起きしたんだろう」
「まあ、掃除もあったし」
「ダンテがこの調子だからね。なかなか片付かないんじゃないか?」
さすがモリソン。よく分かっているとは苦笑いを零す。
だいたいダンテは"片づける"という単語を知らないらしい。
『よく母さんにも同じ事を言われて怒られたな…』
が"出した物は片づけて"と何度か怒った時、情けない顔でそう言っていたのを思い出す。
ダンテの母親であり、スパーダが唯一愛した女性は、なかなか厳しかったようだ。
(でも…綺麗な人だったんだなぁ…。そりゃそうか。英雄スパーダまでメロメロにしちゃうくらいだものね)
ふと事務所の机に飾ってあった写真を思い出し、は笑みを浮かべた。
ダンテ、そしてバージルの母親であるエヴァが、優しい笑みを浮かべている写真だ。
彼女はダンテを悪魔から守り、そして殺された。あの夜バージルも確かそんな事を言っていたはずだ。
自分と同じだ、と思いながら、はしばらくエヴァの写真を眺めていた。
彼女の凛とした美しさが、自分を守り死んでいった母親イリーナの面影と、どこか重なるような気がして。
そこで初めて、母の死に疑問が沸いた。
(お母さんは…どうして狙われたんだろう…。ダンテのお母さんが裏切り者のスパーダが愛した女性だから殺されたんだとしたら…お母さんが殺されたのも同じような理由なのかな)
ダンテの話ではの父カーロは、スパーダの側近として一緒に悪魔達と戦ったという。
その後も魔界には戻らず、人間界に降り立ち、スパーダと一緒にこの世界を守り抜くと決めた。
当然その事を魔界の住人達が許すはずもない。スパーダと同様、"裏切り者"として敵視されてたようだ。
次々に襲ってくる悪魔達と戦いながら、カーロはいつしかスパーダと歩みを分かち、一人でフォルトゥナに残った。
そしてそこで悪魔と戦いながら、あの騎士団を作り上げた、というところか。
(そこで…お母さんと出逢ったのね…)
人間と悪魔。その決して許されない境界線を乗り越え、愛し合った両親を、は誇りに思った。
そしてその結果、生まれたのが自分なのだとしたら、たとえ人や悪魔から忌み嫌われる存在だとしても、何も恥じる事はない。
二人の意思を、自分が告げればそれもまた嬉しい事だ。
(ダンテもきっと同じ事を思ってる…)
ふと前で眠るダンテを見ながら、はかすかに微笑んだ。
ダンテは決して口には出さないが、悪魔を狩る事が自分の使命だと考えてるに違いない。
軽い男に見えて、そういうところはスパーダの意思を受け継いでいる、とは思っていた。
だからこそダンテと一緒に悪魔と戦おうと決めたのもある。
ただ、そこにバージルがいなかった事が、は少し残念だった。
ずっと探していた相手に、二度と会えないかもしれないと思えば、その思いも更に募る。
(…会いたいなあ。バージルに。会ってきちんとお礼が言いたいのに…)
と言って魔界に行くわけにもいかない。
ふとあの夜見せてくれたバージルの優しい笑顔を思い出しながら、はゆっくりと目を瞑った。
モリソンもその気配に気づいたのか、話しかけてくる事もせず、黙って運転に集中している。
静かな車内には、カーラジオから流れるEric Claptonのヒット曲"Wonderful tonight"がかすかに流れていて、それが子守唄のように聞こえた。
それはがまだ小さい頃、母イリーナが好きで良く聞いていたバラードだ。
夫であるカーロがよく口ずさんでいたと言って、時々イリーナがにも歌って聞かせてくれていた事を思い出す。
〜〜 夕暮れが迫り 彼女は何を着ようか迷っている メイクをし 長いブロンドの髪に櫛をかけ 私に尋ねる
「これで良いかしら?」 「大丈夫、今夜は特に素敵だよ」
最高の気分さ 君の瞳の中に 僕を想ってくれている 君の気持ちが見えるから
でも君は僕がどれだけ愛しているか 解ってくれているのかな 〜〜
(―――パパは…ママをとても愛してた…。ママもパパを心から愛してた…。そんな風に、私も誰かを愛せる?)
今は亡き母の思い出が浮かんでは消えるのを感じながら、は薄れゆく意識の中で、ふとそんな事を思っていた。
どれくらい、そうしていたのか。は急に息苦しさを感じて、一気に覚醒した。
「…っ…ふが…っ?」
「ぶははっ!」
目が覚めた、いや――――開けた瞬間。ダンテの綺麗な青い両眼が見下ろしていて、いきなり吹き出されたら誰だって驚くだろう。
さっきまで綺麗なバラードを聴きながら、母の面影を思い出し、心穏やかな眠りについたはずが、今、目の前で腹を抱えて笑っている一人の男のせいで台無しになった。
「な…何してんのよっ」
「はははっ…ぶっ…だってお前…なかなか目ぇ開けねえし、仕方ないから鼻摘まんだら変な声出すから…あはははっ」
「あははじゃない!」
あまりにムカつき、前に座るダンテの脳天をグーで殴ると、ごいんっという小気味いい音がした。
「いってえぇ。殴る事ねえだろがっ」
「うるさい!――――って、あれ?ここ…」
体を起こし窓の外を見れば、そこは最初の目的地である港だった。
時計を見れば午前2時。どうやら少し前に到着してたらしい。
「ったく…起こしてやったらコレだ…」
「あのね…もっとまともな起こし方、出来ないわけ?だいたい女の子の鼻を摘まむってありえない」
「誰が女の子、だって?」
「また殴られたいの?」
からかうように笑うダンテに殴る真似をすれば、そこに苦笑気味のモリソンが振り向いた。
「出発前からケンカをするなよ。――――ほら、これがチケットだ。あと20分ほどで出航する」
「あ、ありがとう…。え、これモリソンが用意してくれたの?」
モリソンから船のチケットを受け取り、は驚いて顔を上げる。
前から思っていたが、彼は何から何まで仕事が早い。
「ま、今回は関係ないが、これもクセでね。しっかり前準備をしてから送り出したい」
「…ホントにありがとう。あ、あの…帰ったらきちんと今夜の報酬は払うから」
すっかり世話になったモリソンにそう言いながら、当然のようにチケットを受け取りサッサと車を降りるダンテを睨む。
そんなにモリソンも笑いながら、「ま、それほど期待しないで待ってるよ」と肩を竦めた。
きっとオーナーの信用がないせいだ、と内心思いつつ、も船に乗る為、車を降りる。
「今日は凪だからボルゴには4時間するかしないかで到着する予定だそうだ。気をつけて行っておいで」
「ありがと。モリソンも帰りは気をつけてね」
「ああ、ありがとう。あまりダンテとケンカするなよ」
窓から手を振り、そう言うとモリソンは小さくクラクションを鳴らした。
も手を振りながら、走り去るモリソンを見送ると、すぐに前を歩くダンテを追いかける。
「ちょっと待ってよ!」
「早くしろよ。もう出航するらしいぜ」
ダンテはそう言いながらチケットを船員に見せ、先に船へと乗り込む。
もチケットを出しながら、目の前の船を見上げた。
この小型フェリーは、この港からボルゴまでノンストップで向かう船だ。
は三か月前、この船に乗ってこの港へ来た事を思い出した。
「私、三カ月前、これに乗ってこの港に来たの」
フェリーに乗り込み、甲板で海を眺めていたダンテの隣に立つと、まだ暗い海を眺める。
この港は24時間フェリーを走らせている為、いつもは客も多いが、今夜はダンテとを入れて他に5人程度と少なかった。
「たった三カ月でまた戻るなんて思わなかったけど」
「…悪魔ぶっ倒したら里帰りでもすりゃいいさ」
「…そうね。そうしようかな」
ふとシェスタやネロの顔を思い出し、そんな気持ちになる。
でもその前に真相を確かめなければならない。
「ダンテも行く?スパーダ…お父さんの思い出の地でもあるし、バージルも色々と見て回ってたみたいよ」
「…親父の、ねえ。ま、あんま興味ねえな。それより…美味い食いもんがあるなら考えてもいい」
「どーせダンテはピザしか食べないクセに」
呆れたように笑うに、ダンテは真顔で「確かにな」と頷く。
「ここを出る時は…バージル…あなたのお兄さんに会う事しか考えてなかったなぁ」
暗い海を眺めながら、がふと呟いた。
まるでその日の気持ちまで思い出したかのように、彼女の瞳は懐かしい面影を見ているような眼差しで夜の海を眺めている。
ダンテはそんなの横顔を見つめながら、ふと笑みを浮かべた。
「…の"好きな人"って…バージルだろ」
「…え?」
「さっきグロリアに言ってたろ?好きな人がいるって」
「……ああ…あれは…」
ダンテの言葉に、は俯きながら、苦笑いを浮かべる。
「ああ言わないとグロリアに誤解されたら困るでしょ」
「それだけか?好きだから、故郷も捨ててバージルを探しに来たんじゃないのかよ」
「…どうかな。もう一度、会いたいと思ったのは確かだけど…無理なんでしょ?」
はそう言いながら、少しだけ寂しそうな顔をする。
その顔を見てると、ダンテもそれ以上、何かを言うのは憚られる気がして、再び暗い海へと視線を戻した。
その時――――出航を告げる霧笛が、夜空に響き渡った。

「ふあぁぁぁ…」
船を下りたダンテは大欠伸をかましつつ、波に揺られ疲れていた体を思い切り伸ばした。
その姿を横目で見つつ、も小さく欠伸を噛み殺す。
移動中は多少眠れたものの、寝不足だった体を完全に休めたというほどではない。
逆に中途半端に寝たせいで、頭が妙に重たく感じた。
「…ここがボルゴって街か?意外と都会だな」
「まあ…私が住んでたフォルトゥナよりはね。若い子はみんなボルゴに出たがるわ」
「へえ…まあこの街からなら、どこへでも船で行けるし当然だろうな」
ダンテは港を見渡し、停船している数の多さに口笛を吹いた。
ボルゴはこの一帯では大きな港町であり、この港からあちこちの街へと船が出ている。
城砦都市であるフォルトゥナより、交通の便がいいのは明らかだった。
「んで…まずはどうする?その騎士長さんとやらを探すか?」
「そうね…。インチェ島に行くのも、この港から船を出すはずだから、ここへは立ち寄ったと思うの」
そう言いながら港を見渡す。
今は朝方の6時だからか、人もまばらで、見えるのは本職である漁師くらいのものだった。
「まずは聴き込み調査だな」
ダンテは背中にギターケースを担ぐと、そのまま漁師の方へと歩いて行く。
その後ろ姿を見ていると、どこかのミュージシャンにしか見えないが、あのケースの中には彼の大剣が密かに隠されている。
あの街では気にしないらしいが、地方へ出向く時は剣をむき出しにしていると何かとうるさいらしい。
当然も自分の剣はロングコートの中へと隠してある。
「おい!」
その時ダンテに大声で呼ばれ、は急いで走って行く。
ダンテはこれから漁に出かけようとしていた一人の漁師を捕まえ、話を聞いたようだ。
「このオッサンが一時間ほど前に、騎士らしい団体が船に乗ってくとこ見たってよ」
「え…ホントですか?」
網を抱えて船に乗ろうとする漁師にも思わず問いかけた。
その漁師――50代くらいの中年男だ――は「ああ、見たぜ」と言って、海の方へと指をさす。
「この辺で観光客相手にしてる奴の船でインチェ島の方へ向かった」
「一時間前…遅かったわ…」
海の方へ視線を向けながら、は溜息をついた。
サガロの事だ。太陽が昇り切る前に船を出させ、ちょうど朝日が昇る頃に向こうへ着いていたかったんだろう。
しかしまだ間に合う。
「そ、それであの…他にインチェ島へ船を出してくれる人に心当たりとかありませんか?」
「インチェ島に?あんたも物好きだな。あんな物騒な島、騎士の人しか近づかないってのに」
「どうしても行きたいの。誰か知り合いとかいません?」
訝しげな顔をする男を無視し、もう一度尋ねてみる。
そこへダンテも苦笑交じりで歩いてくると、「船を出してくれそうな奴を紹介するだけでいい」と、少しばかりその男に金を握らせた。
「へへ…悪いな兄ちゃん」
金を握らせた事で気分を良くしたのか、男は「ちょっと待ってな」と言って港を抜け、目の前にある通りへと走って行く。
男はその通りにあるカフェの中へと入って行った。目当ての人物はそこにいるのだろう。
その姿を見送りながら、は小さく息を吐き出す。
平気なようでいて、やはり先に島へと向かったサガロ達の事が心配だった。
目的地を目の前にして、気ばかりが焦っている自分に気付き、はふと苦笑いを零す。
「ありがとう…お金なんて思いつかなかったわ」
「別に。あんたは今まで真っ当な生き方してきたんだ。悪魔の事には詳しくても裏の人間相手は慣れてねえだろ?」
ダンテは肩を竦め笑った。
「ああいう奴の相手は俺に任せて、は騎士長さんの心配でもしてろよ」
そう言いながらの頭をぐりぐり撫でると、ダンテはカフェから出て来た男の方へと歩いて行く。
事務所を構えたのは最近らしいが、ダンテはそれ以前から偽名で便利屋のような事をしていたという。
だからこそ情報を聞き出したり、どう行動すれば自分にとって有利になるかというやり方を自然と覚えたのかもしれない。
ダンテが漁師の後ろから歩いてきた男と交渉している姿を眺めながら、結構頼りになるじゃない、とも笑みを浮かべた。
「―――おい、いたぜ!船出してくれる奴!」
ダンテはそう叫びながら先ほどの男と、もう一人見知らぬ男を連れて戻って来た。
漁師の紹介してくれた男はベンと名乗り、この辺では観光客を色々な場所へと案内したりもしているらしい。
それも裏稼業では金次第で危険な地域に船を出す事もあるという事で、やダンテにとっては持ってこいの船頭だった。
「ならインチェ島に今すぐ連れて行って欲しいんだけど」
「OK、いいぜ。ただ…」
「何?お金ならちゃんと払うわ」
何か言いたげな様子に、もお金を出そうとする。しかしベンは軽く首を振って肩を竦めた。
「いや、そうじゃなくて同じ場所に連れてけっていう姉ちゃんがいるんですよ。一緒に乗せてやってくれたら俺としても助かるんですが」
「姉ちゃん?インチェ島に?」
あんな呪われた島に行きたいと言う人物がまだいるのか、とが訝しげな顔でダンテを見る。
その時、背後から「遅かったじゃない?」と言う、明るい女の声が聞こえた。
「―――レディ!お前かよ」
ダンテの驚く声と共に、はカフェから一人の少女が歩いてくるのを見て、うんざりしたように息を吐き出した。
彼女の存在をすっかり忘れていたのだ。
そもそもダンテにこの話を持ってきたのは彼女だったのだから、今ここにいてもおかしくはない。
「現地集合じゃなかったのかよ」
歩いてきたレディにダンテはそう言いながら両手を広げる。
レディは溜息交じりで肩を竦め、「何だか中世の騎士みたいな一団に会ってね」と苦笑いを零した。
「ちょうど船を調達しようとしてたら彼らと鉢合わせになって危険だからって止められちゃったの」
「…サガロ達だわ」
が呟くと、レディは改めて視線を彼女の方へ向けた。
「夕べはどうも。あなたも来たのね。えーと…」
「……よ」
「そうそうね。私は…レディでいいわ、この際」
レディはそう言いながら笑うと、ダンテをちらりと見た。
まるでこの子は大丈夫?と問うような顔だ。その態度にはいささかムッとはしたものの、敢えて気付かないフリをしておく。
「はこの辺の出身で島にも詳しい。今回、の知り合いも絡んでるかもしれないしな。腕もいいぜ」
「あら、そうなの」
レディは少々意外といった表情を浮かべたが、敢えて口にはせず、ベンに船へと案内させている。
その後からダンテとも着いて行く。太陽は上がったものの、空はどんよりとした雲や霧が一面を覆って薄暗く感じた。
「インチェ島までは30分くらいで着きまさぁ。まあ今日は曇ってるから見えにくいが近くに来たら向こうの方角に見えてくるから、すーぐ分かりますよ」
ベンは操舵室から顔を出し、太陽とは逆の方向を指差す。
ダンテとレディはその方向へ視線を向け、薄暗い雲に覆われた影を見つめた。
確かに悪魔が出没すると言われるのが分かるほど、陰気な雰囲気ではある。
も島の方角へ目を向けながら、その重い空気を感じていた。
「しかし珍しい。時々怖いもの知らずな客がインチェ島に連れてけと来ますけど、こんなに立て続けに来たのは初めてですよ」
ベンは慣れた手つきで操縦しながら苦笑している。
「最近は特に嫌な噂も多くて誰も近寄りたがらない。漁師さえもね」
「…それは死んだ人間がウロついてるからか?」
ダンテが笑いながら肩を竦めると、ベンは青い顔で振り向いた。
「それ知ってて行くんですかい?」
「それ目当てで行くんだよ」
ダンテの一言に、ベンは驚いたような顔をした後、やれやれといった様子で息を吐く。
「もしかしてデビルハンターって奴ですかい?」
「良く分かるな」
「そういう裏稼業の人じゃなければ、あんな場所に好き好んで行く奴はいませんからね」
「で、当然出るんでしょう?」
そこでレディも話に加わる。
「今は女のハンターもいるんですねえ」
と、ベンは首を振りながら軽く肩を竦めた。
「もちろん出るって噂ですよ。夜にあの島へ近づくと、空をふわふわ飛んでる悪魔がいただの、ぼんやり首のようなものが飛んでいただの目撃証言は沢山あります」
ベンは軽く身震いする仕草で顔をしかめた。
「ま、俺としても関わりたくはないが生活もあるんで近くまで運ぶだけの仕事をしてるんですよ。もちろん昼間だけですがね」
そう言いながらベンはふと思い出したように三人の方を見た。
「そういや…ハンターさんならインチェ島には当然下りるんですよね」
「そりゃそうだ」
「なら準備はしてきましたかい?」
「準備…?」
ベンの言葉にダンテとレディも首を傾げる。しかしだけは「ええ、もちろん」と軽く頷いた。
「何の事?」
意味が分からず、レディがの方を見れば、彼女は手にしていた小さなバッグを持ちあげて見せた。
「インチェ島に行くには手ぶらじゃちょっときついの」
「…きつい?」
「そうでさあ。あの島はどういうわけか一年中、真夏のような暑さらしくてね。あの島の周りだけは海もぬるま湯のように暖かい」
「おいおい聞いてねえぞ」
ダンテが抗議の声を上げたが、は澄ました顔で「大丈夫よ、用意してきたから」と手にしたミニバッグをダンテに放る。
つかさず中を見てみれば、そこには大量のミネラルウォーターが入っていた。
「水がないと一日と持たないくらい暑いの。と言ってもソレ、二人分しか用意してないわ。あなたが来るの知らなくて」
はそう言ってレディへと視線を送る。当然何も用意して来なかったレディは小さく舌打ちをした。
「大丈夫ですよ。そんな事もあるんで俺が予備で持ってる水を売ってあげますから」
「それも商売ってわけ?大したものね」
ベンの言葉にレディも苦笑いを零すと、仕方ないといった顔で水を買っている。
そうこうしている内に、インチェ島へと近づいたのか、一気に気温が上がってくるのが分かり、ダンテは溜息をついた。
「暑いの苦手なんだよな…」
「そのコートの下、何も着てないんだからいいじゃない」
「そりゃそうだけどよ…」
の突っ込みにダンテは情けない顔で項垂れる。といって引き返すと言う選択肢は当然ないのだ。
「ああ、ほら。もうすぐ着きますよ」
ベンの言葉に三人が顔を上げると、先ほどは霧の中に隠れていた島の全貌が目の前に現れた。
「なるほど、ね。確かに不気味だ」
ダンテは島を眺めながら、口元を歪める。黒い木々に覆われたインチェ島はその気温の高さか、全体が蜃気楼に包まれてぼやけて見える。
それが一層、その島を不気味に見せていた。
「こんなに暗くちゃ昼なのか夜なのか分かんねえな…マジであちぃし」
「ま、でもサッサと済ませればいいだけの話よ。―――行きましょ」
ベンがギリギリまで船を寄せると、三人は一気に島へと飛び降りた。
その砂浜さえ、熱を持っていて熱く感じる。
「じゃあ俺は明日の朝、またこの辺まで迎えに来ます。でも一時間待って皆さんが現われなかったら――――」
「ええ、帰っていいわ」
レディは楽しげにそう言うと、ベンは軽く頭を下げて操舵室の中へと消えた。
「さて、と。どこから探索する?」
レディは自らの武器、カリーナ・アンをケースから出して背負うと、ダンテとを振り返る。
二人も武器の準備は万端で、ダンテもギターケースから大剣リべリオンを出すと徐にそれを背負った。
「こっちよ」
は手に<イリーナ>を握ると、二人を促し崖に近い浜辺を指差した。
そこには森へと続く細い獣道がある。
辺りに無数の足跡があるのは、多分サガロ達だろうとは思った。
「あら。も銃と剣、両方使うのね」
の後から着いて行きながら、レディは彼女の背負うカリバーンと手にしている銃に目を止め、微笑んだ。
「ええ…いけない?」
「いいえ。そういうつもりじゃないわ。ただ…その細腕で振るうには大きな剣だなあと思っただけ」
「……何が言いたいの?」
いちいち癇に障るレディの物言いにこれまで我慢してきたが、とうとう苛立ちが頂点に達しては立ち止まった。
その雰囲気を察したのか、ダンテが慌てて間に入る。
「こんなとこでモメんじゃねえよ」
「ダンテはあっち行ってて。この子、私に文句があるみたいだから」
はそう言いながら、目の前のレディを睨む。レディは僅かに目を細めながら、
「そうね。ダンテはあっちに行ってて。邪魔よ」
「……あのな。今は内輪モメしてる場合じゃ―――」
「「ダンテは黙ってて!」」
いきなり女二人から怒鳴られ、さすがのダンテも口を閉じる。
いつもの調子でしゃべりまくれば体に無数の穴が空くかもしれない。
例えそれで死ななくても、痛い事は痛いので、それを避ける為、ダンテは大人しく後ろへ下がり、大きな木の下へと腰を下ろした。
「ったく…女が集まるとコレだ…何で俺の周りには凶暴な女しかいねえんだ…?」
頭を掻きつつ自身の女運のなさを呪う。
出来れば仲良くしてほしいと願うダンテの気持ちも届かず、とレディは険悪なムードの中向き合っていた。
「あなた初対面から気に入らなかったのよ」
「あら、それは失礼。気付かなかったわ」
「文句があるならハッキリ言えば?」
「文句なんてないわ。ただ…ダンテの相棒になる人に興味はあるけど」
レディの意味深な言い方に、は僅かに眉を寄せ、その言葉の意味を探る。
そして一つの答えに行きついた時、は思わず噴き出していた。
「やだ…そうだったの?」
「……は?」
険悪だったはずが、いきなり笑いだしたに、レディも訝しげな顔をする。
はそれでも構わず肩を竦めると、後ろに座っているダンテに視線を向けた。
「そうなら言ってくれればいいのに」
「…何言ってるの…?」
「だから私はダンテとはただの仕事仲間であって、あなたが考えてるような関係じゃ――――」
「ちょ、ちょっと待って!話が見えないんだけど…」
一人で完結しようとするに、レディも慌てたように口をはさむ。
何となく嫌な予感がしたのだ。
そして案の定、はキョトンとした顔でレディを見ると、
「え、だからレディはダンテの事、好きなんでしょう?」
「……はあ?!」
の突拍子もない結論に、さすがのレディも青くなった。どうやら嫌な予感は当たってたらしい。
「あ、あのね…私はそう言うつもりで言ったんじゃないわ!誰があんな奴!」
レディは目を剥いてそう言うと、後ろで笑いを噛み殺しているダンテを思い切り睨んだ。
しかしだけは意味が分からないといった顔で首を傾げている。
「え、だってダンテの相棒に興味があるって…」
「だからそれは…!あ、あなたが普通の…その…神経の持ち主ならダンテの相棒にはならないでしょ?だからその正体に興味があるって意味よ!」
「正体……」
その言葉ではふとダンテを見た。ダンテは意味深な笑みを浮かべながら心底楽しそうな顔をしている。
そしては思い出した。レディがダンテの正体を知っている事を。
「あ…そういう、事」
「……何?やっぱりそうなの?」
この場合"そうなの?"とは、あなたもそうなの?という意味だろう。
はようやくレディの考えてる事を察し、軽くふきだした。
「やだ、そっちか」
「……笑ってないで答えなさいよ」
「おいレディ…。今そんな話いいだろ?」
女同士のバトルに飽きたのか、ダンテは欠伸をしながら立ち上がる。
しかし再びジロリと睨まれ、無言のまま肩を竦めた。本当に女運がないと言いたげだ。
「そうね…。まあ…ご想像に任せるわ」
「何ですって?」
「そんなのいいじゃない?私はダンテの相棒であり味方なんだから。何も心配するような事はないし」
「……それって答えと受け取っていいのかしら」
の態度にレディは目を細める。は溜息交じりで頭を掻くと、銃を持つ手を僅かに持ち上げて見せた。
「そう思うなら思えば?それに私はレディ、あなたに殺意もないし戦う気もないの。分かるでしょ?あなたが私を嫌いでも―――」
がそう言いかけた時だった。突然静かな浜辺にガァァンという銃声が響く。
それはダンテが発砲したエボニ―の銃声だった。
「、レディ!ケンカは後だ!―――早速ご登場らしいぜ!」
その言葉と同時にもイリーナを抜き、背後に浮いている頭部のような浮遊物を撃ち抜く。
突然現れた悪魔は、気付けば三人の周りを囲むようにふわふわと飛んでいた。
「何こいつら!どっから現れたのよ!」
レディも短銃で応戦しながら、と背中を預け合う。
も次々に飛んでくる悪魔を撃ち落とし、「たった今沸いて出たのよ」と笑った。
「お前らのわめく声がうるさくて出て来たんだろ!」
赤いコートを翻し、跳躍すると、ダンテは二丁の銃を激しく連射し、辺りに飛んでいる悪魔をハチの巣状態で打ち抜く。
撃たれた頭部は破裂し、黒い塵となって空気に消えた。
「つーか、これ何だ?カボチャか?ハロウィンパーティかよ…」
「が呼んだんでしょ!」
「ちょっとレディ!それ笑えないわ」
確かにさっきから浮遊している悪魔は、ハロウィンで見かけるようなカボチャにも良く似た形態をしている。
だがケタケタと笑い声をあげているカボチャなど見た事がない。
「観賞用にも食用にもならないって感じね!」
「俺はもうパンプキンパイは食わねえ」
「いっつもピザしか食べないでしょ」
三人三様、そんな軽口を叩き銃を連射しながら、飛んでくる悪魔を撃ち抜いて行く。
しかしダンテは何も攻撃してこないその悪魔達に違和感を感じ、「気をつけろよ二人とも」と辺りの気配を探った。
その時、三体ほどの悪魔がダンテの頭部目がけて飛んで来る。
「…まるでバッティングセンターのカボチャ版だな」
ダンテは笑いながら呟くと、一気に大木の側面を走り抜ける。
そして悪魔が飛んできた手前で身を翻すと、足だけ伸ばして悪魔を蹴り飛ばした。
まるでオーバーヘッドだ、と横目で見ていたは思う。
ダンテはそのまま何度か回転しながら、次々にカボチャのような悪魔を蹴り飛ばし、「ゴール!!」とおどけたように叫んだ。
「……サッカー少年かっての」
悪魔を撃ちながらレディが苦笑し、もそれにつられて笑う。
二人の間にあった、さっきまでの険悪なムードは綺麗さっぱり消えていた。
「ダンテの相棒なんて苦労するわよ」
「…苦労ならすでにしてるわ」
「あら可愛そう」
そんな会話を交わしつつ、飛んできた悪魔を全て塵へと変えた。
その時、「た、助けてくれ…え…!」という掠れた声が聞こえて、とレディは小さく息を呑んだ。
「Jesus!カボチャがしゃべった」
悪魔を蹴り飛ばし終えたダンテは見事に着地すると、目の前にフラフラ歩いてきた物体に目を細める。
その異様な姿に、いや格好にどうしたものかとの方へ視線を向けた。
「おい、もしかしてコレ――――」
「嘘…その人…騎士団の人だわ…」
「何ですって?」
唖然としたように呟くに、レディとダンテも目を見張る。
三人の目の前に歩いてきた人物は、頭は先ほどのカボチャだが、体は白い騎士服を着ていたのだ。
「た…たす…け…」
≪ケケケ…!≫
カボチャのような悪魔に頭部を乗っ取られたのか、その人物は左右にフラつきながら三人の方へ歩いて来る。
その間も悪魔は気味の悪い笑い声をあげ、ムシャムシャという奇妙な音を立てていた。
「……うげ。コイツまさか…」
「まさかじゃなくて……食べてるわね、間違いなく」
「そんな…」
ダンテとレディが思い切り顔をしかめる。頭に被っている悪魔は、その人間の頭部を丸ごと食べているようだ。
それでも歩けると言う事は乗っ取った体を動かせると言う事だろう。
「…これじゃ助けられない…」
「諦めろ、。こいつは動いてるが本人の意思じゃねえぞ」
「…そうね。って事はさっき飛んでたカボチャに頭乗っ取られたら――――」
「ああ…俺達も頭から丸ごと食われんな」
ダンテの一言に、知らないで戦っていたとレディはゾっとしたように顔を見合わせた。
「―――おい、、レディ…気をつけろ。囲まれた」
ダンテの一言に頭上を見上げると、さっきの悪魔が倍の数ほど浮遊しているのが見えて、
とレディは同時にトリガーを引いた――――。
<<< □ >>>