code:06 / A party
"インチェララッカーレ島"―――そこは森の奥へ行けばいくほどに熱帯雨林のような暑さだった。
少し動くだけで息苦しさを感じ、大量に汗が噴き出してくる。
この島の海底にマグマでもあんのか?とダンテは首を傾げながらも、飛んでくる悪魔を交わし、銃を連射していった。
そして何十体目かの悪魔を撃ち抜き、地面に着地したダンテは自分の小さなミスに気付き、銃を持っている手を肩に乗せると盛大な溜息をつく。
「どうやら――――二人とはぐれちまったみたいだな」
その呟きと同時に、休息を邪魔された野鳥が一気に木々の合間から飛び去って行った。

島へ着いたのと同時に、おかしな形態の悪魔に襲われ、戦闘になったのはいいとして。
その数の多さに固まって戦うより散らばった方が早いと、それぞれ好き勝手に戦いだした。
浮遊する悪魔には剣より銃の方が反応しやすい。
三人はある程度、互いの距離をあけながら、飛び交う悪魔を撃ち抜いて行った。
当然ダンテも得意の身軽さを生かし、跳躍しながら悪魔を的に銃撃戦を楽しんでいたのだが、木々を足場にしながら移動した結果、少々深追いしすぎたらしい。
気付けばとレディの姿はなく、ダンテは一人、森の奥へと入って来てしまったようだ。
「……ったく、どこだよ、ここ」
とりあえず出て来た悪魔は全て倒した後、辺りの景色を見渡した。
普通の森とは違い、どこかのジャングルかと思うような植物ばかりなのは、きっとこの気温のせいだろう。
「……しっかし熱ちぃな。気がつきゃ達もいねえし、ったくマジでついてねえ」
近くにあった切り株に腰をおろし、ダンテは持っていた愛銃アイボリーで後頭部を掻く。
別に一人でもどうって事はないのだが、この気温に耐え得る為に必要な物を、が殆ど持っているのだ。
「食いもんと水はコレだけか……」
ダンテはギターケースに無造作に突っ込んでいたミネラルウォーターのボトル二本と、先ほど食べようとから受け取っていた一つのハンバーガーを眺める。
フェリーの中で一気に食べ――チキンやフィッシュなどとバラエティにとんでいた――残るはこの島に着いてからと思っていた。
しかし先ほど、歩きながら食べようとして受け取ったのはこのトマトチーズバーガーのみ。(味がピザに似ている事から、ハンバーガーの中では一番の好物)
あげく一番大切な水はこれ二本だけとくれば、ダンテも少々不安になる。こうしている間も、この島特有の暑さで、やたらと喉が渇いてくるのだ。
「チッ。これじゃゾンビと会う前に干物になっちまうぜ」
そうボヤきながら、ダンテは水を一口飲む。辺りは静かで、銃声などは全く聞こえてこない。
二人が今どこで何をしているのか、ダンテはそちらも心配ではあった。
「……あの二人……大丈夫だろうな…」
この場合、大丈夫かというのは何も二人が悪魔にやられるという心配ではなかった。
あの二人がそれなりに腕があるのは知っているし、雑魚にやられるとも思っていない。
ダンテの心配はただ一つ。またケンカをしていないか、という事だけだった。
「女のケンカは悪魔より恐ろしいからな」
先ほどの険悪なムードを思い出し、ダンテは苦笑すると、水と唯一の食料であるハンバーガーをギターケースへと戻す。
その際、中にギターのような形状の物が光ったが、その禍々しい形態は当然楽器ではない。
リべリオンはすでに背負っている為、全く別の武器である。
普段は二丁の拳銃と大剣しかもたないダンテだが、今回の依頼を受けた時、ふと気まぐれで持って来たものだ。
先日、兄バージルと戦う為に向かった塔で出逢った悪魔が魔具になったもので、どちらかと言えば周りを敵に囲まれた時、使い勝手がいい武器でもある。
「ま、さっきのカボチャ頭が出たら、今度はお前でも使うか。――――って、そういやお前も"女"だったな」
ダンテは苦笑交じりでケースの中の"武器"に話しかけると、徐にジッパーを閉じた。
「さて、と――――マイ・ハニー達が寂しがってケンカしないうちに合流でもすっか」
軽快に立ちあがってギターケースを背負うと、ダンテは一人楽しげに鼻歌を歌いながら、鬱蒼とした森の中を歩き出した。

その頃、ダンテが言うところの"マイ・ハニー達"――二人からは苦情がきそうだが――は、彼の不安をよそにケンカをするどころかすっかり意気投合し、仲良く悪魔を全滅させていた。
「ったら、なかなかやるじゃない。剣の腕も見事なものだし」
「あら、レディの銃さばきも大したものだわ」
「さっきのエンジン音みたいのは?」
「これはイクシードって言って、中に推進剤噴射装置がついてるの。このクラッチレバーを握ると噴射剤が出て剣撃の威力が上がる仕掛けよ」
「えーすっごーい!ちょっと欲しいかも!でもかなりの重量なのに良く振れるわねえ。さすが元騎士ってところかしら」
「10歳からコレ振ってるんだもの。慣れよ慣れ。レディこそ、そのミサイルランチャーを軽々と扱うんだもの。驚いちゃったわ」
綺麗さっぱり悪魔が消えてしまった森を見渡しながら、互いに褒め合う。
この場にダンテがいたならば、ゾっとするような光景だったかもしれない。
「でも同じ歳だったなんてねー」
「ホーント。レディは年下かと思ってたわ」
「やだ、私もの方が年下だと思ってたのよ」
お互い年下だと思っていた事で二人は苦笑いを零すと、近くの岩場に腰をおろし、暴れた事で渇いた喉を水で潤した。
二人がいるのは未だ砂浜からほど近い森の入口付近であり、ダンテがどれほど移動したのか分かるというものだ。
「ところでダンテ、どこまで行ったのかな」
悪魔も恐れ戦き(?)顔を見せなくなった事から女同士の話――主にダンテの悪口(!)――に花を咲かせ、たっぷり10分は過ぎたかという頃。
は己の雇い主兼相棒が一向に姿を見せない事に気付き、辺りを見渡した。
「もしかして先に森の奥まで行っちゃってるかもよ」
「え、まさか…道も分からないのに?」
「あいつは本能のまま動くから。最初に"テメンニグル"で会った時も先にサッサと行っちゃったし」
レディはそう言いながら軽く肩を竦めたが、はその名が出た事で、ふと顔を上げた。
「テメンニグル…」
「あ〜聞いてない?私とあいつが最初に会った――――」
「魔界への道を開く為の塔…でしょ?前にもその話は聞いてたけど、あなたの事は昨日詳しく教えてもらったの」
「……そっか。じゃあ私の"家庭事情"ってやつも知ってるのね」
レディは肩を竦めて笑うと、どんよりと曇っている空を仰いだ。
その横顔はどことなく寂しげで、はふとダンテから聞いた彼女の父親の事を思い出す。
自分の妻、そしてレディの母親でもある女性を殺した父親。その父親に復讐を誓い、実行した娘。
レディもまた、数奇な運命に翻弄されているとは思った。
「は……あいつのお兄さんと会って"Devil May Cry"に来たんですってね」
「え?あ……うんまあ」
不意にその話を持ち出され、ドキリとした顔でレディを見る。レディは空を見上げたまま、かすかに微笑んだ。
「私も少しはダンテに聞いたのよ。のこと…。あの人がダンテの名前を騙ってたなんて驚いたけど」
「あ…そっか。レディはバージルに会った事、あるんだっけ」
「まあね。最初は私の父…ア―カムを唆した張本人だと聞かされ殺しに行ったわ。でも…全く逆だった。ア―カムがバージルを唆してたのよね」
自嘲気味に笑うレディに、は何も言わず微笑む。
自分の父親を名前で呼ぶ彼女に、どこか物悲しさを感じたのだ。
そんなに気付き、レディもまたかすかに笑みを浮かべた。
「最初にバージルと対峙した時は冷静でとても冷たい男に見えたけど……違うのかもね」
「…え?」
「って思ったのも、との事を聞いてからなんだけど。――――あなたの事、悪魔から助けたんでしょ?」
「そんな事まで話したの?おしゃべりな相棒だわ」
「ダンテからおしゃべりとったら、ただのピザ好きな悪魔じゃない?」
「そこにストロベリーサンデーとロックも足せるわよ?」
の言葉にレディも思わず噴き出す。ダンテも今頃どこかでクシャミをしているかもしれない。
「彼……バージルは不器用な人だったと思うの」
「不器用?」
ふとが呟き、レディは首を軽く傾げた。
「一緒にいた時間はほんの短いものだったけど……今なら分かる気がするの。何故バージルがそんなにも魔界を求めたのか…」
「自分の父親であるスパーダの力が欲しかったんじゃないの?」
「それも確かにあるんだろうけど…彼は自分の居場所が欲しかったんじゃないかな…。自らの力を持て余して、どうしようも出来ない苛立ちを魔界へ行く事で消したかったんだと思う」
そう話しながら、はあの夜バージルが遺跡の前で見せた悲しげな表情を思い出していた。
バージルは魔界へ行く前に、この世界で唯一、父親を感じられる場所を見ておきたかったのかもしれない。
父の志とは逆の道へ進む為。たった一人の肉親である弟のダンテに、戦いを挑む前に。
「ダンテがね、チラっと話してくれたの。バージルと戦う前、自分の存在価値が見出せなくて、力を持て余して、毎日イラついてたって。
その苛立ちを目の前に現れる悪魔にぶつけながら、いつ死んでもいいと思ってたって。それ聞いて思ったの。
同じ存在であるバージルも…もしかしたら同じような苛立ちを持ってたのかもしれない。ただダンテとは違う方向へ向かってしまっただけなんだって」
偉大なる父を持ち、普通ではない力を与えられ、その代償に愛する母親を失った二人。
一つの命を分かち合い、同じ顔を分かち合ってこの世に生まれても、その心だけは分かち合えなかった兄と弟の結末は、悲しい永久の別れだった。
あの二人が力を貸し合えば、きっと最強のデビルハンターになれたんだろうな、とは少し寂しく思っていた。
「は……バージルの事が好きなのね」
「……す、好きっていうか…私の人生を変えてくれた人だから…とても大切な存在なのよ」
「大切な存在、か」
「……だって彼と会ってなければ私は今ここにいないと思うわ。色んな意味で」
はそう言いながら、軽く肩を竦めた。そして再び銃を空中へと向ける。
同じくレディも自らの武器、カリーナ・アンを抱え、前方へと向けた。その先には、先ほど現れたのと同じ悪魔が浮遊している。
「おしゃべりはおしまい――――」
「第二ラウンド、開始って事ね!」
二人は楽しげに笑うと、武器を構え浮遊してくる悪魔へと勢い良く発砲した。

次第に深くなっていく森の中をどれくらい歩いたのか。ダンテはある物を見つけて足を止めた。
「……Oops!驚いたな…こりゃ親父じゃねえか」
大げさに両手を広げ、声を上げる。ダンテの行く手を塞ぐように建っていた物。
それは紛れもなく、彼の父親であり、魔剣士と称えられたスパーダの石像だった。
「この辺で崇められてるって話は本当みたいだな」
彼の名と同じ大剣"スパーダ"を天に掲げ、堂々と建っている石像を見上げながら、ダンテは苦笑いを零す。
ただ随分と前に建てられたのか、石像には傍に生えている木々からの枝が絡まり、ぐるりとその体を巻かれていた。
その状態が、いかにも"封印"を現しているかのようにも見えて、ダンテは皮肉めいた表情で肩を竦める。
「……誰が建てたのかは知らねえが…この先に何かがいるってのは確かみたいだ」
二メートルはあるかと思われるその石像は、ここから先は立ち入るべからず、というように道を塞いでいる。
その後ろには大きな洞窟があり、トンネルみたいに通り抜けられるようになっていた。
「フン……確かに"匂う"な。こっから奥は封印地帯ってか?」
ダンテは何度も嗅いだ事のある臭気に気付き顔を顰めた。それは悪魔特有の悪臭といっていい。
歩いている時から薄っすらと匂ってはいたが、ここへ来てそれが更に色濃くなっている。
この先には確実に何体かの悪魔が封印されてると思って間違いないだろう。そしてその悪臭に導かれ、やってくる輩も。
「ったく……とレディはいったい何してんだ?メインは俺がもらっちまうぞ」
なかなか追いつかない二人に文句を言いながらも、ダンテはその手にリべリオンを握りしめると、石像の周りにある草や枝を斬り払った。
そうする事で後ろにある洞窟へ何とか進めるようにする。
他にも小さい規模ではあるが人が通った痕跡があるのは、大方のいう騎士団達だろう。
ここまで辿り着いた人間がいると言う事は、先ほどのカボチャに全滅させられたわけではないらしい。
「しっかし暑ちぃな……。どうなってんだ?この島は!太陽だって隠れてるってのに参るぜ……」
森の奥に進むにつれ気温が上昇しているとは感じていたが、この場所は暑いどころの話ではなかった。
雲に覆われ太陽など見えず、まるで夕方のような暗さなのに、炎に囲まれているような、そんな錯覚に陥るほどの熱がダンテを襲う。
いくら素肌にコートとはいえ、そのコートも革で出来ている為、何の慰めにもならない。
「こう暑くちゃ喉が渇いて仕方ねえ」
顎に伝う汗を手の甲で拭いながら、ダンテは洞窟の前まで大股で歩いて行く。
が、その中へ一歩足を踏み出そうとした瞬間、バチッっと見えない力に弾き返された。
軽く舌打ちして良く良く見れば、洞窟の入り口には赤いクモの巣のような結界が張られている。
そして同時に悪臭が更に濃くなった事で、ダンテは溜息をついて大剣を抜き肩に乗せた。
「……わざわざお出迎えか?丁寧なこったな」
苦笑交じりで振り向き、担いでいたギターケースを無造作に置く。
そして中から水を取りだし、それを一気に飲み干した。ついでに一つだけあったハンバーガーを手に立ち上がる。
目の前には先ほどの悪魔が大量に浮遊しながら、ケタケタと不気味な笑い声をあげていた。
「散々暑い中を歩かされて腹減ってんだ。これ食い終わるまで待って――――くれるわけねえか!」
ダンテは空になったペットボトルを放り、ハンバーガーを口に咥えると、一気に跳躍し空中へと舞う。
そして素早い動作で二丁拳銃の引鉄を引いた。
普通では考えられないほどの速さで無数に連射されるその銃撃で十体ほどの悪魔が消滅する。
拳銃でこれほどの連射が出来る人間はそうそういない。悪魔の血を引くダンテだからこそ出来る芸当だ。
ダンテはそのまま大木を足場に、更に上へと飛びあがり、他の悪魔へも発砲した。
一体、二体、三体、とカボチャのような頭部が次々に塵へと変わり消滅していく。
先ほども思った事だが、その悪魔はふわふわと飛ぶだけで目立った攻撃はしてこない。
もしかしたら、これで油断を誘っているのかもしれないな、とダンテは思った。
確かにすばしっこくはあるが、油断せず、それなりに注意を払って回避すれば、あの騎士のように頭部を乗っ取られる心配はなさそうだ。
「それにしても手ごたえがねえな……」
軽く地面へ着地したダンテは、咥えたハンバーガーを頬張りながら銃を握る手を肩に乗せ溜息をついた。
だが同時に残った悪魔達が再びケタケタと笑いだし、ダンテは最後の一口を口に放り込むと、素早く照準を悪魔へと合わせる。
「さっきから気に入らねえんだよ。その笑い声が癇に障るぜ」
忌々しげに呟くダンテを更に煽るように、悪魔達が一斉に笑いだす。
そして突然スーッと音もなく森の奥へと飛んで行った。
「逃げる気か?そうはいかねえ」
ダンテも追うように跳躍して大木の太い枝へと飛び乗ると、すぐさま銃口を悪魔に向ける。
だが引鉄を引こうとしたその時。悪魔の飛んで行った方向がぼんやりと明るく光るのが見えて、ダンテは僅かに眉を顰めた。
薄暗い森の奥がほんのりとオレンジ色に光っている。それも一つ二つではなく、徐々に数が増えて行った。
「……ハッ!やっとこ本体のご登場――――つーか、こりゃマジでハロウィンパーティって感じだな」
ゆっくりと自分の方へ近づいてくる光を見て、ダンテが楽しげに声を上げる。
目の前に姿を現したのがどうやらカボチャの本体らしい。
先ほど飛んで行った頭部が淡い光を放っていて、それを本体らしき体が腕に抱えている。
体はトカゲのような形態をしていた。
しかし中に数体ほど悪魔とは明らかに違う、人間の体がある事に気付く。
ダンテは徐に顔を顰めると、エボニー&アイボリーを指で軽く回転させ、慣れた動作でホルスターへと収めた。
「そういや食った人間の体を乗っ取って操れるんだったな……。ったく、やりづれぇ」
フラフラと歩いてくる中に、騎士服を身につけた悪魔がいる事に気付き、ダンテは小さく舌打ちをして枝から枝へと飛び移る。
悪魔に憑かれ体を乗っ取られた者を助けるすべはない。元は人間だとしても悪魔として処理しなければいけないのだ。
ダンテもそれを理解してはいるし今までも何度かそういった"元人間"の悪魔を葬って来た。
しかし、だからといって気持ち良く殺せるかと言えば、答えはNOだった。
己の野望の為、人間である事を捨て、自ら悪魔になったレディの父、"ア―カム"の時とは違う。
彼らは自分の意思とは関係なく肉体を乗っ取られ、精神までもが悪魔に操られてしまうのだ。
それを思えば、慕っていた騎士長ミハエルを悪魔に乗っ取られたの辛さが、ダンテには分かる気がした。
(こいつらもが話してた悪魔と同類種って事か?……にしては聞いてた姿形とは違う気がするが……)
どっちにしろ数が多くて面倒だ。徐々に増えていく悪魔達に、ダンテは溜息をついた。
「やっぱ"アレ"を使うか」
最後の枝から石像のある場所へ飛び降りると、ダンテは身軽な動作で着地して、置きっぱなしだったギターケースを足に引っ掛け宙へと放る。
それを素早く手でキャッチしてジッパーを下ろすのと同時に、中に入っていた物を肩から担いだ。
ギュイッィン!
まるでエレキギターのような騒音が静かな森に響き渡り、その音を確かめたダンテはニヤリと笑みを浮かべた。
コレを使うのはア―カムとの戦闘以来だ。
「チューニングもOKだ。いい音、鳴らせよ?」
≪……了解。あなたの好きにして≫
どこからともなく聞こえた女の艶のある声。それはダンテが肩から提げている魔具から響いてくるようだった。
紫色の禍々しい光を放つソレは一見ギターのようにも見える。
だがこれもれっきとした武器であり、前にダンテが倒した女の悪魔が魔具になったもの―――その名も"ネヴァン"。
常にコウモリをその身にまとい電撃を操る女悪魔は、ダンテに敗れた後、屈服するかのように、自らを武器へと変貌させたのだ。
「――――Let'Lock!BABY」
ダンテはそう叫ぶのと同時に"ネヴァン"をギタリストのようにかき鳴らす。
ギュイィーーィン!
その瞬間、"ネヴァン"から放電され、黒いコウモリ達がどこからともなく現れる。
それらがダンテを追いかけ飛びかかろうとしていた悪魔達に、一斉に襲いかかった。
ぎぎゃーーっっ
コウモリの大群に包まれ強烈な電撃を浴びた悪魔達は、笑う余裕もなくなったのだろう。
悲痛な叫び声と共に一瞬で塵へと変わっていく。
数の多い雑魚相手だと、やはり"ネヴァン"は使い勝手がいい、とダンテは消えて行く悪魔達を眺めながら心底楽しげな笑みを浮かべた。
"ネヴァン"はギターの形状をした雷属性を持つ近距離、中距離型の武器であり、召喚したコウモリを敵に飛ばしたり、周囲に電撃を発生させる攻撃を行う。
これらの攻撃は命中率が非常に高く、確実に敵に命中する。しかも射程は長いので確実に敵にヒットさせられるのだ。
攻撃力はやや低く、上級悪魔向けではないが、雷属性に耐性のある敵でなければ、ほぼ一瞬で消滅させる事が出来る。
「Crazy?Huh!」
ケタケタ笑うカボチャを乗せた本体が矢継ぎ早に攻撃を仕掛けてくるのを軽く回避しながら、派手な電撃を"お菓子"代わりにお見舞いする。
「"Trick or treat!"って叫んでみな!」
"ネヴァン"をかき鳴らし、電撃とコウモリを飛ばしながら、ダンテは数いる悪魔を葬って行く。
元人間だった悪魔達も、ダンテに触れることなく塵へと変わった。
ダンテにしてみれば、自分が意思を持って撃ったり斬ったりするよりは、こうして"ネヴァン"の無作為な攻撃で消えてくれた方が多少なりとも気が楽に感じる。
だからといって、このような結果を招いた悪魔を許す気にはなれないが。――――その時、散らばっていた悪魔達が一斉に移動を始めて固まり始めた。
「Hey!次はどんな魔法を見せてくれる気だ?」
まるで吸い込まれるかのように、悪魔が一つに合体していく様を見て、ダンテは苦笑気味に両手を広げ、煽るように叫んだ。
一体、二体と黒い球体に重なる悪魔は、次第に膨れ上がって行く。
そして最後の一体が合体した時、ダンテの目の前に二メートル以上もある巨大な悪魔が姿を現した。それも今までの形とは全く違う変化をとげている。
「……Wow!カボチャの次は狼ってオチかよ……それが本性なら話は早い……」
無数の悪魔が一つの個体になった姿を見上げながら、ダンテは武器を"ネヴァン"から大剣リべリオンへと変えた。
今までの雑魚とは比べ物にならないくらいの禍々しい魔力を肌で感じたのだ。
この悪魔こそ、が話してた奴に違いない――――と、ダンテは直感した。
≪貴様――――俺の分身を見事に消し去るとは……!一体何者だ?!≫
「おいおいおい……さっきのカボチャと違ってお前はしゃべれんのか?」
バカにしたように笑うダンテに、目の前の悪魔――――狼の姿をしている――――は大きな口をあけて咆哮を上げた。
その耳障りな声にダンテも思わず顔をしかめる。
「笑うだけのさっきの奴は何だったんだ?ったく……うるせえ親玉だぜ」
≪だまれ……!このノデッロ様に逆らうとは生意気な人間め!人間ごとき分身で十分だと分からせてやろう!!≫
ノデッロと名乗った悪魔はそう叫ぶと鋭い爪を一振りさせた。その瞬間、黒い塊が無数に現れ、それはコウモリ、そして人型をした狼へと変化を遂げる。
どうやら、この悪魔は自身の魔力で分身を作りだし、その姿形を自在に変えられるようだ。
(……もしかしたらが会ったっていう悪魔も、コイツの分身かもしれねえな……)
次々に襲ってくる分身悪魔を斬り裂きながら、ダンテは後方へと離れた本体を見上げた。
そう考えれば、バージルが倒したはずの悪魔が未だ存在していてもおかしくはない。
ガァァーーーーッ
周りを囲むコウモリを銃で打ち抜き、飛びかかってくる人狼を大剣でなぎ倒す。
その間も本体との距離を縮めて行くと、ダンテは素早く跳躍し、大木の枝へと飛び乗り更に枝を蹴って頂点へと登った。
「わりぃけど……見下ろされるのは好きじゃねえんだ」
≪お前……!!その動き……人間ではないのか?!≫
ダンテの超人的な攻撃や動きを目の当たりにしたノデッロは驚愕の声を上げながら、大木に上ったせいで目線が同じになったダンテを睨みつける。
だがすぐに、その赤く光った鋭い目が驚愕したように見開かれる。
≪……お、お前……あの時の男か……!!!≫
「あん?どっかで会ったか?」
≪その顔……忘れてないぞ!!≫
ノデッロの様子がおかしい事に気付き、ダンテは軽く首を傾げた。
目の前に対峙した悪魔は、ダンテの姿を間近で見て、前にも会ったかのように言っている。
その態度に、ダンテは一つの仮説をたてた。
「まさか……記憶があるのか?分身に起こった事も――――」
≪やはりあの時の男かぁ!我が身の半分を使った分身には記憶も全て俺の記憶として戻ってくるのだ!その顔も忘れはしないぞ!≫
叫んだのと同時にノデッロは突進してくると、その鋭い爪をダンテの方へ突き出した。
やはりそうか、と内心思いながらダンテはそれを飛んで交わしたが、今まで立っていた枝が大木ごと抉り取られる。
それを横目で見ながら、ダンテは身を翻すと速い動作でノデッロの額に数発の弾を撃ち込む。
しかし硬い体毛に包まれた体を貫通するまでには至らず、小さく舌打ちした。
≪待てぇ!!お前は今度こそこの手で――――≫
「うっせえな!てめえを斬ったのは俺じゃねえっ」
ノデッロの攻撃をギリギリとのところで交わしていく。
だが僅かに掠った爪が、ダンテの肩の辺りを斬り裂いた。
「――――チッ。これ高いんだぜ?」
コートが裂けたのを見て溜息をつく。
思った以上に頑丈なノデッロ相手に銃撃はらちが明かない。
木々をなぎ倒しながら追いかけてくる悪魔に弾を撃ち込みながら、ダンテは地面へ着地すると大剣リべリオンを構えた。
手元に魔力を集中させれば、大剣が青い光をは放ち始める。
≪……お…おおお……そ、その大剣は……≫
ダンテが構えた剣を見てノデッロは驚いたように攻撃を止めた。
「へえ、さすがに知ってるみたいだな」
≪……大剣"リべリオン"……あのスパーダが用いた剣の一つを何故お前のような人間が――――≫
ノデッロはそこまで言うと何かに気付いたように、牙を剥きだしにした口元を震わせた。
それこそダンテの事を上から下まで舐めまわすように見ながら、驚愕の表情を隠そうともしない。
≪その銀髪……青い目……そして大剣リべリオン…!!!お前まさか……スパーダの息子か?!≫
「だったら何だってんだよ?親父の功績を称えて見逃してくれんのか?つっても……てめえには聞きてえ事がある。俺も逃げる気はねえけどな」
≪………?!≫
ダンテの言葉に、ノデッロは訝しげな顔で目を細めた。
そのノデッロ相手に真っすぐリべリオンを向ける。
「てめえ……どうしてを狙う?どうして分身に力を半分与えてまで、あいつと母親の前に姿を現した」
≪……何?!≫
「あのアミュレットを何の為に奪おうとする?」
≪……っ?お前が何故あの石の事を……っ!≫
一瞬驚いたように見えたノデッロは、すぐに気付いたようにニヤリと笑う。
≪……そうか。スパーダの息子……そしてカーロの娘が繋がっていたとしても何ら不思議ではない……≫
「いーから答えろよ」
からその話を聞いた時、ダンテは嫌でも自分の持つアミュレットの事を考えた。
兄バージルが何故ダンテの前に姿を現したのか。その理由は彼の持つ、母親の形見でもあるアミュレットだった。
元々はスパーダがダンテの母、エヴァに渡し、それを息子二人が受け取った物だ。
ダンテとバージルの持つアミュレット二つ揃えば魔界の扉テメンニグルが開く"鍵"になっていたのを知ったのは、バージルと対峙した時だった。
だからこそから自分を狙った悪魔はアミュレットを欲しがっていた、と聞かされた時、ダンテはすぐにその事を懸念した。
聞けば父の形見でもあるという。の父であるカーロもまた、スパーダと同じ悪魔だ。
ならば自分のと同様、何らかの力を持っていると考えていいだろう、とダンテは考えた。
「答えろよワン公。どうしての持つアミュレットを狙う!!何故あいつの知り合いを今更利用してるんだ!」
≪黙れ!!裏切り者の息子に答える必要はないわっ!≫
ノデッロは吠えるように叫ぶと、その怒声が台風のような突風を巻き起こし、ダンテを吹き飛ばそうとする。
気温が高い事で、まさに熱風がダンテを直撃し、ダンテはうんざりした顔でその場に踏み止まった。
≪ふっふふ……しかしそうか……。と言う事はあのガキがまんまと引っ掛かってやって来たという事だな?≫
「……何だと?」
≪あの街を出たガキを探すのも苦労する。おびき寄せる為の罠が上手く言ったって事だろう?≫
「てめえ……それじゃはなからをこの島へおびき寄せる為に―――――」
≪スパーダの息子よ!悪いがお前の相手をしている暇はなくなった……お前には我が分身の相手をしていてもらおう!!≫
「な、おい!ちょっと待て―――――」
突如、竜巻が起こり姿を消したノデッロを慌てて追いかけようとした。
しかし同時に無数の下級悪魔がダンテのゆく手を阻むように現れる。
それは先ほどのカボチャやコウモリ、骸骨に小型の人狼達だ。中にはダンテの姿をした悪魔もいる。
それにはさすがのダンテも溜息をついた。
「あんのワン公…!!俺に雑魚の相手しろってか?!しかも俺の姿までコピーしやがって……!!」
そうボヤきつつ、斬りかかってくる自分の姿をした悪魔を撃ち抜く。
いくら相手が悪魔だと分かってはいても、外見がそっくりなのだから気分のいいものではない。
同時に悪魔のあの様子からしてを探しに行ったのは間違いないだろう。
急がないととレディが危険だと、ダンテは舌打ちした。
「クソ……!あの野郎、覚えてろよ!次に会ったらバージルがやった以上に切り刻んでミートボールにしてやる!!」
恨みごとを吐き捨て、ダンテは銃を構えると、大群で襲いかかってくる悪魔達へ、勢いよく発砲した。
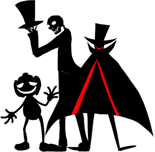
その頃、とレディも下級悪魔を次々に退治しながら、先を進んでいた。
次第に高くなる気温に、レディは少々バテ気味だ。
「ねえ……この島ホントに一年中この暑さなの?」
「そうよ。騎士をしてた頃、何度か見回り任務の為に訪れた事があるけど……何も変わってないわね」
「そう……っていうかはそんなコート着てて暑くないわけ?」
「まあ……暑いけど肌を出して虫に刺されたくないし」
「……私は虫に刺された方がマシだわ……もう我慢できない」
そう言ってレディは着ていたシャツを脱いで下着一枚という格好になってしまった。
「この先にダンテがいるかもしれないのにいいの?」
「あいつがいたら、コレでふっ飛ばすからいいわ…」
背中に背負うカリーナ・アンを軽く持ち上げ、レディは騒動な事を平気で口にしている。
さすが、初対面でダンテの額に穴をあけた人物だ。
「自分で脱いだのに、ダンテにしたらいい迷惑ね」
はレディの理不尽さに苦笑を洩らしつつ、島へ着いた時より歩く速度を落としながら、けもの道を歩いて行く。
あまりの暑さのせいで、行く先には蜃気楼が見えるほどだ。
いつ悪魔と戦闘になっても動けるよう、二人は水で渇いた喉を潤し、時々休憩を取りつつ先へと進む。
そしてやっと中間地点付近へと到着したは、確かこの先にスパーダの石像があったはずだ、と辺りを見渡した。
レディはすでに息を切らしながら、重たい武器を抱え直している。
「の住んでた街もこんなに暑いわけ?」
「ううん。フォルトゥナはどっちかと言えば涼しいところだったわ。夜になれば寒いくらい」
「嘘〜。じゃあ何でこの島だけ暑いの?さっきいたボルゴって街だって、こんなに暑くなかったわ……」
「さあ……何で暑いのかなんて知らないけど……私が生まれた時からすでに暑かったらしいの。もしかしたら島の真下にマグマか何かあるのかも―――――」
言いながらはふと足を止めた。それに気付かずレディが歩いて来て、ドンっとの背中にぶつかる。
「何よ〜どうしたの?」
しゃべるのも億劫な様子でレディが顔を上げる。しかしは目の前の光景を見て、すぐさま銃を握りしめた。
「……何?悪魔?」
「多分、ね。――――見て。あの石像の辺り……戦闘の跡があるわ」
が前方を指差せば、レディも「ホントだ」と大型の銃剣を携えたランチャーを構える。
よくよく辺りを見渡せば、周りの木々はところどころに抉られ、銃や剣で傷つけられた痕跡があり、ここで激しい戦闘があったのは間違いなさそうだ。
「ダンテかしら。それともの元お仲間?」
「……多分ダンテだわ。無数の銃痕があるし。騎士団の連中は銃器なんか使わない」
「そう。ならこの先に行けばダンテがいるって事ね。もしかしたらの探してる奴もとっくに葬ってるかもよ――――」
レディがそう言った瞬間、は空中目がけて<イリーナ>をぶっ放していた。コンマ数秒で穴だらけにされた悪魔が一瞬で塵となって消える。
「……そうでもないみたいね」
「何やってんだか、あいつは」
先を越されたとばかりにレディもランチャーをぶっ放す。
いつの間にか周りを囲んでいる悪魔は、先ほどのカボチャみたいな形態とは少し違うようだ。
「今度はコウモリってわけ?とことんパーティ好きな悪魔ね。そのうちヴァンパイアとかフランケンシュタインなんてのまで出たりして」
「レディのリクエストに応えてくれたみたいよ!」
「……嘘でしょ」
が銃を撃つ方向へ目をやり、レディは本気でウンザリしたように息を吐き出した。
と言うのも、飛んでいたコウモリが一瞬でその姿を変えて襲ってきたからだ。
ガァァァッッ
シャァァッ!
ヴァンパイアの姿をした悪魔が牙をむき出しにして飛びかかってくるのを軽く交わすと、レディは銃剣でその悪魔を貫いた。
見事に心臓を突き刺したらしい。ヴァンパイアの姿をした悪魔は耳障りな悲鳴を上げる。
レディはそれを突き刺したまま遠くへと吹き飛ばし、次に攻撃してきた巨体にもランチャーをぶっ放す。
近距離でミサイルを撃ち込まれた悪魔―――こっちはフランケンらしい―――は、たまらないというように「ぐぉぉ!」という悲鳴と共に消滅した。
「ざまみろってのよ。――――次はミイラ男だったりしてね!」
他の悪魔もハンドガンで撃ち落としながら、レディが冗談めかして笑う。
が、てっきり「やめてよ」と苦笑交じりの返事が返ってくるかと思えば何の応答もない。
レディは攻撃をしながらも、訝しげに首を傾げた。
「何?返事する余裕もないの?――――」
言いながら振り返って唖然とした。
「……?」
襲って来るコウモリを撃ち落としながらも、レディは驚いたように辺りを見渡す。
しかしどこにもの姿はなかった。数秒前まで、すぐ傍にいたのだ。こんな忽然と消えるなんてありえない。
「やだ……どこ行ったのよ。―――――!!」
大きな声で呼んでみても、からの応答はなく、レディはキツネにつままれたような気分になった。
と言って、気を散らしていては次々に現れる悪魔に攻撃されてしまう為、銃を撃つ手は休めない。
下級悪魔でも大量に出ると一人ではきついのだ。
「嘘でしょ〜?どうなってんのよ、もう!」
そう文句を言ってみたところでが姿を現す気配はなく、周りには悪魔しかいない。
とりあえずを探す前に、こいつらだけは始末しよう、とレディは悪魔の攻撃をかわし、ランチャーをぶっ放した。
一方、はと言えば――――レディが言うように"どこへ行った"わけでもなく。
先ほどと全く同じ場所で悪魔と戦っていた。
もまた、忽然と消えたレディに驚いていたのだ。
ただレディと違うのは、何故急に彼女が姿を消したのか、という理由を、は気付いている。
「結界、か。面白い事してくれるじゃない」
普通の人間には見えにくいだろうが、の眼にはクモの巣のような結界がハッキリと見えている。
騎士だった頃も何度となく目にしていたものだ。
この場合、同じ場所で戦っていながら、互いに別次元にいる、という事だろう。
この結界は仕掛けた悪魔達を消滅させない限り消えて無くならないのだ。
「私とレディ相手じゃ分が悪いから分散させて襲おうっての?雑魚がいくら集まったって無駄よ!」
コウモリ、カボチャ、ヴァンパイア、骸骨にフランケンシュタイン。ご丁寧に鎌を持った死神のような悪魔までいる。
これだけ集まるとまるで安っぽいホラー映画みたいね、と内心苦笑しながら、は両手に魔力を溜め始めた。
雑魚相手に時間を食ってる暇はない。ここは一気に全滅させるのが一番手っ取り早い、とはデビルトリガーを引いた。
その瞬間、の両手から瞬時に炎が噴き出し、ゆらゆらと怪しい色で燃えている。
「さっきはレディに気を遣って使えなかったけど……傍にいても感じなければ関係ない。全開で行かせてもらうわ!」
叫ぶのと同時に一気に跳躍したは、燃え盛る手を悪魔へと翳した。
その刹那――――劫火が爆発したように周りにあるもの全てを焼きつくしていく。
無数の悪魔達の悲鳴を聴きながら、は口元を僅かに上げると、大木を足場に勢いをつけ更に後方の悪魔へと炎を放つ。
一瞬で燃えて消滅していく悪魔達もいれば、燃えてもなお攻撃を仕掛けてくる悪魔がいるが、それもの騎士剣<ベローナ>で、灰になる前に切り刻まれた。
イクシードと魔力で操る炎をプラスすればその威力は何倍にもなる。
数分後には、あれだけいた悪魔達も全て全滅していた。ついでに周りの木々も焼け、黒こげになってしまっている。
「……やりすぎちゃったわね」
両手の炎を消し、騎士剣を背中に収めると、は身軽な動作で着地し、苦笑交じりで頭を掻いた。
ぱちぱちと音を立て、辺りの木々が未だに燃えているせいか、更にの周りの気温が上昇している。
それなのに、今のにはそれほど暑くは感じなかった。
元々フォルトゥナは暑い気候の街ではないし、も暑さに強いというわけではない。
しかしこの島の暑さだけは、何となく彼女にとって心地よく感じるのだ。
「これもパパの力を受け継いでるっていうのかな……」
炎を自在に操った自らの手を眺めながら呟く。
この技も何度か集中して練習したところ、出来るようになったものだ。
母イリーナが亡くなった時に一度、無意識で使った力だが、今では多少難しいものの、コントロール出来るようにまでなっていた。
あのマンナーロも言っていたが、後でカーロの事を知るダンテに詳しく聞いたところ、の父は炎を操る悪魔だったという。
"炎帝カーロ"
地獄の業火に耐え抜き、その極炎をも我がものにした帝王――――そういう意味も込めて悪魔達から恐れ崇められていた父。
その父が尊敬し仕えていたスパーダは、どれほどの悪魔だったんだろう。
「英雄スパーダの歴史に、自分の父親がいるなんて変な感じね」
そんな事を呟きながら苦笑する。そしてふと思い出したように辺りを見渡した。
「いけない……レディ探さないと」
悪魔を全滅させたのだから結界はすでに解けているだろう、とは先を歩き出した。
だがスパーダの石像前まで歩いても、一向にレディは姿を現さない。
「やだ。どうしたんだろ。まさか場所までワープしちゃってたりしないわよね」
それともレディの方も悪魔を全滅させなければ元に戻れないのだろうか?
あれこれ考えながらは30分ほど、その場で待ってみたが、レディが戻ってくる気配はない。
は溜息をつきながら、ゆっくりと立ち上がった。
「……もしかして気付かないうちに先へ行っちゃったとか?」
ふと石像の後ろに見えるトンネルへ視線を向け、首を傾げる。
そういえばダンテはどこにいるんだろう、と疑問が沸いた。
てっきり、この辺りで待っているだろうと思っていたが、思惑は外れたようだ。
といって、いつまでもこうしているわけにも行かず―――サガロ達の事もある―――は仕方なく先へ進んで見る事にした。
「はあ……協調性のない相棒を持つと苦労するわ」
そんな事を独りボヤきながら、トンネルの中へと入る。ここから先はも足を踏み入れた事はなかった。
「……確かこの先に封印結界があるのよね」
薄暗いトンネルをゆっくりと進む。まだ昼間だというのに不気味なほど静かだ。
本当にサガロ達はこの島にいるんだろうか、という疑問さえ湧いてくる。
だが長いトンネルを抜けたところで、は驚いたように足を止めた。
そこは少し開けた空間になっていた。だが正面には岩で出来た細長い橋のような通路があり、両サイドは切りだった崖になっている。
そしてそれを渡り切ったところに洞窟があり、その入り口には結界が張られていた。
しかしを驚かせたのは、その洞窟でも切りだった崖でもない。
渡る足場の手前に倒れていた、数人の騎士の姿だった。その中には、あのサガロの姿もある。
「――――サガロ騎士長!」
サガロの姿を見つけた瞬間、は駆けだし彼の体を抱き起こしていた。
「サガロ騎士長!シッカリして下さい!!サガロ騎士長!」
体中に怪我はしているものの、僅かに息がある事に気付いたは、大声でサガロを呼ぶ。
何度かそれを繰り返している内に、サガロが小さく咽かえりながら、うっすらと目を開けた。
「サガロ騎士長?」
「……お前……か……?」
「大丈夫ですか?!」
「な……何故lここにお前が……」
「シェスタから電話をもらったんです……。ミハエルの事だから私も駆けつけました」
「そ……そう、か……う……ゴホッ……」
「大丈夫ですか?」
苦しげに咳込むサガロの背中をは慌ててさすった。
サガロはかなりの重症のようだ。は他の騎士達にも視線を向けたが、他の者は全滅しているようだった。
「………」
「あまり話さない方が……」
「い、いい。大丈夫…だ…。それより……ミハエル…騎士長が連れ去られ…た……」
「え……?!」
そのサガロの言葉はを驚愕させるものだった。
「まさか……本当にミハエルが……いたんですか?」
「……あ…あ……会った…。彼に…間違いない……悪…魔に…囚われている…」
「悪魔……?もしかしてその悪魔って―――――」
「お前……が話してた奴…だろう……。狼…のような奴だ…。ミハエル騎士長は……奴に精神を囚われてい…る…だけだ…。死んで…はいなかったんだ……」
「……死んでない……?でも――――」
「……あの悪魔を…倒せ……ば解放される…。頼…む。…お前が……」
サガロの言葉に、は耳を疑った。ミハエルが生きていてくれるならだってどれほど嬉しいだろう。
だがその話をすぐには信じられない。といって、サガロの言葉に希望をつなげておきたい気持ちもある。
「分かりました。私が行ってきます…。サガロ騎士長はここにいて下さい」
「……頼…む…」
哀願するような弱々しい声。
サガロがこんな風に頼みごとをする姿など見た事がない。
は軽く頷き静かに立ち上がると、<イリーナ>を片手に細い足場を渡って行く。
左右は崖。底は暗いせいでよく見えない。
真ん中まで歩いてくると、悪魔特有の匂いが更に濃くなり鼻をついた。
正面に見える洞窟の中には間違いなく、悪魔がいるようだ。
洞窟前まで歩いて行くと、は結界の奥に見える通路を目を凝らして見てみた。
「この中にミハエルが連れて行かれたっていうの……?でもどうやって結界の中に……?」
伝え聞いた話ではスパーダが張った結界だったはずだ。それをいとも簡単に通り抜けられたというのもおかしい気がする。
しかし確かに何かが動く気配がする。
「っていっても……この封印結界、どう壊せばいいのよ……。スパーダの張ったものはいくら私でも無理――――」
そう呟いた時だった。
胸元が突然熱く感じ、は慌ててコートに隠れているアミュレットに触れてみた。
同時に熱が解放されるかの如く、真っ赤に光りだし、目の前の結界と呼応しているように感じる。
「な……何なのこれ……見えない力が呼びあってる?」
アミュレットから結界へ力が流れ込む、そして結界からは力を注がれているような感覚になり、は小さく息を呑んだ。
次第に膨らんでいくパワーにどうする事も出来ない。その時、パァァァン!という音が響き、同時に目の前の結界が弾け飛んだ。
「嘘……結界が……」
目の前にあった結界が見事に消え去り、は一瞬唖然とした。
そしてその洞窟の奥へと目を向けた時、の表情が驚愕のものへと変わる。
「――――ミハエル!!」
洞窟の奥に倒れていたのは、あの夜の目の前で死んだはずのミハエルだった。
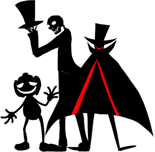
同じ頃、ダンテはやっとの事で雑魚を全滅させていた。
あのノデッロの"置き土産"は相当の数で、さすがのダンテも苦戦したようだ。
「あの野郎……余計な手間取らせやがって……」
暑い中で暴れれば、それなりに体力を消耗する。
それは半魔のダンテとて同じ事だ。
幸い水はまだあるものの、食料は先ほど食べてしまった。
しかもあれだけでは到底足りない。ダンテは暑さと空腹でフラフラになりながら、石像の前まで戻って来た。
「あ〜いけね……。放りだしたままだったぜ。まーた文句言われちまう」
足元に落ちている"ネヴァン"を拾い上げ、苦笑する。
先ほどノデッロと対峙した時、リべリオンを引きぬくと同時に遠くへ放り投げたのだ。
ダンテは軽く土を払ってやると、"ネヴァン"をすぐにケースへ戻そうとした。
だが若干懸念していた事が現実になり、少しだけスネた声が頭の中に響いてきた。
≪……ひどいじゃない?レディを放り投げるなんて≫
その声に反応し、手元の"ネヴァン"を見下ろす。
今はこのような形状の武器だが、元はセクシーな女悪魔である。
主であるダンテに放り投げられた事が彼女のプライドを傷つけたようだ。
ダンテも苦笑交じりで、「わりぃわりぃ」と頭を掻いた。
「でもまあ何つーか……戦闘中に優しく置いたりしまったり出来ねえだろ?」
≪だからってアレはないわよ。お尻をしたたか打って痛かったわ≫
「だから悪かったって。今度からはなるべく優しく扱ってやるからスネんなよ」
ダンテはそう言いながら"ネヴァン"の表面を撫でる。
瞬間、ビリリっと電気が走り、本体から紫色の電撃がダンテの指先をしびれさせた。
「いってえな……」
≪いやらしいわね……どこ触ってるのよ。戦闘以外で私の体に気易く触らないでちょうだい≫
「ああ?どこって表面に触れただけじゃねえか」
≪デリカシーのない男は嫌いよ……あと私を雑に扱う男にはお仕置きしなくちゃ。次やったら倍の電流、流しちゃうから≫
「……はいはい。ったく……俺の周りには乱暴な女しかいねえのかよ」
指先のしびれに顔をしかめつつ、"ネヴァン"をケースへと戻し、しっかりとジッパーを閉める。
そして深々と息を吐き出し、それを背負った。
「今度は違う奴にすっか……。つっても後は"氷漬けのワン公"と、"おしゃべりな兄弟"くらいしかねえしな……参るぜ」
事務所に置いてきた他の魔具を思い出し、再び溜息をつくと、ダンテは静かに立ち上がる。
見れば結界も消えているようだ。
「ま、これで先に進めるな。―――――しっかし、あちぃっ」
先ほど暴れた為、喉が渇いたダンテは、水を煽りながらトンネルへと歩いて行く。その時―――――
「―――――きゃあぁぁぁぁっ!!」
「…………?!」
奥からの悲鳴が響いて来て、ダンテは一気に駆けだした。
<<< □ >>>